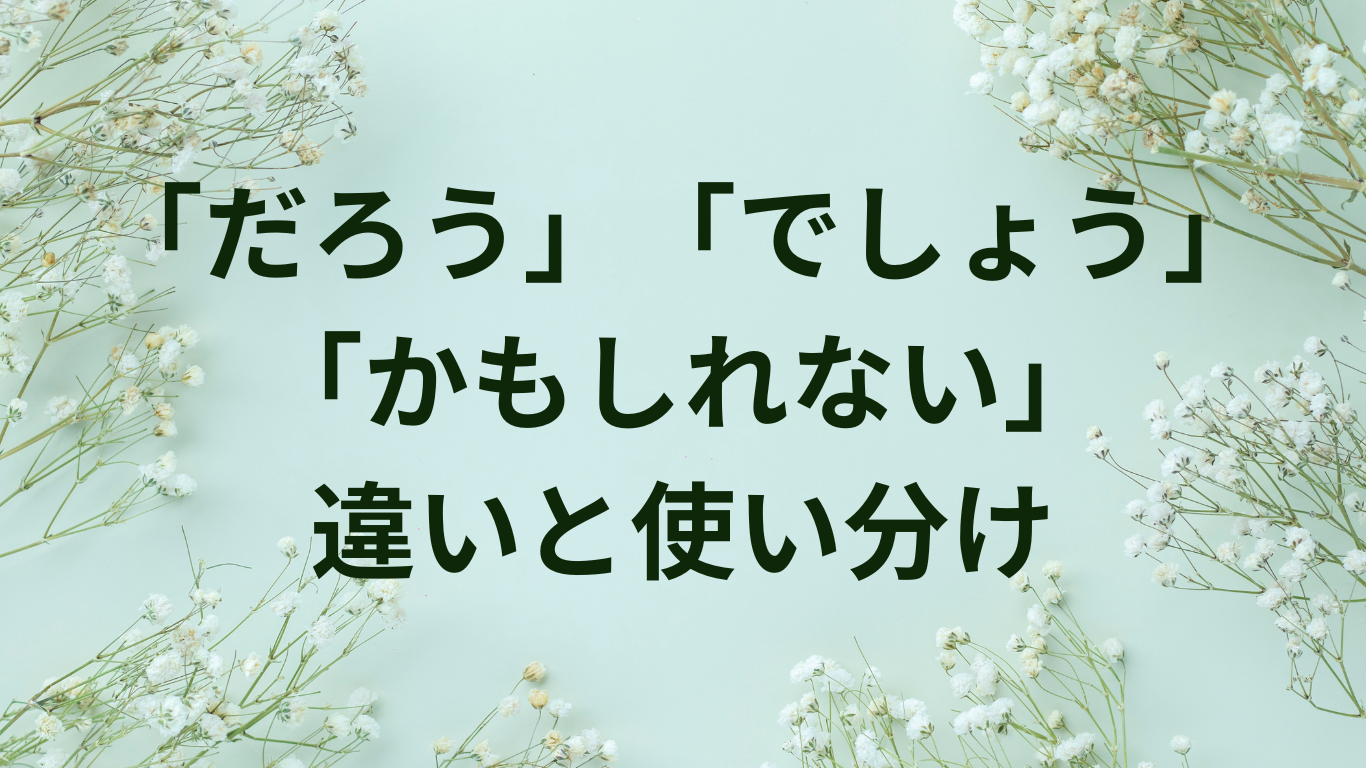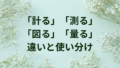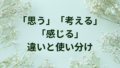「明日は雨が降るだろう」
「明日は雨が降るでしょう」
「明日は雨が降るかもしれない」
—これらの表現には微妙な確信度の違いがあります。
日本語の推量表現は、話し手の確信の強さや状況によって使い分けるべきものですが、その境界線が曖昧で迷うことも多いでしょう。
本記事では「だろう」「でしょう」「かもしれない」の意味の違いと適切な使い分けを徹底解説します。
それぞれの表現が持つニュアンスを理解して、より正確で豊かな日本語表現を身につけましょう。
基本的な意味の違い

「だろう」「でしょう」「かもしれない」は、いずれも推量を表す表現ですが、確信度や丁寧さのレベルに明確な違いがあります。
「だろう」
「だろう」は比較的高い確信度を持つ断定的な推量表現です。
話し手が自分の判断に自信を持っており、ほぼ間違いないと思っていることを表します。
くだけた表現であり、フォーマルな場面では避けられることもあります。
「でしょう」
「でしょう」は「だろう」の丁寧な形で、同様に高い確信度を持ちますが、話し手の判断を押し付けず、聞き手への配慮を含みます。
フォーマルな場面でも使用できる汎用性の高い表現です。
「かもしれない」
「かもしれない」は可能性を示す表現で、確信度は「だろう」「でしょう」より低くなります。
「そうなる可能性がある」という程度の推測を表し、話し手の判断に不確実性があることを示します。
これらの違いは、天気予報に例えると分かりやすいでしょう。
「明日は雨が降るだろう」は90%以上の確率で雨を予測している状態、「明日は雨が降るでしょう」は同様の高確率だが丁寧に伝えている状態、「明日は雨が降るかもしれない」は50%程度の確率で述べている状態と考えられます。
使い分けのポイント

これらの表現は場面や状況、話し手の意図によって使い分けるべきです。
以下に、シーン別の適切な使い分けを整理します。
フォーマル度による使い分け
| 表現 | フォーマル度 | 適切な場面 |
|---|---|---|
| だろう | 低(カジュアル) | 友人との会話、独り言、文学的表現 |
| でしょう | 中~高 | ビジネス会話、目上の人との会話、公式の場 |
| かもしれない | 中 | カジュアル~フォーマルまで幅広く使用可能 |
確信度による使い分け
| 表現 | 確信度 | 使用例 |
|---|---|---|
| だろう | 高(70-100%) | 「彼なら合格するだろう」(ほぼ確実) |
| でしょう | 高(70-100%) | 「この方法が最適でしょう」(確信あり) |
| かもしれない | 中(30-70%) | 「遅れるかもしれない」(可能性あり) |
コミュニケーション意図による使い分け
- 断定的な意見を述べる場合: 「だろう」「でしょう」 例)「この方針で成功するだろう」
- 控えめに意見を述べる場合: 「かもしれない」 例)「別のアプローチも効果的かもしれない」
- 相手の意見に同意する場合: 「でしょう」 例)「おっしゃる通りでしょう」
- 推測を述べる場合: 状況や確信度に応じて使い分け 例)「彼は既に到着しているだろう/でしょう」(高確信度) 例)「彼はまだ途中かもしれない」(中程度の確信度)
よくある間違い & 誤用例

これらの表現の誤用は、意図しないニュアンスを伝えてしまう恐れがあります。
以下によくある間違いとその修正例を示します。
確信度と表現の不一致
🚫 「間違いなく雨が降るかもしれない」
✅ 「間違いなく雨が降るでしょう」
「間違いなく」という高確信度の副詞と、「かもしれない」という中程度の確信度の表現が矛盾しています。
フォーマル場面での不適切な表現
🚫 (ビジネスプレゼンで)「この戦略が効果的だろう」
✅ 「この戦略が効果的でしょう」
ビジネスシーンでは「だろう」よりも丁寧な「でしょう」が適切です。
断定すべきでない場面での過度な確信表現
🚫 (不確実な情報に基づいて)「明日の会議は中止になるだろう」
✅ 「明日の会議は中止になるかもしれない」
不確実な情報に基づく推測には、確信度の低い「かもしれない」が適切です。
婉曲表現が必要な場面での直接的表現
🚫 (上司の意見に対して)「それは間違っているだろう」
✅ 「それは別の見方もあるかもしれません」
特に上下関係がある場面では、直接的な反論より婉曲的な表現が適切です。
文化的背景・歴史的背景
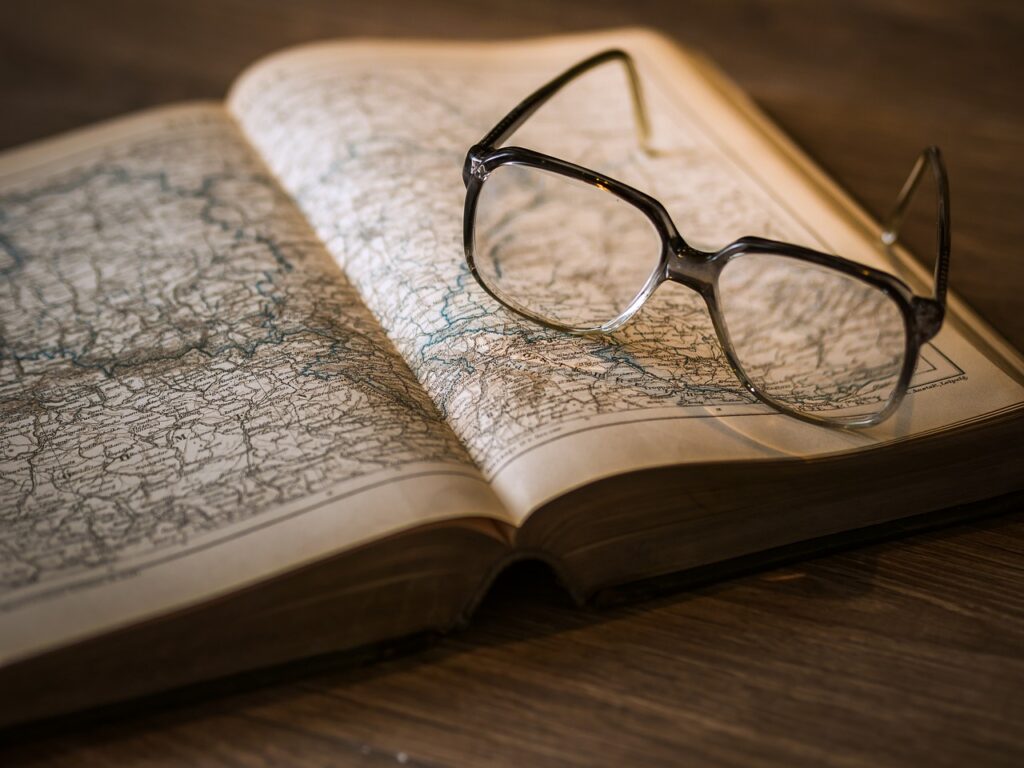
日本語の推量表現の使い分けには、日本文化特有の「配慮」や「遠慮」の概念が反映されています。
「だろう」の歴史
「だろう」は「である」+「あろう」から変化した表現で、古くは断定的な判断を表していました。
時代が下るにつれて、カジュアルな表現として定着していきました。
「でしょう」の発展
「でしょう」は「です」+「あろう」から派生し、明治時代以降、丁寧語として広く使用されるようになりました。
特に近代以降のビジネスコミュニケーションの発展と共に、フォーマルな場での標準的な推量表現となっています。
「かもしれない」の文化的背景
「かもしれない」という表現には、日本文化における「断定を避ける」という対人配慮の考え方が表れています。
特に日本社会では、自分の意見を押し付けず、可能性を示すことで相手に選択の余地を残す表現が好まれる傾向があります。
この三つの表現の適切な使い分けは、日本語のコミュニケーションにおける「以心伝心」や「察する文化」と深く関連しています。
実践的な例文集
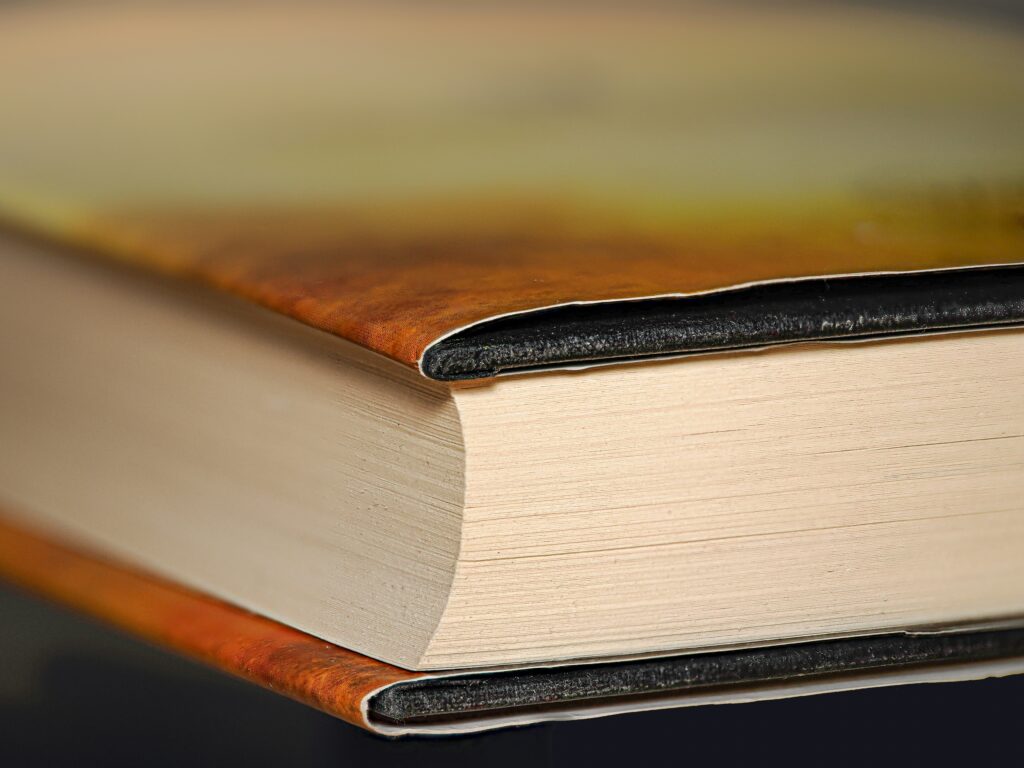
それぞれの表現の適切な使い方を、様々な場面での例文で見ていきましょう。
日常会話での使用例
- 「この映画は面白いだろう」(友人に自信を持って薦める)
- 「明日は混雑するでしょうね」(丁寧に予測を伝える)
- 「電車が遅れるかもしれないから、早めに家を出よう」(可能性を考慮)
ビジネスシーンでの使用例
- 「このプロジェクトは成功するでしょう」(肯定的な見通しを丁寧に伝える)
- 「予算超過の可能性があるかもしれません」(リスクを控えめに伝える)
- 「御社の提案は非常に魅力的でしょう」(相手の立場を尊重した推測)
学術・論文での使用例
- 「この結果から、AとBには相関関係があるといえるだろう」(論文での結論)
- 「複数の要因が影響しているかもしれない」(可能性を示す考察)
- 「今後の研究でさらに明らかになるでしょう」(将来の展望)
メールでの使用例
- 「ご多忙中とは存じますが、ご検討いただけますでしょうか」(丁寧な依頼)
- 「当日は交通機関の乱れがあるかもしれませんので、お早めにお越しください」(注意喚起)
- 「添付資料をご確認いただければ、ご理解いただけるでしょう」(丁寧な説明)
言い換え表現
- 「だろう」→「と思われる」「と考えられる」
- 「でしょう」→「と存じます」「かと思います」
- 「かもしれない」→「可能性があります」「恐れがあります」
まとめ
「だろう」「でしょう」「かもしれない」は、話し手の確信度と丁寧さのレベルによって使い分ける推量表現です。
適切な使い分けのためには、以下のポイントを押さえておきましょう。
覚えておきたいポイント
- 「だろう」は高い確信度を持つカジュアルな表現
- 「でしょう」は高い確信度を持つ丁寧な表現
- 「かもしれない」は中程度の確信度を示す表現
- 場面や相手との関係性に応じて適切に使い分ける
- 確信度と表現のレベルを一致させる
- 文化的背景や対人配慮を意識する
これらの推量表現を適切に使い分けることで、より豊かで正確なコミュニケーションが可能になります。
状況や意図に合わせた表現選びを心がけ、日本語表現の幅を広げていきましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1: 「だろう」と「でしょう」は確信度が同じなのですか?
A: 基本的に両者の確信度は同程度(高い)ですが、「でしょう」は丁寧さが加わります。
また、場面によっては「でしょう」の方が若干控えめなニュアンスになることもあります。
Q2: ビジネスシーンでは「かもしれない」を使っても問題ないですか?
A: はい、「かもしれない」はフォーマルな場面でも使用できます。
特にリスクや不確実性を伝える際に適しています。
より丁寧にする場合は「かもしれません」の形になります。
Q3: 「だろう」「でしょう」「かもしれない」以外の推量表現はありますか?
A: はい、他にも「はずだ」(高確信度)、「と思う」(個人的見解)、「ようだ/みたいだ」(様子から推測)などがあります。
それぞれニュアンスが異なるので、状況に応じて使い分けると良いでしょう。
Q4: 論文やレポートではどの表現が適切ですか?
A: 学術的な文章では「だろう」が一般的です。
これは論文が「である調」で書かれることが多いためです。
ただし、確信度が低い場合は「かもしれない」を使用することも適切です。
Q5: 「きっとだろう」「たぶんでしょう」のように副詞と組み合わせても良いですか?
A: はい、確信度を強調したり調整したりするために副詞と組み合わせることができます。
ただし、「絶対にかもしれない」のように矛盾する組み合わせは避けるべきです。