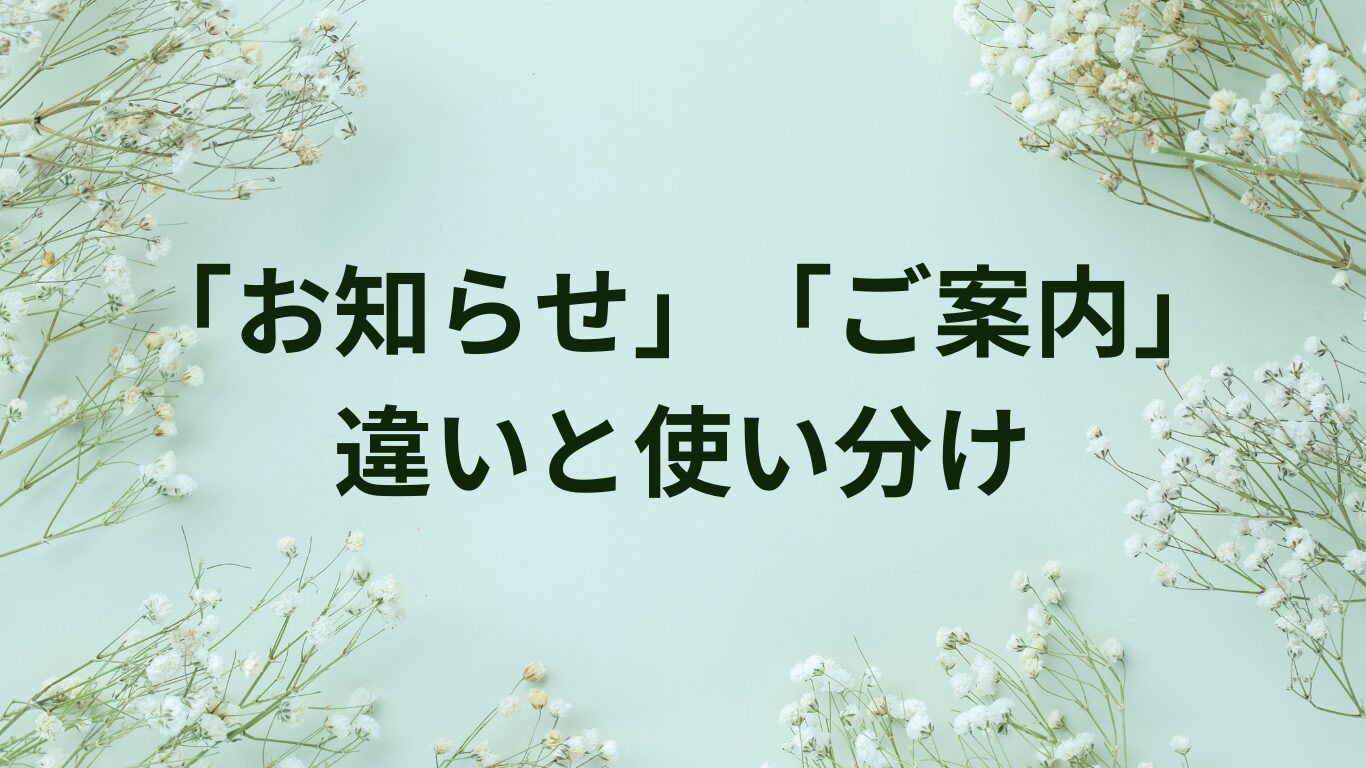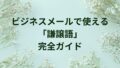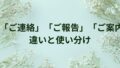ビジネス文書で「お知らせ」と「ご案内」、どちらを使うべきか迷ったことはありませんか?
この2つの言葉は似ているようで異なる意味と用途を持ちます。
この記事では、それぞれの適切な使い方と使い分けのポイントを解説します。
この記事でわかること
- 「お知らせ」と「ご案内」の明確な意味の違い
- 文書の目的別・相手別の正しい選び方
- よくある誤用例と修正ポイント
- すぐに使える状況別の文例集
基本的な意味の違い
「お知らせ」と「ご案内」は、ビジネス文書でよく使われる表現ですが、その意味と使用場面には明確な違いがあります。
「お知らせ」の基本的な意味
「お知らせ」は、主に「情報を相手に伝える」という意味を持ちます。
すでに決定した事実や情報を一方的に通知する際に用います。
お知らせの特徴:
- 決定事項の通知
- 一方的な情報提供
- 相手の行動を必ずしも促さない
- 報告的な性質
「ご案内」の基本的な意味
「ご案内」は、「道筋を示す」「誘導する」という意味を持ちます。
相手に何らかの行動や判断を促す場合や、詳細な情報とともに招待する場合に使用します。
ご案内の特徴:
- 行動や参加を促す
- 詳細情報の提供を伴う
- 相手に選択や判断を委ねる
- 誘導的な性質
比較表
| 項目 | お知らせ | ご案内 |
|---|---|---|
| 目的 | 情報通知 | 行動促進・招待 |
| 方向性 | 一方向(発信者→受信者) | 双方向(発信者⇄受信者) |
| 相手の行動 | 必ずしも必要としない | 期待する傾向がある |
| 内容例 | 休業日、人事異動、価格改定など | イベント開催、キャンペーン、新サービスなど |
| 文書タイプ | 通達、告知、報告 | 招待状、募集、説明 |
使い分けのポイント
「お知らせ」と「ご案内」をビジネスシーンで適切に使い分けるためのポイントを紹介します。
目的による使い分け
「お知らせ」を使うべき場面
- 決定事項の通知:「弊社の夏季休業日についてお知らせいたします」
- 変更の報告:「営業時間変更のお知らせ」
- お詫びや経過報告:「システム障害に関するお知らせ」
「ご案内」を使うべき場面
- イベントへの招待:「セミナー開催のご案内」
- 新サービスの紹介:「新商品発売のご案内」
- 申込みの促進:「年末調整書類提出のご案内」
相手別の使い分け
社内向け文書
- 社内連絡では基本的に「お知らせ」を使用することが多い
- 例:「社内システムメンテナンスのお知らせ」「年末年始休業のお知らせ」
社外向け文書
- 顧客への情報提供は内容によって使い分ける
- 単純な事実通知→「お知らせ」:「価格改定のお知らせ」
- 行動を促す場合→「ご案内」:「展示会へのご案内」
取引先向け文書
- 丁寧さを重視する場合は「ご案内」を選ぶことが多い
- 特に重要な取引先には「ご案内」で丁寧に伝える
文書の性質による使い分け
フォーマル度の違い
- 「ご案内」の方が若干フォーマルで丁寧な印象
- 重要な案件や公式文書では「ご案内」を好む傾向
情報量による違い
- 詳細な説明を伴う場合→「ご案内」
- 簡潔な通知のみの場合→「お知らせ」
よくある間違いと誤用例
「お知らせ」と「ご案内」の誤用例と正しい使い方を紹介します。
「お知らせ」を使うべき場面で「ご案内」を使う誤り
🚫 誤用例: 「弊社の定休日変更についてご案内いたします」
✅ 正しい例: 「弊社の定休日変更についてお知らせいたします」
解説
すでに決定した事項の通知は「お知らせ」が適切です。
相手に行動を促すわけではない単純な情報提供には「お知らせ」を使いましょう。
「ご案内」を使うべき場面で「お知らせ」を使う誤り
🚫 誤用例: 「新商品発表会へのご参加をお知らせいたします」
✅ 正しい例: 「新商品発表会へのご参加をご案内いたします」
解説
イベントへの参加を促す場合は「ご案内」が適切です。
相手の行動を期待する内容には「ご案内」を使いましょう。
タイトルと本文での不一致
🚫 誤用例: タイトル:「セミナー開催のお知らせ」 本文:「下記の通りセミナーを開催いたしますので、ぜひご参加ください」
✅ 正しい例: タイトル:「セミナー開催のご案内」 本文:「下記の通りセミナーを開催いたしますので、ぜひご参加ください」
解説
タイトルと本文の内容を一致させましょう。
参加を促すセミナー案内は「ご案内」が適切です。
両方を併記する冗長な表現
🚫 誤用例: 「価格改定に関するお知らせとご案内」
✅ 正しい例: 「価格改定に関するお知らせ」
解説
「お知らせ」と「ご案内」を併記すると冗長になります。
内容に合わせて適切な方を選びましょう。
実践的な例文集
実際のビジネスシーンで使える「お知らせ」と「ご案内」の例文を紹介します。
「お知らせ」の例文
休業日のお知らせ
「誠に勝手ながら、弊社では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
休業期間:2025年8月13日(水)~2025年8月16日(土)」
人事異動のお知らせ
「下記の通り人事異動がございましたので、お知らせいたします。
今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
異動内容: 山田太郎 営業部長(前:営業次長) 佐藤花子 マーケティング部長(前:営業部長)」
システムメンテナンスのお知らせ
「システムメンテナンスのため、下記の日時にサービスをご利用いただけません。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
日時:2025年5月20日(火)午前2時~午前5時」
価格改定のお知らせ
「平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。誠に恐縮ではございますが、原材料価格の高騰により、2025年6月1日より下記の通り価格を改定させていただきます。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。」
「ご案内」の例文
セミナー開催のご案内
「拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、このたび弊社では『最新マーケティング戦略セミナー』を開催する運びとなりました。
つきましては、ぜひともご参加いただきたく、下記の通りご案内申し上げます。
日時:2025年6月15日(火)14:00~17:00 場所:東京国際フォーラム会議室A 参加費:無料(事前登録制)」
新サービス開始のご案内
「平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
このたび、弊社では新サービス『クラウドバックアップPro』を開始する運びとなりました。
つきましては、サービスの概要と特長について下記の通りご案内申し上げます。
サービス開始日:2025年7月1日 月額料金:5,000円(税別) 特長:24時間自動バックアップ、無制限ストレージ、多要素認証」
展示会出展のご案内
「拝啓 貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます。
さて、弊社は下記の通り『国際IoTソリューション展』に出展いたします。
最新製品のデモンストレーションを行いますので、ぜひご来場いただきたくご案内申し上げます。
日程:2025年9月10日(水)~12日(金) 会場:東京ビッグサイト 東展示棟 ブース番号:East 4-B25 招待券:本メールの添付ファイルをご利用ください」
キャンペーンのご案内
「日頃より弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
この度、日頃の感謝を込めまして、『サマースペシャルキャンペーン』を実施いたします。
期間中は全商品20%オフでご提供いたしますので、この機会にぜひご利用ください。
期間:2025年7月1日~7月31日 対象:全商品 特典:購入金額の20%オフ 応募方法:特設サイトからのお申し込み」
「お知らせ」「ご案内」の語源と変遷
「お知らせ」と「ご案内」の歴史的背景と使われ方の変化を理解することで、より適切に使い分けることができます。
言葉の由来と語源
「お知らせ」の語源
「知らせる」という動詞に丁寧語の接頭辞「お」をつけた言葉です。
「知る」という日本古来の言葉が語源で、平安時代から「人に情報を与える」という意味で使われてきました。
「ご案内」の語源
「案内」は元々中国語由来の言葉で、「道を示す」「導く」という意味を持ちます。
日本では奈良時代から使用され、接頭辞「ご」をつけて丁寧な表現となりました。
ビジネス文書における変遷
戦前・戦後の使い分け
- 戦前:身分制度を反映し、厳格に使い分け
- 戦後:民主化により徐々に簡略化、実用性重視へ
現代のデジタル時代での変化
- メール文化の普及により、より簡潔な表現を好む傾向
- Webサイトでは「お知らせ」が情報カテゴリとして定着
- 「ご案内」はより公式・フォーマルな印象が強まる
業界による使い分けの特徴
金融・保険業界
「ご案内」を多用する傾向(商品案内、サービス変更など)
IT・通信業界
「お知らせ」を好む傾向(サービス状況、メンテナンス情報など)
官公庁・公共機関
フォーマルな「ご案内」を重視(行政手続き、制度改正など)
まとめ
「お知らせ」と「ご案内」は、似ているようでその使い分けはビジネス文書の質を左右する重要なポイントです。
覚えておきたいポイント
- 「お知らせ」は決定事項の一方的な通知に適している
- 「ご案内」は相手の行動を促したり、詳細情報を提供したりする場合に適している
- 文書の目的や相手との関係性に応じて適切に使い分ける
- タイトルと本文の内容を一致させる
- 両方を併記するような冗長な表現は避ける
適切な使い分けを心がけることで、ビジネス文書の品質向上につながります。
状況や目的に応じて「お知らせ」と「ご案内」を使い分けましょう。
関連記事
- 「ご連絡」「お知らせ」の違いとは?正しい使い分けと例文【ビジネスメール必須知識】
- ビジネスメールで迷う「と思います/考えます/存じます」の正しい使い分け方
- 「お伝えします」「ご連絡します」の違いと使い分け【敬語レベル別例文30選】
よくある質問(FAQ)
Q1: 社内向けと社外向けで使い分けるべきですか?
A: 基本的に、社内向けは「お知らせ」を使うことが多く、社外向けは内容に応じて使い分けます。
社内連絡では簡潔さが重視されるため「お知らせ」が好まれ、社外向けには相手との関係性や内容の重要度に応じて選択します。
特に重要な取引先に対しては「ご案内」を使うことで丁寧さを表現できます。
Q2: メールの件名ではどちらを使うべきですか?
A: メール本文の内容と一致させることが最も重要です。
単純な情報提供であれば「○○のお知らせ」、行動や参加を促す内容であれば「○○のご案内」とするのが適切です。
また、件名は簡潔にして内容が一目でわかるようにしましょう。
例:「5/20(火) システムメンテナンスのお知らせ」「6/15(火) マーケティングセミナーのご案内」
Q3: 「お知らせとお願い」という表現は正しいですか?
A: 「お知らせとお願い」は、情報提供(お知らせ)と依頼事項(お願い)を含む場合に使用される正しい表現です。
例えば、「夏季休業のお知らせと緊急連絡先のご登録お願い」のように、通知と依頼を組み合わせた内容の場合に適しています。
ただし、「ご案内とお願い」という表現もあり、より丁寧に依頼事項を伝えたい場合に使用されます。
Q4: Webサイトの「お知らせ」セクションに掲載するイベント情報は「ご案内」にすべきですか?
A: Webサイトのセクション名としては、一般的に「お知らせ」が定着しており、その中にイベント情報などの「ご案内」を含めることが多いです。
各記事のタイトルとしては、イベント参加を促す内容であれば「○○セミナーのご案内」とするのが適切です。
セクション名と個別記事のタイトルを区別して考えるとよいでしょう。
Q5: 「お知らせ」と「ご案内」を使い分ける際の例外はありますか?
A: 業界慣習や社内ルールによって例外はあります。
例えば、金融機関では商品情報を「商品のご案内」と表現するのが一般的です。
また、社内マニュアルで特定の用語使用が規定されている場合はそれに従うべきです。
不確かな場合は、同業他社の表現や過去の社内文書を参考にするとよいでしょう。