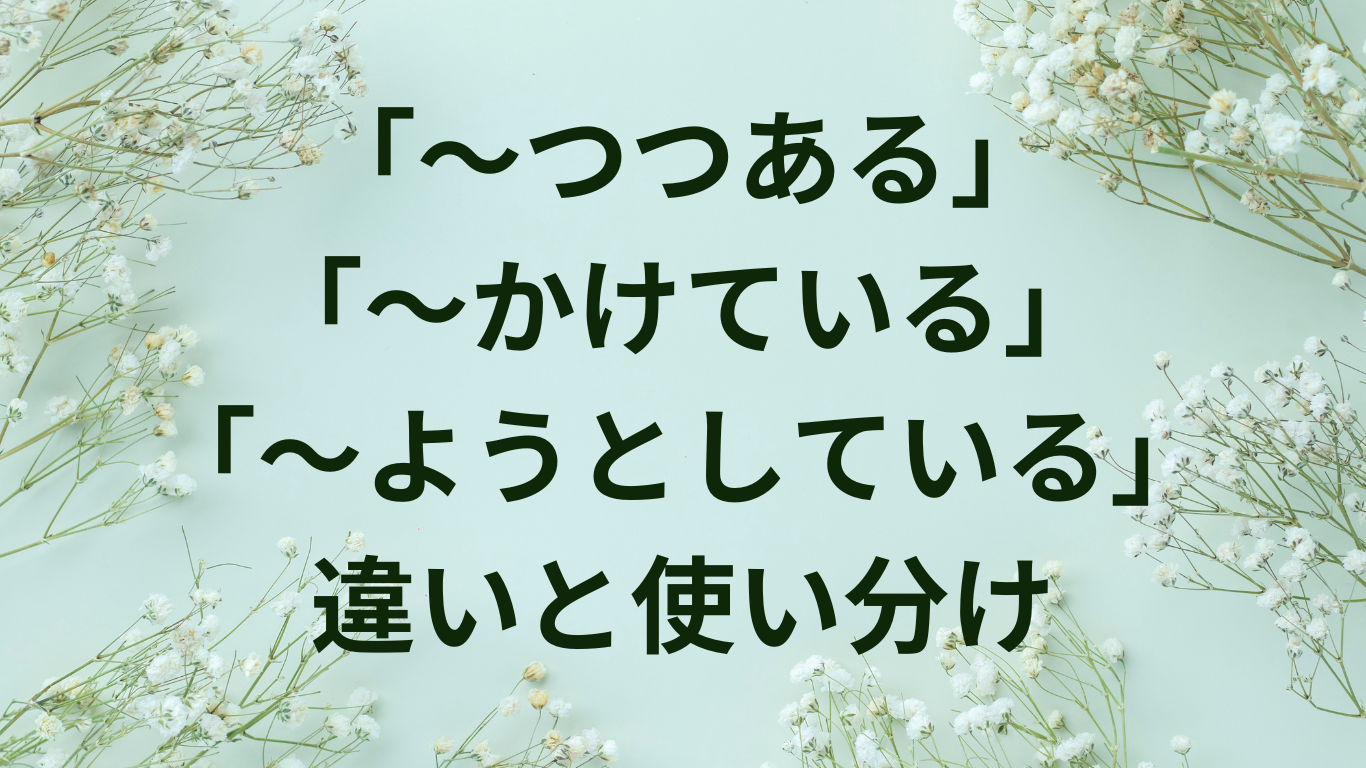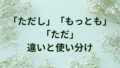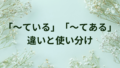日本語には変化の過程や動作の進行を表す表現として、「~つつある」「~かけている」「~ようとしている」という三つの表現があります。
これらは一見似ているように感じられますが、微妙な違いがあり、適切な場面で使い分けることが重要です。
この記事では、それぞれの表現の意味、ニュアンスの違い、適切な使い方について詳しく解説します。
正しく使い分けることで、あなたの日本語表現がより豊かで正確なものになるでしょう。
基本的な意味の違い
「~つつある」「~かけている」「~ようとしている」はいずれも変化の過程を表す表現ですが、それぞれが持つ基本的な意味には明確な違いがあります。
「~つつある」の基本的な意味
「~つつある」は、ある変化や動作が「徐々に進行している」ことを表します。
すでに変化や動作が始まっており、それが少しずつ進んでいる状態を示します。
特に、ゆっくりとした変化や、社会的な傾向などを表す際に使われることが多いです。
例えば、「経済は回復しつつある」という表現は、経済の回復がすでに始まっており、少しずつその傾向が続いていることを意味します。
「~かけている」の基本的な意味
「~かけている」は、ある動作や変化が「まさに始まろうとしている」または「始まったばかり」の状態を表します。
動作や変化の初期段階、特に変化の瞬間に焦点を当てた表現です。
例えるなら、電車が駅を出発しようとしている瞬間や、水が沸騰し始める瞬間のように、状態変化の境界線上にある状況を表現するのに適しています。
「~ようとしている」の基本的な意味
「~ようとしている」は、主体が「意図的に何かをしようとしている」状態を表します。
動作の直前の段階で、まだ実際の動作は始まっていないが、その準備や意図が明確にある状況を示します。
この表現は特に意志性が強く、主体の意図や目的を強調する表現です。
「彼は家を出ようとしている」という表現は、彼がこれから家を出る意図を持っていることを示しています。
三者の違いを簡潔に言えば、「~つつある」は徐々に進行中の変化、「~かけている」は変化の始まりの瞬間、「~ようとしている」は変化の直前の意図的な準備段階を表していると言えるでしょう。
使い分けのポイント
これらの表現を適切に使い分けるためには、状況や文脈に応じた選択が必要です。
ここでは、具体的なシーンごとの使い分けのポイントを解説します。
変化の段階による使い分け
| 表現 | 変化の段階 | 適切な状況 |
|---|---|---|
| ~つつある | 変化の進行中(中間段階) | 徐々に進行している社会的傾向や緩やかな変化 |
| ~かけている | 変化の開始段階(初期段階) | まさに始まる瞬間や開始直後の状態 |
| ~ようとしている | 変化の準備段階(直前) | 変化を起こす直前、まだ実際には始まっていない状態 |
意志性による使い分け
「~ようとしている」は強い意志性を持ち、主体が意図的に行動しようとしている状態を表します。
例えば、「彼は出発しようとしている」は、彼が自分の意志で出発する準備をしていることを意味します。
一方、「~つつある」は意志性が比較的弱く、自然な流れや社会的な傾向を表すことが多いです。
「物価は上昇しつつある」というように、主体の意図とは関係なく進行している変化に使われます。
「~かけている」は、意志的な行動にも非意志的な変化にも使うことができますが、特に変化が始まる瞬間を強調します。
フォーマル度による使い分け
| 表現 | フォーマル度 | 適する場面 |
|---|---|---|
| ~つつある | 高(やや硬い表現) | 論文、ニュース、ビジネス文書、公式発表 |
| ~かけている | 中(日常的な表現) | 日常会話、メール、ブログ、カジュアルな文章 |
| ~ようとしている | 中〜高 | 物語、説明文、報告書、日常会話 |
「~つつある」は特に報告書や論文などの硬い文章で使われることが多く、「景気は回復しつつある」のような経済レポートや社会動向の分析などでよく見られます。
時間的な幅による使い分け
「~つつある」は比較的長い時間をかけて進行する変化に使われることが多く、「~かけている」は瞬間的な変化、「~ようとしている」はこれから起こる短い時間の動作に使われる傾向があります。
- 「技術は日々進化しつつある」(長期的な変化)
- 「太陽が沈みかけている」(瞬間的な変化)
- 「彼は窓を開けようとしている」(これからの短い動作)
よくある間違い & 誤用例
これらの表現は微妙なニュアンスの違いがあるため、誤用が生じやすいです。
特によくある間違いと正しい使い方を確認しましょう。
非意志的な主語と「~ようとしている」の組み合わせ
🚫 「台風は日本に近づこうとしている」(誤用)
✅ 「台風は日本に近づきつつある」(正しい)
✅ 「台風は日本に近づいている」(正しい)
台風のような意志を持たない自然現象に「~ようとしている」を使うのは不自然です。
これは主体の意図を強調する表現であるため、意志を持たない対象には「~つつある」や単純な「~ている」を使うのが適切です。
瞬間的な変化と「~つつある」の組み合わせ
🚫 「彼は今まさに転んでつつある」(誤用)
✅ 「彼は今まさに転びかけている」(正しい)
「転ぶ」のような瞬間的な動作に「~つつある」を使うのは不自然です。
瞬間的な変化には「~かけている」を使うのが適切です。
フォーマルな文書での「~かけている」の過剰使用
🚫 「当社の業績は改善してかけています」(誤用、フォーマル度が合わない)
✅ 「当社の業績は改善しつつあります」(正しい)
ビジネス文書や報告書など、フォーマルな文脈では「~つつある」を使うのが一般的です。
「~かけている」はやや口語的な印象があります。
文化的背景・歴史的背景
これらの表現がどのように発展してきたのか、その文化的・歴史的背景を見ていきましょう。
「~つつある」は古くから使われている表現で、特に文語体の日本語において重要な役割を果たしてきました。
「つつ」という助詞は古典日本語にも見られる表現で、徐々に進行する様子を表す際に使われてきました。
現代でも新聞や報道で多用され、客観的な事実の進行を表す際に重宝されています。
「~かけている」は「かける」という動詞が持つ「始める」「着手する」という意味から派生した表現です。
江戸時代の文献にも見られるように、日常的な表現として長く使われてきました。
「~ようとしている」の「よう」は意志や意図を表す助動詞で、日本語の敬語表現などにも関連する重要な要素です。
主体の意図を強調する表現として、物語や説明文などで頻繁に使用されています。
現代日本語教育においては、これらの表現の違いは微妙なニュアンスを理解する上で重要なポイントとして教えられており、特に日本語学習者にとっては習得が難しい項目の一つとされています。
実践的な例文集
それぞれの表現を使った例文を、日常会話、ビジネス場面、文学的表現など様々な文脈で見ていきましょう。
日常会話での使用例
「~つつある」の例文:
- 「最近、彼の考え方は変わりつつあるね」
- 「この街は少しずつ発展しつつある」
- 「私の日本語能力は向上しつつあると感じています」
「~かけている」の例文:
- 「ごめん、今出かけているところなんだ」
- 「雨が降りかけているから傘を持って行ったほうがいいよ」
- 「ちょうどご飯を食べかけていたところだよ」
「~ようとしている」の例文:
- 「彼女は何か言おうとしているみたいだけど、言い出せないみたい」
- 「子どもが自転車に乗ろうとしている」
- 「私はちょうど寝ようとしていたところです」
ビジネスシーンでの使用例
「~つつある」の例文:
- 「市場は徐々に回復しつつあります」
- 「新しいビジネスモデルが定着しつつある」
- 「当社の新戦略は効果を発揮しつつあります」
「~かけている」の例文:
- 「会議が始まりかけているので、急いでください」
- 「プロジェクトが遅れかけているので対策が必要です」
- 「取引先から連絡がきかけたところです」
「~ようとしている」の例文:
- 「当社は新しい市場に参入しようとしています」
- 「彼は重要な提案をしようとしているところです」
- 「我々はビジネスモデルを変革しようとしています」
文学的表現・ニュースでの使用例
「~つつある」の例文:
- 「夕暮れの空は赤く染まりつつあった」
- 「社会の価値観は大きく変わりつつある」
- 「彼女の瞳には涙が浮かびつつあった」
「~かけている」の例文:
- 「太陽が山の端に沈みかけていた」
- 「彼は過去の記憶を思い出しかけていた」
- 「列車がプラットフォームを出かけていた」
「~ようとしている」の例文:
- 「彼はその謎を解こうとしていた」
- 「新しい時代が始まろうとしている」
- 「彼女は大きな決断をしようとしていた」
まとめ
「~つつある」「~かけている」「~ようとしている」は、いずれも変化の過程を表す表現ですが、それぞれが持つニュアンスや適した状況が異なります。
覚えておきたいポイント
- 「~つつある」:徐々に進行中の変化を表し、フォーマルな文脈で使われることが多い
- 「~かけている」:変化の開始段階や瞬間を表し、日常的な会話でよく使用される
- 「~ようとしている」:主体の意図的な行動を表し、まだ始まっていない変化の直前を示す
- 非意志的な主語(自然現象など)には「~ようとしている」を使わない
- 瞬間的な変化には「~つつある」よりも「~かけている」が自然
- フォーマルな文書では「~つつある」を優先的に使用する
これらの表現を適切に使い分けることで、あなたの日本語表現はより正確で豊かなものになるでしょう。
状況や文脈に応じて最適な表現を選ぶことが、効果的なコミュニケーションの鍵となります。
よくある質問(FAQ)
Q1: 「~つつある」と単純な「~ている」はどう違うのですか?
A: 「~つつある」は変化が進行中であることを強調し、特に徐々に進行している様子を表します。
一方、「~ている」はより一般的な進行形で、必ずしも変化の途中段階を強調するわけではありません。
例えば「変わりつつある」は変化の過程を強調し、「変わっている」は変化の結果や状態を表すことが多いです。
Q2: 「~かけている」と「~始めている」の違いは何ですか?
A: 「~かけている」は変化が始まる瞬間や初期段階を表し、瞬間的なイメージが強いです。
「~始めている」は動作や変化が確実に開始されたことを表し、より明確な開始を示します。
例えば「雨が降りかけている」は雨がまさに降り出そうとしている状態を、「雨が降り始めている」は既に雨が降り出したことを表します。
Q3: 意志のない自然現象を表す場合、どの表現が適切ですか?
A: 意志のない自然現象には「~ようとしている」は不自然です。
代わりに「~つつある」(徐々に進行中の場合)や「~かけている」(変化の瞬間を表す場合)、または単純に「~ている」を使います。
例えば「台風が近づきつつある」「日が沈みかけている」などが自然な表現です。
Q4: ビジネス文書では、どの表現を使うべきですか?
A: ビジネス文書や報告書などのフォーマルな文脈では、一般的に「~つつある」が最も適切です。
例えば「市場は拡大しつつある」「業績は改善しつつある」などの表現がよく使われます。
「~かけている」はやや口語的な印象があるため、正式な文書では避けられることがあります。