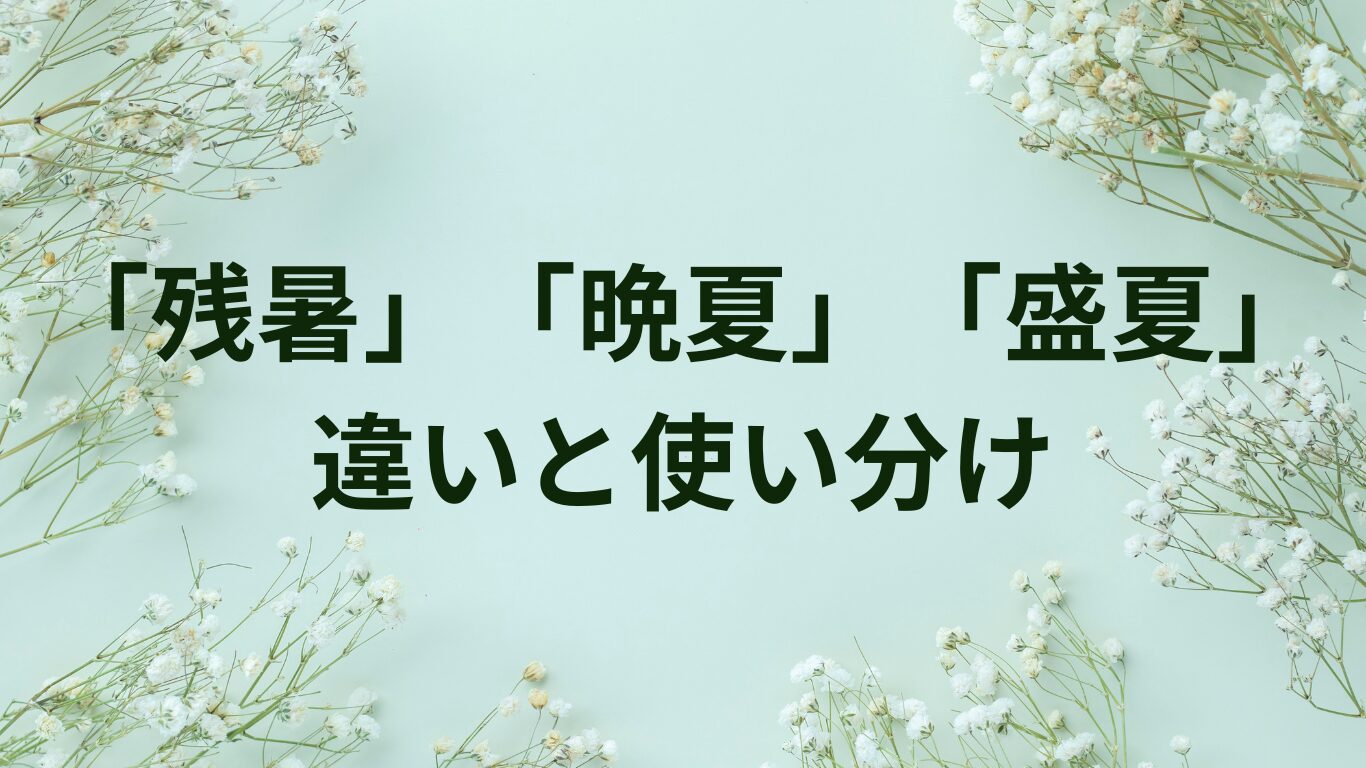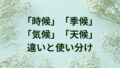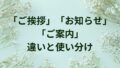【結論】3つの使い分けルール
- 残暑:立秋(8/7)~白露の前日までが原則(2025年は9/6まで)。ビジネス実務は8月末到着が無難。
- 晩夏:立秋直後~8/20ごろが目安(“夏の名残”を柔らかく伝える語)。
- 盛夏:7月上旬~8/6(立秋前日)。暑中見舞い・真夏の時候語。
※「9月上旬」は、異常高温や暑い地域宛などの条件下で、配慮表現+一文を添えると可(詳細は本文)。
本文は今年の基準日となっています
「二十四節気 × 用語」早見表
| 節気 | 2025年の日付 | 季節感 | 使える主な表現 | OK/NGの目安 |
|---|---|---|---|---|
| 小暑 | 7/7ごろ | 夏本番へ | 暑中/盛夏 | OK(暑中) |
| 大暑 | 7/22ごろ | 最も暑い頃 | 盛夏/大暑 | OK(盛夏) |
| 立秋 | 8/7 | 暦の上で秋の始まり | 残暑/晩夏/初秋 | 盛夏→残暑に切替 |
| 処暑 | 8/23ごろ | 暑さが和らぐ頃 | 残暑/初秋 | まだ残暑OK |
| 白露 | 9/7 | 秋の気配が濃くなる | 初秋/新秋/孟秋 | 前日(9/6)までが残暑の原則 |
実務では8月末までが安心ライン。9月上旬は異常高温時のみ、配慮表現を。
なぜ使い分けが重要なのか?
ビジネス文書や正式な手紙では、時期に応じた正確な時候の挨拶が相手への配慮を示す重要な要素です。
暑中見舞いでは「盛夏」、残暑見舞いでは「晩夏」「立秋」「葉月」を使い分けるのが一般的なマナーとされています。
間違った時期表現は相手に違和感を与え、ビジネス関係に悪影響を与える可能性があります。
「残暑」の正しい意味と使い方
基本的な意味
「残暑」とは立秋(8月7日頃)以後、9月初めごろまで残る暑さを指します。
暦の上で「立秋」(秋の始まり)を迎えても、暑さが残る時期という意味で使われます。
残暑の使用時期
- 開始:立秋(8月7日)から
- 終了(原則):白露の前日まで(2025年は9月6日)
実務目安:8月末までに到着が無難。9月上旬にかかる場合は、記録的猛暑への言及とお詫びの一文を添える。
表現例(遅れたとき):「記録的な暑さが続く中、時期が後ろ寄せとなりましたことをお許しください。」
期限だけ先に確認したいなら → ▶[まだ間に合う?残暑見舞いはいつまで|例外の判断基準つき]で解説しています
ビジネス文書での使用例
残暑見舞いでの使用
- 冒頭: 「残暑お見舞い申し上げます」
- 本文: 「秋とは名ばかりの暑さが続いておりますがいかがお過ごしですか」
- 日付: 「○年 晩夏」「立秋」「葉月」
メールでの使用例
件名: 残暑お見舞い申し上げます
暦の上では秋とはいえ、なお暑い日が続いておりますが、
皆さま、お元気でいらっしゃいますでしょうか。
30秒で使えるビジネス例文はこちらへ → ▶ [ビジネス(社外中心)残暑見舞いの文例25選【失礼のないビジネス対応】]
「晩夏」の正しい意味と使い方
基本的な意味
晩夏とは夏の終わりから秋の始まりにかけての時期を指します。
夏の終わり、夏の末という意味で、夏も終わりに近づき秋の足音すらも聞こえ始める時期を表現します。
使用時期
季語としての定義
- 7月7日頃~8月7日頃(二十四節気ベース)
実用的な使用時期
- 立秋(8月7日前後)の直後から8月20日前後まで
- お盆の時期(8月13日~15日)辺りから8月末まで
ビジネス文書での使用例
時候の挨拶として
- 「晩夏の候、○○様におかれましてはいっそうご活躍のこととお慶び申し上げます」
残暑見舞いとの組み合わせ
- 「残暑お見舞い申し上げます。晩夏の候、いかがお過ごしでしょうか?」
「盛夏」の正しい意味と使い方
基本的な意味
盛夏とは、夏のもっとも暑い時期のことです。
梅雨明け頃から立秋までの夏の一番暑い時期を表す季語として使われます。
使用時期
- 主に7月上旬から8月上旬までにかけて使われるのが一般的
- 8月中旬になると時候の挨拶としては「残暑の候」や「残炎の候」といった言葉が使われる
ビジネス文書での使用例
暑中見舞いでの使用
- 日付表記: 「○年盛夏」
- 時候の挨拶: 「盛夏の折、ますますご健勝のことと拝察いたします」
実践的な使い分けガイド
暑中見舞い・残暑見舞いでの使い分け
| 時期 | 挨拶状 | 使用する言葉 | 日付表記 |
|---|---|---|---|
| 7月7日頃~8月6日頃 | 暑中見舞い | 盛夏 | ○年盛夏 |
| 8月7日頃~8月末 | 残暑見舞い | 晩夏・立秋・葉月 | ○年晩夏 |
※原則は白露の前日まで。2025年は9/6まで。実務は8月末着が無難
ビジネスメールでの月別使い分け
7月
- 上旬~中旬: 「盛夏の候」
- 下旬: 「盛夏の候」または「大暑の候」
8月
- 上旬: 「盛夏の候」(立秋前まで)
- 中旬~下旬: 「晩夏の候」「残暑の候」
「言い換えリスト」
| 表現 | 季節区分 | フォーマル度 | ビジネス相性 | 親しい関係 | 使いどころ |
|---|---|---|---|---|---|
| 残暑 | 立秋〜白露前日 | 高 | ◎ | ○ | 迷ったらコレ(汎用) |
| 晩夏 | 夏の名残(実務は立秋直後〜8/20) | 中 | ○ | ◎ | 柔らかい余情 |
| 初秋 | 秋の初め | 高 | ◎ | ○ | 8月下旬〜9月に安全 |
| 新秋 | 秋の初め(雅語) | 高 | ○ | △ | 改まった手紙に |
| 孟秋 | 初秋(古風) | 高 | △ | △ | 相手の好みにより |
| 葉月 | 和風月名(八月) | 中 | ◎ | ◎ | 日付・署名で使う |
よくある間違いと正しい使い方
❌ 間違い例
- 7月に「晩夏の候」を使用
- 8月下旬に「盛夏」を使用
- 残暑見舞いで「梅雨が明けて」「蝉の声が賑やかに」といった暑中見舞いの文例を使用
✅ 正しい使い方
- 時期に応じた適切な表現の選択
- 残暑見舞いでは「秋のはじまりを意識した挨拶文」を使用
- 相手の地域の気候に配慮した表現
相手別・場面別の使い分け例文
取引先・目上の方へ
8月上旬(立秋前)
拝啓 盛夏の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。
連日厳しい暑さが続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。
8月中旬(残暑見舞い)
残暑お見舞い申し上げます
晩夏の候、皆様におかれましてはいっそうご活躍のこととお慶び申し上げます。
暦の上では秋とはいえ、なお暑い日が続いておりますが、
お変わりなくお過ごしでしょうか。
同僚・親しい関係の方へ
8月中旬
残暑お見舞い申し上げます
立秋とは名ばかりの暑さが続きますが、お元気でいらっしゃいますか。
夏の疲れが出る頃かと思いますが、どうぞご自愛ください。
友人・家族向けのカジュアル文例はこちらへ → ▶ [友人・知人への残暑見舞い15選【LINEでも使えるカジュアル文例】]
地域差と現代的な配慮
地域による気候差への対応
暑中見舞いの時期が地域によって異なるのは、お盆の日付が地域ごとに異なることや、新暦旧暦の違いなどが理由とされています。
相手の居住地域の気候に配慮した表現を選ぶことが重要です。
北海道・東北地方:早めに涼しくなるため、8月下旬の「残暑」表現は控えめに
九州・沖縄地方:9月でも暑さが続くため、「残暑」期間を長めに考慮
現代の気候変動への対応
近年は9月に入っても暑い日が続いているため、従来の基準よりも柔軟な対応が求められます。
ただし、残暑見舞いの正式な時期は、立秋(8月7日)から白露(9月8日)の前日までとされているため、基本的なマナーは守りつつ配慮することが大切です。
FAQ
Q1:9月上旬に「残暑」は失礼?
A. 原則は9/6まで。
ただし異常高温や暑い地域宛なら、配慮表現+お詫びの一文を添えれば許容されることがあります。
無難なのは「初秋」。
Q2:「晩夏」と「初秋」どっちが無難?
A. 8/中旬まで=晩夏、8/下旬〜9月=初秋が安全。迷ったら残暑/初秋に。
Q3:「葉月」はどこで使う?
A. 書き出しではなく、日付・署名に使うのが自然(例:令和七年 葉月)。
まとめ:正しい使い分けで印象アップ
残暑・晩夏・盛夏の使い分けの要点
- 時期の正確な把握: 立秋を境に「盛夏」から「残暑・晩夏」へ切り替え
- 相手への配慮: 居住地域の気候や関係性に応じた適切な表現選択
- 文書の種類: 暑中見舞い・残暑見舞い・ビジネスメールそれぞれに適した使い方
正しい時候の挨拶は、相手への敬意と教養を示す重要な要素です。
これらの使い分けをマスターして、より印象的なビジネスコミュニケーションを実現しましょう。
関連記事
- 暑中見舞いと残暑見舞いの書き方完全ガイド
- ビジネスメールの時候の挨拶一覧
- 季節の挨拶で差をつける大人のマナー