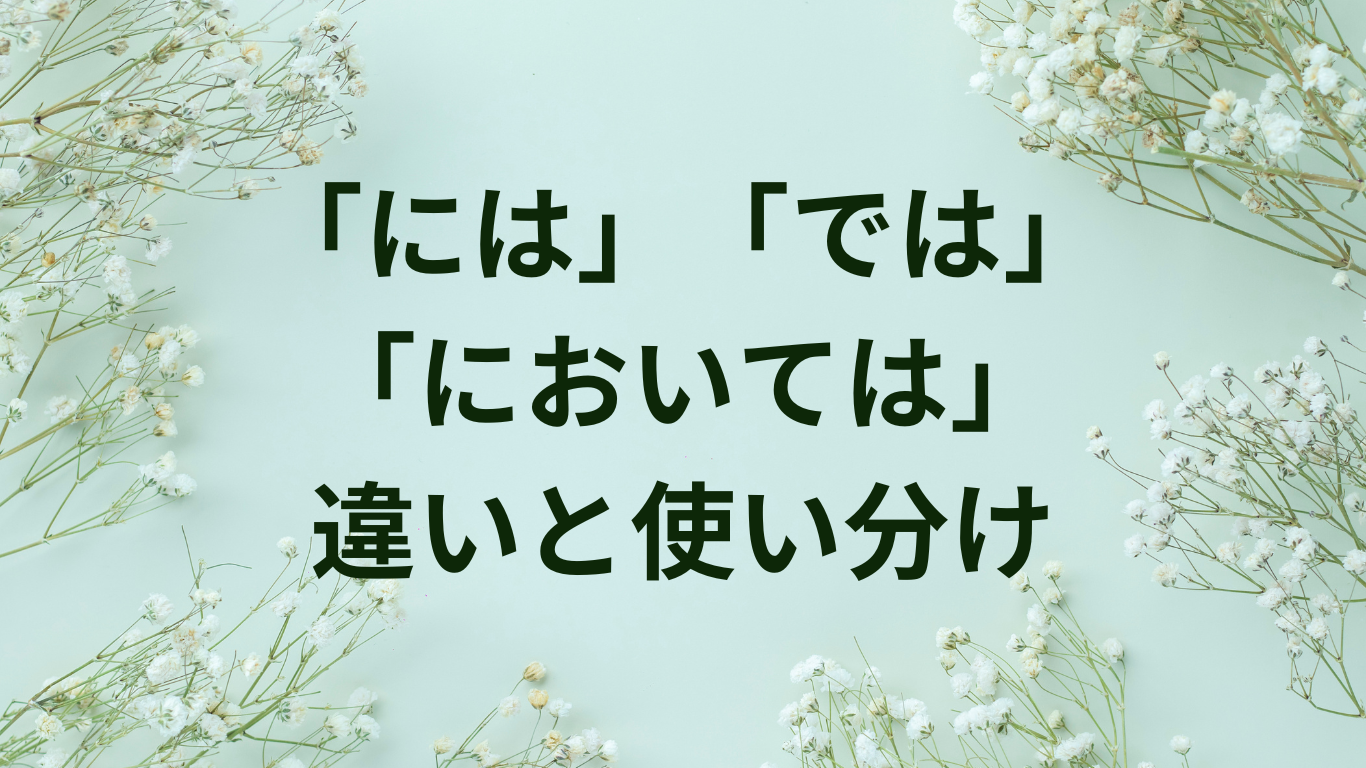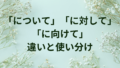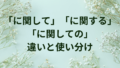学術論文やレポートでよく使われる「には」「では」「においては」
一見似たような表現ですが、それぞれに微妙なニュアンスの違いがあり、適切に使い分けることで文章の正確さと説得力が大きく向上します。
本記事では、これらの表現の違いを詳しく解説し、論文やレポートで効果的に使い分けるためのポイントを紹介します。
日本語の学術文章をより洗練されたものにしたい方は、ぜひ最後までお読みください。
「において」の意味や基本的な使い方については、
👉 『においてとは?意味と使い方』 をご覧ください。
基本的な意味の違い
「には」「では」「においては」は、いずれも場所や状況を示す助詞ですが、その使い方には明確な違いがあります。
「には」は「に」と「は」の複合助詞で、「に」が示す場所・対象・時間などに「は」の主題提示の機能が加わったものです。
比較的シンプルな表現で、対象を限定して話題にする際に使われます。
「では」は「で」と「は」の複合助詞で、「で」が示す場所・手段・状態などに「は」の主題提示の機能が加わったものです。
特定の状況や条件下での話題を提示する際に使われます。
「においては」は「に」「おいて」「は」の複合表現で、最も形式的かつ硬い印象を与えます。
学術論文や公式文書でよく使用され、議論の場や枠組みを明確に設定する際に用いられます。
これらの違いは、たとえるなら以下のようになります:
- 「には」:地図上の特定の地点を指し示す(焦点が明確)
- 「では」:特定の地域内の状況を説明する(範囲内の状態)
- 「においては」:公式な会議の場で厳格に定められた議題を扱う(形式的な枠組み)
使い分けのポイント
これらの表現は、文章のスタイルや伝えたいニュアンスによって使い分けることが重要です。
以下に状況別の使い分けポイントをまとめます。
学術論文・専門文書での使い分け
| 表現 | 使用場面 | 効果 | 例文 |
|---|---|---|---|
| には | 研究対象を限定する場合 | 対象を明確に | この研究には新たな方法論を採用した |
| では | 特定分野内の状況説明 | 範囲内の状態を説明 | 心理学ではこの現象を〇〇と呼ぶ |
| においては | 公式な議論の枠組み設定 | 最も格式高く厳密 | 本論文においては以下の3点に焦点を当てる |
論理展開・比較での使い分け
| 表現 | 使用場面 | 効果 |
|---|---|---|
| には | 対比の前提となる要素 | 対象を際立たせる |
| では | 条件付きの状況説明 | 状況の特殊性を示す |
| においては | 厳密な議論の範囲設定 | 議論の枠組みを明確化 |
フォーマル度による使い分け
- カジュアル〜フォーマルの順:「には」→「では」→「においては」
- 「においては」:最も形式的で、公式文書、学術論文に適する
- 「では」:一般的な論説文、解説文に適する
- 「には」:比較的柔らかい印象で、幅広い文章に使える
よくある間違い & 誤用例
これらの表現の誤用は、文章の論理性や説得力を損なう恐れがあります。
よくある間違いと正しい使い方を見てみましょう。
🚫 「この実験においては、温度計を使用した」(大げさすぎる)
✅ 「この実験では、温度計を使用した」(適切な硬さ)
🚫 「日常会話においては敬語を使うべきだ」(不自然に硬い)
✅ 「日常会話では敬語を使うべきだ」(自然な表現)
🚫 「東京では多くの人が住んでいる」(「に」が適切)
✅ 「東京には多くの人が住んでいる」(存在を示すので「に」が正しい)
🚫 「この問題を解決するでは時間がかかる」(文法的に不正確)
✅ 「この問題を解決するには時間がかかる」(目的を示す「に」が適切)
特に注意すべきは、形式的な硬さを出そうとして「においては」を多用する傾向です。
必要以上に硬い表現を使うと、かえって文章が不自然になりますので、文脈に応じた適切な選択が重要です。
文化的背景・歴史的背景
これらの表現の違いは、日本語の助詞の発達と文章の格式化の歴史に関連しています。
「には」「では」は古くから日常語として使われてきましたが、「においては」は漢文訓読の影響を受けた改まった表現として発達しました。
江戸時代以降、公文書や学術的な文章では漢文調の硬い表現が好まれ、明治以降の近代化の中で西洋の学術文体の影響も受けて、「においては」のような形式的表現が定着しました。
特に学術論文では、客観性や論理性を重視する文化から、主観を排した硬い表現が重宝されてきました。
現代でも、「においては」の使用頻度は論文や法律文書で高く、文章の格式の高さを示す指標のひとつとなっています。
実践的な例文集
学術論文・レポートでの使用例
「には」の例:
- 効果的な論文作成には十分な先行研究のレビューが不可欠である。
- この実験結果を分析するには統計的手法を用いる必要がある。
- 持続可能な開発には環境負荷の軽減が求められる。
「では」の例:
- 先行研究では同様の結果が報告されていない。
- 本章では研究方法について詳述する。
- 質的研究では対象者の主観的体験を重視する。
「においては」の例:
- 本研究においては、三つの観点から分析を行った。
- 現代社会においては、デジタル技術の役割が増大している。
- 学術的議論においては、客観的証拠に基づく論証が求められる。
言い換え表現例
「においては」→「では」→「には」と格式を下げる例:
- 本稿においては以下の点について論じる → 本稿では以下の点について論じる → 本稿には以下の点について書いた
「には」→「では」→「においては」と格式を上げる例:
- この調査には新しい手法を使った → この調査では新しい手法を使った → この調査においては新しい手法を採用した
まとめ
「には」「では」「においては」は、いずれも場所や状況を示す表現ですが、ニュアンスと格式に違いがあります。
適切な使い分けが、論文やレポートの質を高める重要な要素となります。
覚えておきたいポイント
- 「には」:対象を限定・強調する際に使用(比較的柔らかい)
- 「では」:特定の状況や条件下での説明に使用(中程度の硬さ)
- 「においては」:公式な議論の枠組み設定に使用(最も形式的で硬い)
- 必要以上に硬い表現を使わず、文脈に応じた適切な選択を心がける
- 論文・レポートでは「においては」の使用頻度を意識的に調整する
よくある質問(FAQ)
Q1: 「においては」を多用すると文章が良くなりますか?
A: 必ずしもそうではありません。
「においては」は最も形式的で硬い表現であり、多用すると不自然な印象を与えます。
論文の序論や重要な論点の提示など、格式を高めたい部分に限定して使用するのが効果的です。
Q2: 「では」と「においては」はいつでも置き換え可能ですか?
A: 文法的には置き換え可能な場合が多いですが、文の格式感やリズムが変わります。
特に「においては」は公式性が高いため、日常的な話題や簡潔さを求める文脈では「では」の方が自然です。
Q3: 存在を表す場合は「には」と「では」のどちらが適切ですか?
A: 存在を表す場合は基本的に「には」が適切です。
「東京には多くの観光地がある」のように使います。
「では」は状態や状況を説明する際に用いられます。
Q4: 論文の各セクションのはじめでは、どの表現が適切ですか?
A: 論文の主要セクション(序論、方法、結果など)の冒頭では「本章では」や「この節では」が一般的です。
特に重要な理論的枠組みの提示などでは「本研究においては」のように「においては」を使うこともあります。