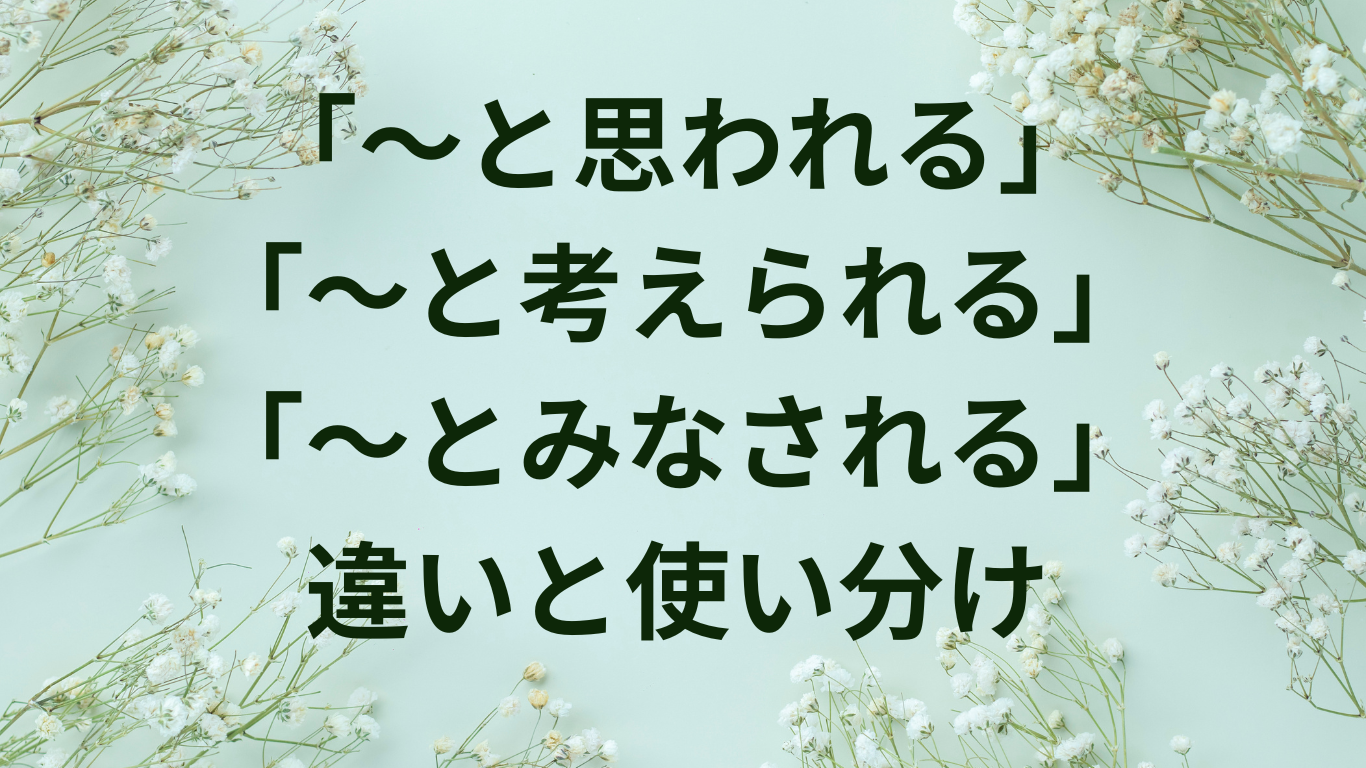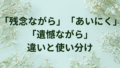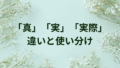日本語には「〜と思われる」「〜と考えられる」「〜とみなされる」という、似たような客観的判断を表す表現があります。
これらは微妙なニュアンスの違いがあり、ビジネス文書や論文、日常会話など様々な場面で適切に使い分けることが重要です。
本記事では、これらの表現の違いと使い分けについて詳しく解説します。
正しく理解して使うことで、より洗練された日本語表現が可能になるでしょう。
基本的な意味の違い
「〜と思われる」「〜と考えられる」「〜とみなされる」はいずれも客観的な判断を表す表現ですが、その確信度や根拠の性質に違いがあります。
「〜と思われる」の意味
「〜と思われる」は、 比較的軽い印象や主観的な判断を示します。
直感的な印象や個人的な見解に基づくことが多く、確信度は三つの中で最も低いといえます。
「見た目から判断して〜のようだ」というニュアンスを含みます。
「〜と考えられる」の意味
「〜と考えられる」は、 論理的な思考や分析に基づく判断を示します。
「〜と思われる」より客観性が高く、ある程度の根拠や理由に基づいた推論であることを示唆します。
学術論文やビジネス文書でよく使われる表現です。
「〜とみなされる」の意味
「〜とみなされる」は、社会的な評価や一般的な認識を示す表現です。
個人の判断というより、集団や社会による評価や判定を表します。
法律や規定に基づく判断、あるいは社会通念上の扱いを表すことが多く、公式な文脈で使われます。
たとえるなら、「〜と思われる」は「窓の外の空を見て、明日は雨になりそうだ」という個人的な予測、「〜と考えられる」は「気圧配置と湿度から分析すると、明日は雨になる可能性が高い」という分析的判断、「〜とみなされる」は「気象庁の発表により、明日は雨天と認定された」という公式な判断のような違いがあります。
使い分けのポイント
状況や文脈によって、これらの表現は使い分けるべきです。
以下に具体的なシーン別の使い分けを紹介します。
フォーマルな場面(論文・報告書など)
「〜と思われる」
- 控えめな推測を述べる場合に使用
- 確固たる証拠がなく、著者の印象を述べる場合
- 例:「この現象は一時的なものと思われる」
「〜と考えられる」
- データや分析に基づく論理的な推論
- 学術的な考察や仮説を述べる場合
- 例:「実験結果から、AとBには因果関係があると考えられる」
「〜とみなされる」
- 既存の基準や規定に基づく評価
- 一般的に認められた解釈を述べる場合
- 例:「国際法上、この行為は違法行為とみなされる」
ビジネスシーン
「〜と思われる」
- 個人的な見解を控えめに伝える場合
- 確証はないが、経験からの予測を述べる場合
- 例:「納期は来週末になると思われます」
「〜と考えられる」
- 市場分析や調査結果に基づく判断
- 客観的な根拠のある推論を示す場合
- 例:「市場データから、今後需要が拡大すると考えられます」
「〜とみなされる」
- 会社の規定や業界基準に基づく評価
- 公式な立場からの判断を示す場合
- 例:「この契約書では、30日以上の遅延は重大な違反とみなされます」
日常会話・カジュアルな文脈
「〜と思われる」
- 日常的な推測や印象を述べる場合(ただし少し硬い印象)
- 例:「彼は疲れているようで、早く帰りたいと思われる」
「〜と考えられる」
- 日常会話では少し堅苦しく、あまり使用されない
- 例:「この道具の使い方は簡単ではないと考えられる」
「〜とみなされる」
- 日常会話ではさらに硬い印象を与え、ほとんど使用されない
- 友人間では「〜とみなされている」というより「〜と言われている」などの表現が自然
- 例:「地域の風習では、この行為は失礼とみなされる」
よくある間違い & 誤用例
これらの表現の誤用や不適切な使用例を見てみましょう。
確信度と表現の不一致
🚫 「明確な証拠があるため、犯人は彼と思われる」
✅ 「明確な証拠があるため、犯人は彼と考えられる」
(強い証拠がある場合は「考えられる」がより適切)
個人的判断と社会的認識の混同
🚫 「私の個人的な意見では、この行為は違法とみなされる」
✅ 「私の個人的な意見では、この行為は違法と思われる」
(個人的意見には「みなされる」は不適切)
フォーマル度の不一致
🚫 「やあ、今日は雨になるみたいだから傘が必要と考えられるよ」
✅ 「やあ、今日は雨になるみたいだから傘が必要だよ」
(日常会話では「考えられる」は不自然に堅い)
主語と表現の不一致
🚫 「私はこの計画が成功すると思われる」
✅ 「私はこの計画が成功すると思う」または「この計画は成功すると思われる」
(自分の思考を表す場合は「思う」を使用)
文化的背景・歴史的背景
これらの表現の違いは、日本語の「婉曲表現」と「間接表現」の伝統に根差しています。
日本文化では直接的な断定を避け、控えめに表現することが礼儀正しいとされてきました。
「〜と思われる」は「思う」という主観的動詞の受身形で、江戸時代の文献にもその用例が見られます。
個人の判断を控えめに表す伝統的な表現です。
「〜と考えられる」は明治時代以降、西洋の論理的思考法や学術文化の影響を受けて広まった表現です。
特に科学論文や学術的な文脈で重視されるようになりました。
「〜とみなされる」は法律用語としての歴史が長く、明治以降の近代法制度の整備とともに公的文書で多用されるようになりました。
「みなす」という行政・法律的判断を表す言葉の受身形です。
これらの表現の使い分けは、日本語特有の「立場」や「視点」の繊細な区別に基づいており、適切に使い分けることで、話者の教養や言語感覚が表れるといえます。
実践的な例文集
日常会話での使用例
- 「あの雲の様子から、もうすぐ雨が降ると思われる」(個人的な印象)
- 「彼の話し方から、東北地方の出身と思われる」(見た目からの推測)
- 「あの煙の量から、火事はかなり大きいと考えられる」(状況証拠からの推論)
- 「この地域では、お祝いに訪問する際は手土産を持参するものとみなされている」(社会的慣習)
ビジネス文書での使用例
- 「ご返信がないため、ご検討中と思われますが、何かご不明点があればお知らせください」(控えめな推測)
- 「市場調査の結果から、今後5年間で需要が30%増加すると考えられます」(データに基づく予測)
- 「当社規定により、3回連続の遅刻は重大な懲戒事由とみなされます」(規定に基づく判断)
学術論文での使用例
- 「被験者の反応から、この刺激はストレス要因となっていると思われる」(観察に基づく印象)
- 「これらのデータから、AとBの間には強い相関関係があると考えられる」(分析に基づく推論)
- 「国際基準によれば、500ppm以上の濃度は危険レベルとみなされる」(基準に基づく評価)
言い換え表現
- 「〜と思われる」→「〜と見受けられる」「〜のように見える」「〜と推察される」
- 「〜と考えられる」→「〜と推定される」「〜と判断される」「〜という結論に達する」
- 「〜とみなされる」→「〜と認識される」「〜と解釈される」「〜と定義される」
まとめ
「〜と思われる」「〜と考えられる」「〜とみなされる」は、客観的判断を表す表現ですが、それぞれに異なる特徴とニュアンスがあります。
覚えておきたいポイント
- 「〜と思われる」は主観的な印象や見た目からの推測を表す
- 「〜と考えられる」は論理的分析や根拠に基づく判断を表す
- 「〜とみなされる」は社会的評価や公的基準に基づく認識を表す
- 文脈やフォーマル度に応じて適切に使い分けることが重要
- 自分自身の判断を述べる場合は「思う」「考える」を使い、受身形は避ける
適切な表現を選ぶことで、文章の信頼性や正確さが大きく向上します。
特に公式文書やビジネス文書では、これらの違いを理解して使い分けることが、プロフェッショナルな印象を与える鍵となるでしょう。
よくある質問(FAQ)
Q1: 「〜と思われる」と「〜と思います」の違いは何ですか?
A: 「〜と思われる」は客観的な立場からの推測を表し、「〜と思います」は話者自身の主観的な考えを表します。
「私はこの案が最適と思います」(自分の意見)と「この案が最適と思われます」(一般的な見解)では、主体が異なります。
Q2: 学術論文では「〜と思われる」と「〜と考えられる」のどちらを使うべきですか?
A: 学術論文では「〜と考えられる」の方が一般的です。
「考えられる」はデータや分析に基づく論理的な推論を示唆するため、科学的な文脈により適しています。
「思われる」は印象や感覚的な判断のニュアンスがあります。
Q3: 「〜とされる」と「〜とみなされる」の違いは何ですか?
A: 「〜とされる」は一般的な認識や定説を示し、「〜とみなされる」は明確な基準や規定に基づく公式な判定や評価を示します。
例えば、「この建物は国宝とされる」(一般的認識)と「この建物は法律上国宝とみなされる」(法的評価)です。
Q4: ビジネスメールで丁寧に推測を伝えるにはどの表現が適切ですか?
A: 状況に応じて使い分けるとよいでしょう。
個人的な印象は「〜と思われます」、根拠のある推測は「〜と考えられます」、会社の規定などに基づく判断は「〜とみなされます」が適切です。
いずれも「〜かと存じます」という丁寧な表現に言い換えることも可能です。