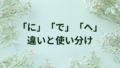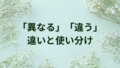書類や文書を作成する際、「をもって」「により」「によって」といった表現に迷うことはありませんか?
これらは日本語の公式文書やビジネス文書でよく使われる表現ですが、微妙なニュアンスの違いがあり、適切に使い分けることで文書の品質が大きく向上します。
本記事では、これらの表現の違いと適切な使い分け方を詳しく解説します。
結論から言うと、「をもって」は終了・完了・区切りを示す場合に、「により」はより形式的な原因・手段を示す場合に、「によって」は幅広い状況で使える汎用的な表現として使い分けるのがポイントです。
基本的な意味の違い
「をもって」「により」「によって」は、いずれも何かの手段や原因、根拠を示す表現ですが、それぞれ異なるニュアンスと使用場面があります。
「をもって」の基本的な意味
「をもって」は主に以下の意味で使われます
- 区切りや期限を示す(時間的な区切り)
- 手段や方法を表す
- 根拠や基準を示す
「をもって」は特に公式文書や法律文書で多用され、明確な区切りや完了を示す場合に適しています。
たとえば「本日をもって退職いたします」という表現は、退職という行為が本日という時点で明確に区切られることを示しています。
「により」の基本的な意味
「により」は次のような意味で使われます
- 原因や理由を表す
- 手段や方法を示す
- 根拠を示す
「により」は「をもって」よりもさらに形式的で硬い印象を与え、公文書や契約書などで多用されます。
たとえるなら、「により」は法律文書の中で細かい条項を整然と並べるような、秩序だった印象を持ちます。
「によって」の基本的な意味
「によって」の基本的な意味は以下の通りです
- 原因や理由を表す
- 手段や方法を示す
- 行為者を示す(受動態と一緒に使用)
「によって」は上記の表現の中で最も汎用性が高く、フォーマルな文書からカジュアルな文脈まで幅広く使えます。
水が様々な容器の形に合わせるように、「によって」は多様な文脈に対応できる柔軟性を持っています。
使い分けのポイント
状況や文脈に応じた適切な使い分けを理解することで、より精確で洗練された文書が作成できます。
フォーマル度による使い分け
| 表現 | フォーマル度 | 適した場面 |
|---|---|---|
| をもって | 非常に高い | 法律文書、公文書、辞令 |
| により | 高い | 契約書、報告書、学術論文 |
| によって | 中~高 | ビジネス文書、説明文、一般文書 |
時間的要素の有無による使い分け
「をもって」は特に時間的な区切りを示す場合に使われます。
「本日をもって」「年度末をもって」のように、明確な時点や期間の区切りを表現する場合に適しています。
一方、「により」「によって」は時間的要素よりも原因や手段に焦点を当てています。
文章の流れによる使い分け
文章の構造や流れによっても使い分けが変わります
- 「をもって」の使用例:
- 区切りを強調する場合:「今回の決議をもって、この問題は終了とします」
- 手段を具体的に示す場合:「書面をもって通知する」
- 「により」の使用例:
- 法的な根拠を示す場合:「法律第10条により、次の措置を講じる」
- 客観的な原因を示す場合:「天候不良により中止となりました」
- 「によって」の使用例:
- 一般的な原因説明:「気温の変化によって、植物の成長速度が変わる」
- 行為者を示す場合:「専門家によって検証された情報」
よくある間違い & 誤用例
これらの表現の誤用は文書の質を下げるだけでなく、意図が正確に伝わらない原因にもなります。
「をもって」の誤用
🚫 「台風をもって、イベントは中止になりました」
✅ 「台風により、イベントは中止になりました」
理由:「をもって」は原因を示す場合よりも、区切りや期限を示す場合に適しています。
上記の例では原因を示しているため「により」または「によって」が適切です。
「により」の誤用
🚫 「明日により、新しい規則が適用されます」
✅ 「明日をもって、新しい規則が適用されます」
理由:時間的な区切りを示す場合は「をもって」が適切です。
「により」は時間よりも原因や手段を示します。
「によって」の誤用
🚫 「本契約書によって締結する」(非常に形式的な文書の場合)
✅ 「本契約書をもって締結する」または「本契約書により締結する」
理由:極めて形式的な契約書などでは、「によって」よりも「をもって」または「により」のほうが適切です。
文化的背景・歴史的背景
これらの表現の使い分けには、日本語の公用文や公文書の歴史が関わっています。
「をもって」の歴史
「をもって」は古くから公文書や法令文で使われてきた表現で、漢文調の文体から影響を受けています。
特に明治時代以降の公文書において、西洋の法律文書の翻訳過程で定着した表現でもあります。
「により」「によって」の発展
「により」は近代以降の公文書で多用されるようになった表現で、より簡潔で分かりやすい文体への移行を示しています。
「によって」はさらに口語的で、戦後の公用文の民主化の流れの中で一般化しました。
これらの表現は、日本の文書作成の歴史と共に発展してきた言葉であり、その使い分けを理解することは、日本語の公文書の伝統を尊重することにもつながります。
実践的な例文集
様々な状況でのこれらの表現の使い方を具体的に見ていきましょう。
ビジネス文書での使用例
辞令・通達:
- 「本日をもって、山田太郎を営業部長に任命する」
- 「4月1日をもって、新規定が施行される」
報告書:
- 「市場調査により、新商品のニーズが確認された」
- 「専門家チームによって、製品の安全性が検証された」
契約書:
- 「本契約書をもって、両者の合意を証するものとする」
- 「第3条の規定により、支払いは月末に行われるものとする」
公文書での使用例
法令・条例:
- 「この法律は、公布の日から起算して3ヶ月を経過した日をもって施行する」
- 「市長により指定された区域は、特別保全地区とする」
通知・案内:
- 「令和5年度末をもって、当制度は廃止となります」
- 「法改正によって、申請手続きが簡素化されます」
学術文書での使用例
論文・研究報告:
- 「統計分析により、有意な相関関係が認められた」
- 「この実験によって、従来の理論の妥当性が確認された」
日常的な書類での使用例
願書・申請書:
- 「本状をもって、休暇を申請いたします」
- 「健康上の理由により、退職を希望いたします」
まとめ
「をもって」「により」「によって」の適切な使い分けは、文書の品質と伝わりやすさを大きく左右します。
覚えておきたいポイント:
- 「をもって」は区切りや期限、完了を示す場合に最適
- 「により」は形式的な文書で原因や手段を示す場合に使用
- 「によって」は幅広い状況で使える汎用的な表現
- 文書の種類やフォーマル度に応じて適切に使い分ける
- 時間的要素があるか、原因・手段を示すかで使い分ける
これらの表現を正確に使い分けることで、より洗練された文書作成が可能になります。
特に公式文書やビジネス文書では、適切な表現の選択が専門性と信頼性を高める重要な要素となります。
よくある質問(FAQ)
Q1: 「をもって」と「をもちまして」の違いは何ですか?
A: 「をもちまして」は「をもって」の丁寧な表現です。特に改まった場面や、より敬意を示したい場合に「をもちまして」を使用します。
例えば「本日をもちまして閉店させていただきます」のように使います。
Q2: 「による」と「により」はどう違いますか?
A: 「による」は連体修飾語(名詞を修飾する)として使われ、「により」は連用修飾語(動詞や文全体を修飾する)として使われます。
例えば「専門家による調査」(連体)と「専門家により調査された」(連用)のように使い分けます。
Q3: メールでも「をもって」は使えますか?
A: ビジネスメールでは使用可能ですが、やや硬い印象を与えます。
特に正式な通知や期限を明確にする場合には適していますが、日常的なコミュニケーションでは「によって」の方が自然な場合が多いでしょう。
Q4: 「をもって」を使わずに同じ意味を表現するには?
A: 「をもって終了」は「で終了」、「をもって開始」は「から開始」のように言い換えることができます。
例えば「本日をもって終了」→「本日で終了」、「4月1日をもって開始」→「4月1日から開始」などです。