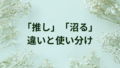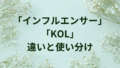SNSやインターネット上で頻繁に目にする「メンブレ」「エゴサ」「壮大フラグ」といった言葉。
実はこれらの表現、正確な意味を理解していないと、コミュニケーションに齟齬が生じることもあります。
特にビジネスでSNSを活用する場合や、若い世代と会話する際に、これらの言葉の意味や使い方を知っておくことは大切です。
本記事では、最新のSNS用語20選を厳選し、その意味や使い方、由来まで詳しく解説します。
この記事を読めば、最新のSNS用語をマスターし、オンラインコミュニケーションをより円滑に進められるようになるでしょう。
この記事でわかること
- 「メンブレ」「エゴサ」「壮大フラグ」など最新SNS用語20選の意味と使い方
- それぞれの用語の由来や文化的背景
- ビジネスシーンでの言い換え表現
- 年代別の理解度と使用頻度
- 実践的な例文と応用例
コミュニケーション系SNS用語
日常のコミュニケーションをより効率的に、あるいは微妙なニュアンスを伝えるために使われるSNS用語をご紹介します。
メンブレ
意味
「メンタルが崩れる」の略。
精神的に不安定になったり、落ち込んだりする状態を表します。
由来
「メンタルブレイク」という言葉が短縮されて「メンブレ」となりました。
使用例
- 「試験前でメンブレ気味…」
- 「推しの卒業発表でメンブレした」
- 「締め切り近くてメンブレ寸前」
類義語
メンヘラ、メンタル弱る、心が折れる
メンブレは一時的な精神状態の不安定さを表すことが多く、「メンヘラ」(メンタルヘルスに問題を抱える人)とは区別されます。
一過性の落ち込みや不安を表現するのに使われることが多いです。
エゴサ
意味
「エゴサーチ」の略。自分の名前やハンドルネーム、関連キーワードをインターネットで検索すること。
由来
「ego search(自分を検索する)」という英語からきています。
使用例
- 「ついエゴサしてしまって、悪口見つけてショックだった」
- 「エゴサ厳禁!気にしすぎると精神衛生上よくない」
- 「企業アカウントは定期的にエゴサして評判チェックするべき」
類義語
自分検索、セルフ検索
エゴサは個人でも企業でも行われますが、SNS上では特に自分に関する評判や言及を確認するために行われることが多いです。
ポジティブな言及を見つけると嬉しくなる一方、ネガティブな内容を見つけるとメンタルに影響することもあるため、「エゴサ禁止」と自戒する人も少なくありません。
既読スルー
意味
メッセージを読んだ(既読になった)にも関わらず、返信をしないこと。
由来
「既読」と「スルー(無視する)」を組み合わせた言葉です。
使用例
- 「昨日の連絡、既読スルーされてショック…」
- 「忙しくて返信できないから、既読スルーしてごめん」
- 「既読スルーは相手を不安にさせるからやめよう」
類義語
既読無視、既読放置
LINEやFacebookメッセンジャーなど、メッセージの既読機能がついたアプリの普及により生まれた言葉です。
意図的な無視と単なる返信忘れの区別がつかないため、人間関係のトラブルになることもあります。
リプ欄
意味
SNS(特にTwitter)での返信(リプライ)が表示される場所。
由来
「リプライ(reply)」と「欄」を組み合わせた言葉です。
使用例
- 「彼の投稿のリプ欄が荒れている」
- 「リプ欄見ると意見が二分してるね」
- 「リプ欄に書くより、DMした方がいいよ」
類義語
コメント欄、返信欄
主にTwitterで使われる表現ですが、他のSNSでも「コメント欄」などと言い換えて使われることがあります。
リプ欄は時に議論や炎上の場になることもあります。
壮大フラグ
意味
後に重大な展開につながりそうな発言や状況のこと。
特に「これから素晴らしいことが起こる」と思わせておいて、実際には逆の結果になることを予感させる発言。
由来
アニメやゲームで、キャラクターの「これからの展望」などの発言が、実は不吉な結末の前触れ(フラグ)になっていることから。
使用例
- 「『明日から本気出す』って言うのは壮大フラグ」
- 「卒業前に『将来は絶対に連絡を取り合おう』は壮大フラグ」
- 「『この作戦は絶対に成功する』という発言、壮大フラグ立ててる」
類義語
デスフラグ、失敗フラグ
元々はアニメやゲームのキャラクターが「これから〜する」と言った直後に、予想外の展開(多くは死や失敗)が訪れることを「フラグが立つ」と表現していました。
現実の生活でも、大きな希望を語った後に失敗することを自虐的に表現するために使われます。
感情表現系SNS用語
感情や気持ちを表現するために使われる、新しいSNS用語を紹介します。
マヨる
意味
迷う、躊躇する、判断に困る状態を表します。
由来
「迷う」の「まよう」から派生した言葉。
使用例
- 「どっちの服を買うか、マヨってる」
- 「告白しようかマヨってる…」
- 「今日の予定、雨だからマヨるなぁ」
類義語
迷う、悩む、決めかねる
「マヨる」は若者を中心に広まった表現で、特に日常的な選択や決断の場面で使われることが多いです。
「マヨネーズ」とは関係なく、純粋に「迷う」の言い換えとして使われます。
詰む
意味
行き詰まる、打つ手がなくなる、どうしようもなくなる状態。
由来
チェスや将棋などのボードゲームで、どう動いても負けが確定する「詰み」の状態から。
使用例
- 「財布忘れた…完全に詰んだ」
- 「締切までに終わらない、詰んだ…」
- 「電車逃して詰み。次は30分後か…」
類義語
詰み、終わった、万事休す
ゲーム用語から日常会話に浸透した表現で、「もう打つ手がない」「どうしようもない状況」を端的に表現できるため、SNS上でよく使われます。
尊い
意味
純粋で美しく、保護したくなるような対象に対する崇拝や感動の気持ち。
由来
本来は「尊敬に値する、貴重である」という意味の日本語。
使用例
- 「赤ちゃんと遊ぶ推しの姿、尊すぎる…」
- 「一生懸命練習する姿が尊い」
- 「純粋な笑顔が尊すぎて心が浄化される」
類義語
神聖、いとおしい、癒される
「尊い」は元々宗教的な文脈で使われていましたが、アニメやアイドルのファン文化の中で「純粋で心打たれる」という意味で広く使われるようになりました。
単なる「かわいい」とは異なり、より深い感動や敬愛の念を含みます。
【関連記事】
- 「尊い」「エモい」表現の深掘り解説【SNS時代の感情表現完全ガイド】
- 「推し」「尊い」「エモい」「沼る」の意味と変遷【SNS時代の感情表現辞典】
- 「エモい」「尊い」「癒し」の違いと使い分け【感情表現の新語解説】
- 「尊い」「推せる」「神推し」の違いと使い分け【ファン表現の正しい用法】
- 「尊い」「づまりすぎ」「沼る」の意味と使い分け|オタク用語の完全ガイド
エモい
意味
複雑な感情が入り混じって言葉では表現しきれない状態。
懐かしさ、切なさ、感動などが複雑に絡み合った感情。
由来
英語の「emotional(感情的な)」から来ています。
使用例
- 「夕日を見ながら聴く音楽、エモすぎる」
- 「青春時代の写真見つけて、エモくなった」
- 「雨の日の駅のホーム、なんかエモい」
類義語
感慨深い、しみじみする、胸に迫る
「エモい」は特定の感情を指すのではなく、複数の感情が混ざり合った状態を一言で表現できる便利な言葉として広まりました。
特に懐かしさや儚さを感じる瞬間によく使われます。
【関連記事】
- 「尊い」「エモい」表現の深掘り解説【SNS時代の感情表現完全ガイド】
- 「推し」「尊い」「エモい」「沼る」の意味と変遷【SNS時代の感情表現辞典】
- 「エモい」「尊い」「癒し」の違いと使い分け【感情表現の新語解説】
沼る
意味
ある趣味や対象にどっぷりはまり込み、抜け出せなくなった状態。
由来
「沼にはまる」という表現が動詞化したもの。
使用例
- 「推しの沼にハマって、グッズ集めが止まらない」
- 「韓国ドラマに沼って、毎日3時間は見てる」
- 「カメラ沼から抜け出せず、レンズを5本も買ってしまった」
類義語
ハマる、のめり込む、沼落ち
「沼る」は単なる「ハマる」より深い熱中状態を表し、時間やお金を際限なく費やしてしまう様子を自虐的に表現するのに使われます。
一度入ると抜け出しにくい「沼」という比喩が効果的に使われています。
【関連記事】
状況描写系SNS用語
特定の状況や状態を簡潔に表現するSNS用語を紹介します。
草
意味
インターネット上で笑うこと、おかしいと思うこと。
由来
「w」(笑いを表す「ワラ」の頭文字)が複数連なると草が生えているように見えることから。
使用例
- 「それは草」
- 「草生える」
- 「大草原不可避」
類義語
笑、ワロタ、爆笑
「w」→「草」→「大草原」→「ジャングル」など、笑いの程度によって表現が拡張されることもあります。
SNS上で感情を表現する独特の言葉です。
【関連記事】「草」「www」「爆笑」「笑」の違いと使い分け【オンライン笑い表現の変遷】
ぴえん
意味
悲しみや切なさを表現する言葉。
泣きそうな感情を表します。
由来
泣く様子を表す擬音語「ぴえ〜ん」から。
使用例
- 「テスト落ちた…ぴえん」
- 「推しのライブチケット取れなかった、ぴえん」
- 「待ち合わせに遅れて友達に怒られた、ぴえん」
類義語
悲しい、泣きたい、切ない
「ぴえん」は2019年頃から若者を中心に広まり、「ぴえん超えてぱおん」など派生形も生まれました。
軽めの悲しみを表現するのに使われることが多いです。
【関連記事】「ぴえん」「それな」「リスぺクト」の意味と変遷|SNS時代の新語辞典
リアタイ
意味
「リアルタイム」の略。
何かを実際に起こっている時間に合わせて視聴したり参加したりすること。
由来
「リアルタイム」を短縮した言葉。
使用例
- 「今夜の番組、リアタイで見る予定」
- 「配信、リアタイで参加できなかった…」
- 「トレンド入りしてるから、リアタイで反応見るの面白い」
類義語
生で見る、同時視聴、ライブ視聴
特にテレビ番組やネット配信において、録画やアーカイブではなく、放送時間中にリアルタイムで視聴することを指します。
SNSでの実況コメントと合わせて楽しむ文化も広がっています。
積みタワー
意味
買ったものの未読・未視聴・未使用のまま積み上がっている本やゲーム、映像作品などの集積。
由来
「積み重なったタワーのように高くなる」というイメージから。
使用例
- 「積みタワーが崩れないように気をつけて本を抜き取る」
- 「また新刊買っちゃった…積みタワー崩壊しそう」
- 「積みタワー消化するために一ヶ月休みたい」
類義語
積読(つんどく)、買いっぱなし
元々「積読(本を買ったものの読まずに積んでおくこと)」から派生し、ゲームソフト(積みゲー)や映像作品(積みドラマ)など様々なコンテンツに使われるようになりました。
消費より購入のペースが早い現代人の悩みを象徴する言葉です。
沸いた
意味
群衆やオンラインコミュニティが一斉に盛り上がること。
熱狂や興奮状態になること。
由来
水が熱せられて沸騰するイメージから。
使用例
- 「サプライズ発表で会場が沸いた」
- 「推しの名前が呼ばれた瞬間、TLが沸いた」
- 「あの発言でファンが沸きすぎ」
類義語
盛り上がる、熱狂する、湧く
主にコンサートや配信の視聴者が一斉に反応する様子や、SNSのタイムラインが特定の話題で活気づく様子を表現します。
ポジティブな盛り上がりを指すことが多いです。
インターネット文化系SNS用語
インターネット特有の文化や習慣から生まれた表現を紹介します。
高まる
意味
テンションが上がる、興奮する、気持ちが高ぶる状態。
由来
「気持ちが高まる」という表現が省略されたもの。
使用例
- 「推しの新曲発表で高まってる」
- 「週末のライブに向けて高まる一方」
- 「このMV見ると毎回高まる」
類義語
テンション上がる、興奮する、ハイテンション
主にポジティブな興奮や期待感が高まる状態を表します。
特にアイドルやアーティストのファンが、推しに関する情報や出来事に対して使うことが多いです。
トレンド入り
意味
ある話題やハッシュタグがSNS(特にTwitter)のトレンドランキングに表示されること。
由来
SNSの「トレンド(trend)」機能に由来。
使用例
- 「あのハッシュタグ、トレンド入りしてる!」
- 「新商品発売でブランド名がトレンド入りした」
- 「びっくりするような話題でトレンド入りしてた」
類義語
バズる、話題になる、ランクイン
SNS上で多くの人が同時に言及している話題が「トレンド」として表示される機能から生まれた表現です。
トレンド入りは注目度の高さを示すバロメーターとなり、マーケティングや広報活動の成果指標としても使われます。
オタク失格
意味
好きなものについての知識が不足していたり、ファン活動が不十分だと自虐的に表現する言葉。
由来
「〜失格」という表現に「オタク」を組み合わせたもの。
使用例
- 「推しの新曲、まだ聴いてない…オタク失格だ」
- 「全ての衣装を言えないなんて、オタク失格だね」
- 「グッズ持ってないとか、オタク失格じゃん」
類義語
ヘタレファン、にわか、ライト層
自分のファン活動や知識が不十分だと感じた時に自虐的に使う表現です。
実際には深刻に考えておらず、冗談めかして使われることが多いです。
聖地巡礼
意味
アニメや映画、ドラマなどの作品に登場した実在の場所を訪れること。
由来
宗教的な「聖地巡礼」から転じたもの。
使用例
- 「休日を使って推しの聖地巡礼してきた」
- 「あの映画の聖地巡礼ルートを計画中」
- 「聖地巡礼で地元の経済も潤う」
類義語
ロケ地訪問、舞台探訪
もともとはアニメファンの間で使われていた言葉ですが、現在では映画やドラマ、アイドルや有名人ゆかりの場所を訪れることも「聖地巡礼」と呼ばれるようになりました。
観光産業にも影響を与える現象として注目されています。
沼落ち
意味
新しい趣味や対象に急にハマること。
特にお金や時間を大量に消費するような趣味にハマった状態。
由来
「沼にはまる(抜け出せなくなる)」という表現と「落ちる」を組み合わせたもの。
使用例
- 「推しに沼落ちして、全グッズ集め始めた」
- 「フィギュア収集に沼落ちして財布が危険」
- 「新しいゲームに沼落ちして毎日徹夜中」
類義語
沼る、どハマりする、のめり込む
「沼落ち」は「沼る」と似ていますが、特にハマり始めの段階や、急激にのめり込んだ状態を表現することが多いです。
自分の熱中ぶりを自虐的に表現する言葉です。
ビジネスシーンでの使い方
SNS用語は基本的にカジュアルな表現ですが、適切な場面では効果的に使うこともできます。
ここでは、ビジネスシーンでの適切な使い方と言い換え表現を紹介します。
ビジネスで使えるSNS用語
以下のSNS用語は、カジュアルなビジネス場面でも使用できることがあります。
- エゴサ – マーケティング担当者やPR担当者の間では一般的な用語になっています
- 例:「定期的なエゴサで顧客の声を拾い上げましょう」
- トレンド入り – デジタルマーケティングの文脈では使用可能
- 例:「キャンペーンハッシュタグのトレンド入りを目指します」
- リアタイ – デジタルコンテンツや配信に関する場面で
- 例:「新製品発表はリアタイで視聴できるようにライブ配信します」
ビジネスでの言い換え表現
以下のSNS用語は、ビジネスシーンでは言い換えた方が良いでしょう。
- メンブレ → 「精神的に疲労している」「一時的に判断力が低下している」
- 例:「メンブレ気味で…」→「少し精神的に疲れているため…」
- 草 → 「面白い」「興味深い」
- 例:「それは草」→「それは興味深いですね」
- ぴえん → 「残念です」「遺憾です」
- 例:「ぴえん」→「大変残念に思います」
- 沼る → 「深く取り組んでいる」「集中的に研究している」
- 例:「この案件に沼ってる」→「この案件に集中的に取り組んでいます」
- 高まる → 「期待が高まる」「意欲が向上する」
- 例:「高まってる」→「意欲が高まっています」
年代別・業界別の使い分け
SNS用語の使用は相手や状況によって適切さが変わります。
年代別の目安:
- 20代との会話:ほとんどのSNS用語が通じる
- 30-40代との会話:「エゴサ」「トレンド」など一部は通じる
- 50代以上との会話:基本的に避け、一般的な表現を使う
業界別の目安:
- IT・広告・メディア業界:比較的多くのSNS用語が許容される
- 金融・法律・医療業界:公式の場では基本的に避ける
- 教育・公共機関:公式の場では避け、若者との交流の文脈でのみ使用
ビジネスシーンでSNS用語を使う際は、相手や場の雰囲気を見極めることが大切です。
使用に迷ったら、より一般的な表現を選ぶのが無難でしょう。
まとめ
SNS用語は現代のコミュニケーションにおいて欠かせない表現となっています。
これらの言葉の意味や適切な使い方を理解することで、オンライン上でのコミュニケーションをより円滑に進めることができるでしょう。
覚えておきたいポイント
- SNS用語の本質: 既存の言葉では表現しきれないニュアンスや感情を簡潔に伝えるために生まれた表現
- 使い分けの重要性: 場面や相手に応じて適切に使い分け、公式な場では一般的な表現に言い換える
- 世代間ギャップの認識: SNS用語の理解度には世代差があることを認識し、必要に応じて説明を加える
- 進化し続ける言葉: SNS用語は常に進化しており、新しい表現が次々と生まれている
SNS用語は単なる若者言葉ではなく、現代のコミュニケーションを豊かにする表現として認識されつつあります。
適切に使いこなすことで、あなたのコミュニケーション能力も向上するでしょう。
よくある質問(FAQ)
Q1: SNS用語を使うと年齢がバレますか?
A: 世代によって使用するSNS用語や使い方に特徴があるため、ある程度年齢層が推測されることはあります。
例えば、「草」や「ぴえん」は若年層に多く、「orz」や「ワロタ」などの古めのネット用語を使うと、ネットを長く使っている年代と推測されることもあります。
ただし、SNS用語の理解や使用は個人差が大きいため、単純に年齢だけでは判断できません。
様々な世代の表現に触れることで、コミュニケーションの幅を広げることができるでしょう。
Q2: ビジネスメールでSNS用語を使っても大丈夫ですか?
A: 基本的には、ビジネスメールでのSNS用語の使用は避けるべきです。
特に以下の点に注意しましょう。
- 正式なビジネス文書では使用しない
- 目上の人や取引先とのメールでは避ける
- 初めてのやり取りでは使わない
ただし、以下のような例外もあります。
- 若い世代が中心の職場の内部コミュニケーション
- デジタルマーケティングなど、SNS関連の業務内容についての会話
- すでに親しい関係が構築できている相手との非公式なやり取り
使用に迷った場合は、より一般的で公式な表現を選ぶのが無難です。
Q3: SNS用語について行けない場合はどうすればいいですか?
A: SNS用語は常に変化しているため、全てを把握するのは難しいものです。
以下の対処法が役立つでしょう。
- 分からない表現があれば素直に質問する
- オンライン辞典やSNS用語集を活用する
- コンテキストから意味を推測する
- SNSやオンラインコミュニティを定期的にチェックする
SNS用語について行けないと感じても焦る必要はありません。
誰もが全ての表現を理解しているわけではなく、必要に応じて学んでいくという姿勢が大切です。
Q4: 海外のSNS用語との違いはありますか?
A: 海外、特に英語圏のSNS用語と日本のSNS用語には、共通点と相違点があります。
共通点:
- 短縮表現の多用(「LOL」→「laughing out loud」、「エゴサ」→「エゴサーチ」)
- 若者文化から生まれる傾向
- 感情表現が豊富(「ぴえん」と「sad」や「crying」の絵文字の使用など)
相違点:
- 日本のSNS用語は「〜する」という動詞化(「沼る」「メンブレる」)が特徴的
- 英語圏では頭字語(「FOMO」「TBT」など)が多い
- 日本語は表意文字(漢字)と表音文字(ひらがな・カタカナ)の組み合わせによる言葉遊びが豊富
海外のSNS用語の例としては、「FOMO(Fear Of Missing Out:取り残される恐怖)」「TBT(Throwback Thursday:過去の写真を木曜日に投稿する習慣)」「Stan(熱狂的なファン)」などがあります。
日本のSNS用語と同様に、流行の変化が速い点は共通しています。
Q5: 親や先生にSNS用語を説明するにはどうすればいいですか?
A: 年代の異なる方々にSNS用語を説明する際のポイントは以下の通りです。
- 具体例を交えて説明する
- 例:「エゴサとは、自分の名前をネットで検索することです。例えば会社名や製品名で検索して評判を調べることもエゴサと言います」
- 元の意味や由来から説明する
- 例:「『メンブレ』は『メンタルが崩れる』という言葉が短くなったもので、一時的に落ち込んだりストレスを感じたりする状態を表します」
- 世代に合わせた比較表現を使う
- 例:「『沼る』は昔で言う『のめり込む』や『夢中になる』に近いですが、もっと自虐的なニュアンスがあります」
- 文化的背景も含めて説明する
- 例:「『推し』という言葉はアイドルファン文化から生まれました。単に好きなだけでなく、積極的に応援する対象を指します」
- 否定的な反応を示さず、言語の進化として説明する
- 例:「言葉は時代とともに変化するもので、SNS用語も現代のコミュニケーションを豊かにする表現の一つです」
相手に合わせた説明を心がけることで、世代間の理解が深まり、コミュニケーションがより円滑になるでしょう。
Q6: 新しいSNS用語はどのように生まれるのですか?
A: 新しいSNS用語が生まれる過程には、いくつかのパターンがあります。
- 既存表現の短縮・変形
- 例:「エゴサーチ」→「エゴサ」、「メンタルブレイク」→「メンブレ」
- 若者コミュニティでの言葉遊び
- 例:「w」(笑い)→「草」(wが並ぶと草に見える)
- 他言語からの取り入れと日本語化
- 例:「Stan」→「推し」(意味は異なるが機能は類似)
- 擬音語・擬態語の活用
- 例:「ぴえ〜ん」(泣き声)→「ぴえん」
- 有名人・インフルエンサーの発言
- YouTuberや人気配信者が使った表現が広まることも多い
- アニメ・ゲーム用語の一般化
- 例:「フラグ」(ゲーム用語)→「壮大フラグ」(日常会話)
SNS用語は、使いやすさ、表現の簡潔さ、独自性などが評価され、共感を得ることで急速に広がります。
また、SNSのアルゴリズムが特定の表現の拡散を加速させる側面もあります。
Q7: 子どもがSNS用語を使いすぎるのが心配です。どうすればいいですか?
A: 子どものSNS用語使用について心配な場合は、以下のアプローチが役立つでしょう。
- 禁止せず、興味を示す
- 言葉狩りをすると反発を招くので、まずは子どもの使う表現に興味を持つ
- TPOの意識を育てる
- 「学校の先生や祖父母と話すときはどう言い換えるといいかな?」など、状況に応じた言葉選びを一緒に考える
- 言葉の背景を理解させる
- なぜその言葉が生まれたのか、どんなニュアンスがあるのかを考えさせる
- バランス感覚を身につけさせる
- SNS用語だけでなく、幅広い語彙力を身につけることの大切さを伝える
- コミュニケーションの本質を教える
- 言葉選びは相手に自分の気持ちを伝えるためのものだと教える
SNS用語の使用自体は問題ではなく、場面や相手に応じた適切な言葉選びができることが大切です。
親子でコミュニケーションについて話し合う機会にするとよいでしょう。
Q8: 企業の公式SNSでこうした用語を使うべきですか?
A: 企業の公式SNSでのSNS用語の使用については、以下のポイントを考慮するとよいでしょう。
使用を検討できる状況:
- ターゲット層が若年層中心の場合
- カジュアルなブランドイメージを持つ企業
- トレンドに敏感なファッションや娯楽関連の業種
- コミュニティ感の醸成が目的の場合
避けるべき状況:
- 金融、医療、法律など信頼性が特に重視される業種
- 主要顧客が年配層の場合
- 国際的な発信を行っている場合(文化的誤解を招く可能性)
- 危機管理・謝罪などの重要なアナウンス
バランスの取り方:
- SNS担当者にガイドラインを設ける
- 使用前に複数人でチェックする
- トレンドを追いかけすぎない(すぐに古びる可能性)
- 文脈を理解せずに使わない
- 試験的に使用して反応を見る
企業SNSでのSNS用語の使用は、ブランドの一貫性、ターゲット層との親和性、業界の特性などを総合的に判断して決めるべきです。
無理に若者言葉を使うと、「バブルおじさん」「痛い企業アカウント」と逆効果になる可能性もあります。
Q9: SNS用語辞典やトレンドをチェックできるサイトはありますか?
A: SNS用語やネット流行語をチェックできるサイトやリソースには以下のようなものがあります。
- Web辞書・用語集
- 「ネット流行語大賞」関連サイト
- 「若者言葉辞典」系のウェブサイト
- 「コトバンク」のインターネット用語集
- SNSで確認する方法
- Twitter/Xのトレンド機能
- 人気ハッシュタグをチェック
- TikTokの人気トレンドコーナー
- メディア・ニュースサイト
- IT系ニュースサイトの「ネット用語」カテゴリ
- 若者向けウェブメディアの用語解説コーナー
- 「新語・流行語大賞」のノミネート発表
- 書籍
- 定期的に出版されるネット用語辞典
- 若者文化研究の書籍
最新のSNS用語を把握するには、定期的にSNSを利用する若年層のアカウントをフォローしたり、トレンドタグを追ったりするのが効果的です。
ただし、SNS用語は非常に早く変化するため、完全に追いつくことは難しいかもしれません。
Q10: SNS用語の将来はどうなると思いますか?
A: SNS用語の将来については、以下のような展望が考えられます。
- 一部は一般語化する
- 「エモい」「推し」などの一部の表現は既に一般化しつつあり、今後辞書にも掲載される可能性がある
- メディア間の垣根が低くなる
- Twitter発、TikTok発など、特定プラットフォーム発の言葉が他のメディアにも広がる傾向が強まる
- 世代間ギャップの縮小
- SNSの普及により、年代を超えた用語の共有が進む
- 国際的な影響の増加
- グローバルSNSの影響で、海外発の表現が日本語化するケースが増える
- 音声・映像ベースの表現の台頭
- 文字だけでなく、特定の音声や動作を表す表現(TikTokの「推しカメラ」など)も増加
- AIとの相互影響
- AIツールとの会話が増えることで、新たな表現形態が生まれる可能性
SNS用語は言語の自然な進化の一部であり、今後も社会変化や技術の発展に合わせて変化し続けるでしょう。
コミュニケーションがより効率的に、また豊かになる方向で発展していくことが期待されます。
関連記事