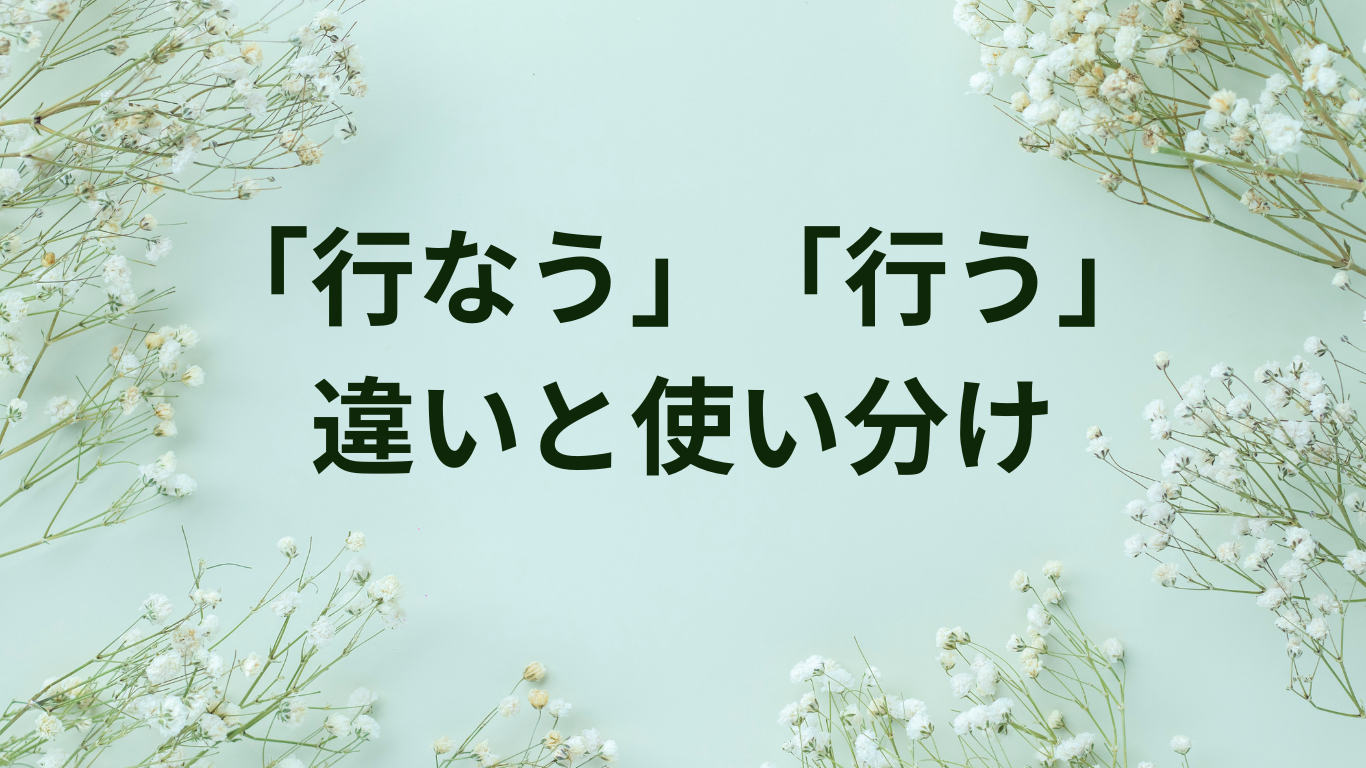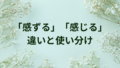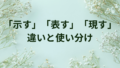「行なう」と「行う」、どちらが正しい表記なのか迷ったことはありませんか?
同じ意味を持つこれらの表記ですが、実は書き方に明確なルールがあります。
この記事では、「行なう」と「行う」の違いや正しい使い方について詳しく解説します。
送り仮名の基本ルールから実際の使い分け例まで、言葉の専門家が徹底解説しますので、今後の文章作成に自信を持って取り組めるようになるでしょう。
結論から言えば、現代の標準的な表記は「行う」ですが、「行なう」にも一定の根拠があります。
「行なう」と「行う」の基本的な意味の違い
「行なう」と「行う」は同じ動詞「おこなう(行う)」の表記の違いです。
意味としては「物事を実際に実行する・実施する」という点で共通しています。
辞書的な定義
国語辞典での「行う(おこなう)」の定義は以下の通りです:
- 計画したことや決めたことを実際に実行する
- 儀式や催し物などを執り行う
- 道徳や規則などを実践する
この意味において、「行なう」と「行う」に違いはありません。
違いは送り仮名の表記方法にあります。
送り仮名のルール
送り仮名とは、漢字に付ける平仮名のことで、文部科学省の「送り仮名の付け方」によれば、「行う」の標準的な表記は「行う」とされています。
これは最小限の送り仮名を用いる「本則」に基づいています。
一方で「行なう」という表記は、「なう」の部分まで送り仮名として表記する「許容」の範囲とされています。
つまり、正式には「行う」が標準ですが、「行なう」も完全に間違いというわけではないのです。
これは「漢字の意味を明確にするために必要な送り仮名」という考え方と「読みやすさを重視した送り仮名」という考え方の違いから生じています。
「行なう」と「行う」の使い分けのポイント
公的文書・ビジネス文書での使い分け
| 文書の種類 | 推奨される表記 | 理由 |
|---|---|---|
| 公文書 | 行う | 公用文の基準に準拠 |
| ビジネス文書 | 行う | 簡潔さと一般性を重視 |
| 学術論文 | 行う | 学術的慣例に基づく |
| 報道記事 | 行う | 新聞社・通信社の標準に基づく |
多くの組織や企業では社内の文書作成基準を設けており、その多くは文部科学省の「送り仮名の付け方」に準拠して「行う」を採用しています。
文学作品・個人的文章での使い分け
文学作品や個人的な文章では、「行なう」という表記が好まれる場合もあります。
これは「な」を含めることで、より読みやすさを重視した表記だと考えられているためです。
特に小説や随筆などでは作家の個性や好みとして「行なう」が選ばれることがあります。
使い分けの実際
実際には、どちらを使うかはその文書の性質や、所属する組織のルールによって決まることが多いです。
ただし、同じ文書内では一貫性を持って表記することが重要です。
「行う」と「行なう」が混在すると、文書全体の統一感が損なわれてしまいます。
よくある間違い & 誤用例
同一文書内での不統一
🚫 「会議を行なう予定です。また、研修も行う予定となっております。」
✅ 「会議を行う予定です。また、研修も行う予定となっております。」
組織のルールに合わない使用
🚫 (社内規定で「行う」と定められている企業で)「プロジェクトを行なうことになりました」
✅ 「プロジェクトを行うことになりました」
「行なう」と「行う」の混合使用
多くの文書作成ソフトでは校正機能があり、送り仮名の不統一を指摘してくれます。
しかし、自動修正されない場合もあるため、最終的な確認は人の目で行うことが重要です。
類似表現との混同
「行(ぎょう)」という漢字を含む別の言葉、例えば「行列(ぎょうれつ)」や「行為(こうい)」などと混同しないように注意が必要です。
これらは「おこなう」とは読み方も意味も異なります。
文化的背景・歴史的背景
送り仮名の歴史
送り仮名の付け方は時代によって変化してきました。
明治時代以前は必ずしも統一されておらず、個人の好みや慣習によって様々な表記が存在していました。
「行なふ」「行ふ」などの古い表記もその一例です。
現代の送り仮名のルールは、1973年に内閣告示された「送り仮名の付け方」が基本となっています。
この中で「行う」が本則、「行なう」が許容として定められました。
表記の変遷
戦前は「行ふ」という表記が一般的でしたが、戦後の国語改革で「行う」に変わりました。
また、多くの古典文学では「行なふ」という表記も見られ、これが現代の「行なう」の源流となっています。
送り仮名の付け方に関する議論は現在も続いており、「読みやすさ」「分かりやすさ」「伝統」などの観点から様々な意見があります。
実践的な例文集
日常会話での使用例
- 「明日、町内会のイベントを行う予定です。」
- 「子どもたちと一緒に実験を行うのは楽しい。」
ビジネス文書での使用例
- 「第3四半期に市場調査を行う予定です。」
- 「新製品の発表会を来月行うことになりました。」
公文書での使用例
- 「本事業は国の補助金を活用して行うものである。」
- 「選挙管理委員会が投票の管理を行う。」
文学的な表現での使用例
- 「彼は静かに儀式を行なった。その所作には古来からの伝統が息づいていた。」
- 「人知れず善行を行なう彼女の姿に、深い感銘を受けた。」
関連表現と言い換え
「行う」の言い換え表現としては、「実施する」「実行する」「執り行う」「催す」などがあります。
状況や文脈に応じて使い分けると、文章に変化をつけることができます。
まとめ
「行なう」と「行う」の違いは意味ではなく、送り仮名の付け方にあります。
現代の標準的な表記は「行う」ですが、「行なう」も許容範囲内とされています。
覚えておきたいポイント
- 公的文書やビジネス文書では「行う」が一般的
- 文学作品では作家の好みで「行なう」が使われることもある
- 同一文書内では表記を統一することが重要
- 所属する組織や出版社などのルールに従う
- どちらを選んでも完全な誤りではないが、一貫性を持たせる
送り仮名の付け方には明確なルールがありますが、一部許容される範囲もあります。
重要なのは、一貫性を持って使用することと、対象となる文書の性質や目的に合わせて適切な表記を選ぶことです。
よくある質問(FAQ)
Q1: 学校の試験やレポートではどちらを使うべきですか?
A: 基本的には「行う」を使用するのが無難です。
ただし、学校や教師から特別な指示がある場合はそれに従いましょう。
Q2: 「行ない」と「行い」はどちらが正しいですか?
A: 名詞形の場合も同様に、「行い」が標準的な表記で、「行ない」は許容される表記です。
「良い行い」などと使います。
Q3: 類似の言葉(例:「計る」と「測る」)の送り仮名の付け方も同じルールですか?
A: 漢字によって送り仮名のルールは異なります。
「計る/測る/量る/図る」などは意味によって漢字自体が変わる例で、「行う/行なう」とは異なるケースです。
Q4: 文学作品を書く場合、どちらの表記が好まれますか?
A: 文学作品では個人の文体や好みが尊重されるため、どちらの表記も可能です。
ただし、出版社によってスタイルガイドがある場合はそれに従うことが一般的です。