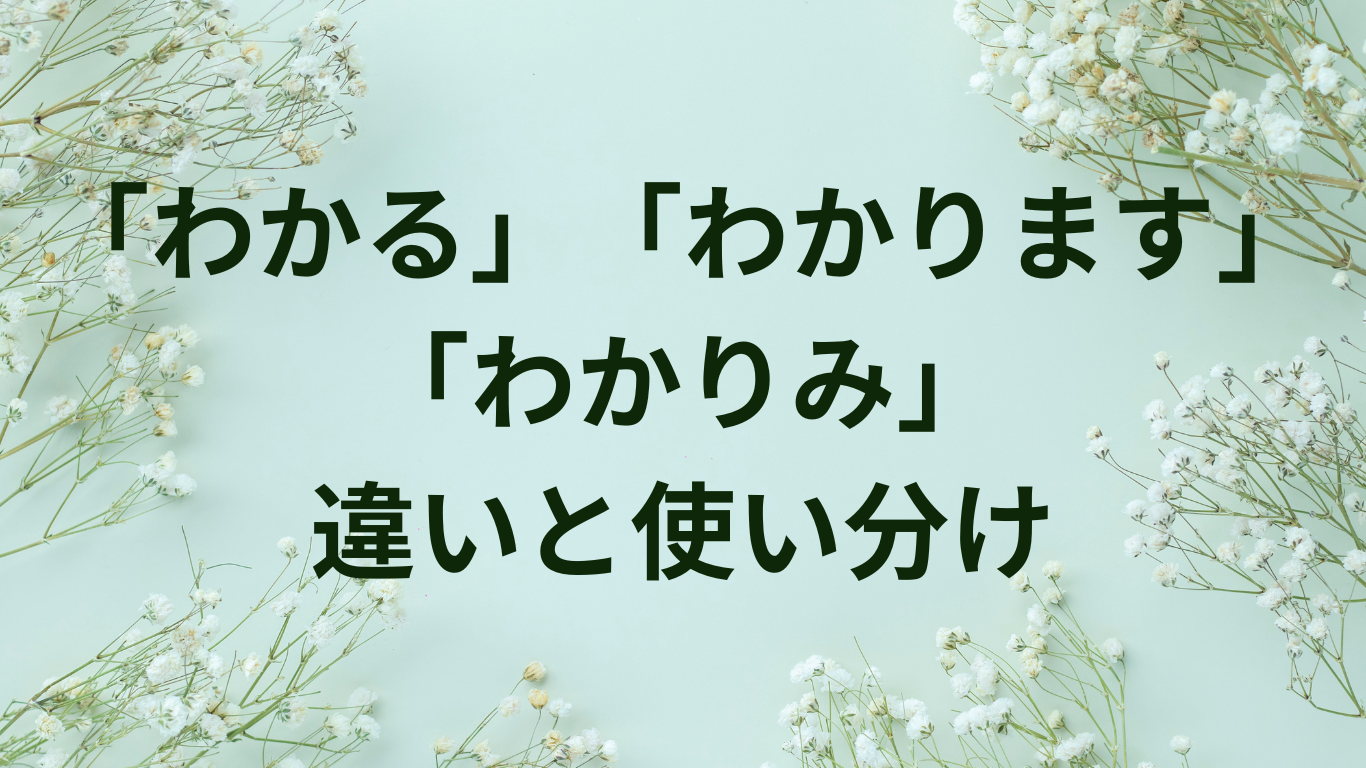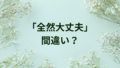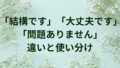共感を示す表現として、「わかる」「わかります」「わかりみ」を見かけることが増えてきました。
特にSNSでは、相手の気持ちに寄り添うためにこれらの言葉が頻繁に使われています。
しかし、それぞれの言葉にはニュアンスの違いがあり、状況によって適切な使い分けが求められます。
誤った使い方をすると、意図せず失礼な印象を与えたり、コミュニケーションエラーを起こしたりするリスクがあります。
この記事では、これら3つの表現の違いや使い分けのポイント、そして文化的背景までを詳しく解説します。
シーンに合わせた適切な共感表現を身につけて、より円滑なコミュニケーションを目指しましょう。
この記事でわかること
- 「わかる」「わかります」「わかりみ」の基本的な意味の違い
- フォーマル度と共感の強さによる使い分け方
- 世代別の解釈と適切な使用シーン
- よくある誤用パターンとその修正方法
- これらの表現の文化的・歴史的背景
- 実践で使える例文40選
- 「わかる」「わかります」「わかりみ」の基本的な意味の違い
- 使い分けのポイント
- よくある間違いと誤用例
- 「わかる」「わかります」「わかりみ」の文化的・歴史的背景
- 実践的な例文集
- 言い換え表現
- まとめ
- よくある質問(FAQ)
- Q1: 「わかりみ」はビジネスの場で使っても良いですか?
- Q2: 「わかる」と「理解する」の違いは何ですか?
- Q3: 「わかりみ」の類似表現はありますか?
- Q4: 「わかります」「わかりました」の違いは?
- Q5: 50代以上の人と話すとき、「わかりみ」を使うのは失礼になりますか?
- Q6: 「わかりみ」はいつ頃から使われるようになった表現ですか?
- Q7: 仕事のメールで「わかる」と書いてしまいました。問題があるでしょうか?
- Q8: 「わかりみが深い」とはどういう意味ですか?
- Q9: 英語に「わかりみ」に相当する表現はありますか?
- Q10: 「わかる」「わかります」「わかりみ」以外に共感を示す日本語表現はありますか?
「わかる」「わかります」「わかりみ」の基本的な意味の違い
これら3つの言葉は、いずれも相手の状況や気持ちを理解・共感していることを示す表現ですが、それぞれに異なる特徴があります。
「わかる」の基本的意味
「わかる」は最もシンプルな共感表現で、カジュアルな場面で多く使われます。
- 「理解できる」という意味の動詞「分かる」をそのまま使った表現
- 文法的には普通体(常体)であり、友人同士の会話やSNSのコメントなど、親しい間柄やカジュアルな場面で使われることが多い
- シンプルな表現であるがゆえに、多様な場面で使いやすい特徴がある
例えば、友人が「今日は疲れた」と言った時に「わかる」と返すことで、相手の状況に共感していることを伝えられます。
「わかります」の基本的意味
「わかります」は「わかる」の丁寧体(敬体)であり、より丁寧な印象を与えます。
- フォーマルな場面や、目上の人との会話、初対面の人とのやり取りなどで使われることが多い
- 「わかります」は単なる丁寧な表現にとどまらず、相手の話をしっかりと受け止めて理解していることをより強調する効果もある
例えば、カスタマーサービスの場面で「ご不便をおかけして申し訳ありません。
お客様のお気持ちはよくわかります」というように使われます。
「わかりみ」の基本的意味
「わかりみ」は比較的新しいインターネットスラングで、「わかる」を変形させた表現です。
- 「理解(わかり)見(み)」と分解できるが、実際には「深く共感する」「心から理解できる」というニュアンスを持つ
- 「わかる」よりも強い共感を示したい時に使われ、特に若年層のSNSやオンラインコミュニティで広まっている
- 2010年代後半から2020年代初頭にかけてオンラインゲームやVTuberコミュニティなどで使われ始めた比較的新しい表現
例えば、友人が「リモートワークだと集中できないことがある」と言った時に、「それ、わかりみが深い」と返すことで、非常に共感できる・同じ経験をしていることを強調できます。
「わかる」がシンプルな理解を示すのに対し、「わかりみ」はより感情的で強い共感を表現できるため、特に若者文化の中で人気を集めています。
使い分けのポイント
状況や相手との関係性によって、これら3つの表現の使い分けが重要になります。
適切な使い分けのポイントを、シーン別に解説します。
フォーマル度による使い分け
| 表現 | フォーマル度 | 適した場面 |
|---|---|---|
| わかります | 高い | ビジネス会話、目上の人との会話、公式の場 |
| わかる | 中程度 | 友人との会話、カジュアルな場面、SNSの一般的なやりとり |
| わかりみ | 低い | 親しい友人とのSNS、若者同士の会話、オンラインコミュニティ |
フォーマルな場面(ビジネス・公式の場)
- 基本的に「わかります」または「理解しております」など丁寧な表現を使用する
- 「わかる」や「わかりみ」の使用は避けるべき
- 特に取引先や顧客とのコミュニケーションでは、「わかります」または「理解しております」という言い回しが最も信頼性を高める効果がある
カジュアルな場面(友人との会話・SNS)
- 若者同士:「わかる」や「わかりみ」を自由に使用可能
- 世代が混在する場:誤解を避けるため、表情やトーンで意図を明確にする
- SNSでは#やばいなどのハッシュタグと絵文字を組み合わせて意図を明確に
共感の強さによる使い分け
| 表現 | 共感の強さ | ニュアンス |
|---|---|---|
| わかります | 中程度 | 「あなたの状況を理解し、共感しています」 |
| わかる | やや弱い〜中程度 | 「理解した」「そうだね」 |
| わかりみ | 非常に強い | 「超共感!」「めちゃくちゃわかる!」 |
「わかりみ」を使用する場合、単に「わかる」では表現できない強い共感や感情を伝えたい時に効果的です。
特に若者間のSNSやメッセージアプリでのコミュニケーションで重宝されています。
世代別の解釈と使い分け
世代によって、これらの表現の捉え方や使用頻度は大きく異なります。
10代~20代前半
- ポジティブな意味での「わかりみ」の使用が多い
- 「わかりみが深い」「わかりみの深海」などの派生表現も活用
- SNS上でも頻繁に使用
- イントネーションや絵文字で意味を補完する傾向が強い
30代~40代
- 「わかる」と「わかります」の両方を状況に応じて使い分ける
- 「わかりみ」の意味は理解しているが、日常的には使わない人も多い
- ビジネスシーンでは基本的に「わかります」を使用
- フォーマルさを重視する傾向がある
50代以上
- 基本的に「わかります」を丁寧な表現として使用
- 「わかる」はカジュアルな場面に限定して使用する傾向
- 「わかりみ」を知らない、または違和感を持つ人が多い
- 調査によると、50代以上の約85%が「わかりみ」という表現を知らない、または意味を誤解している
SNS・オンラインでの使い分け
| 表現 | プラットフォーム | 適切さ |
|---|---|---|
| わかる | Twitter/X、Instagram、TikTok | ⭕ 適切 |
| わかります | LinkedIn、ビジネス向けSNS | ⭕ 適切 |
| わかりみ | Twitter/X、TikTok、Discord | ⭕ 特定コミュニティで適切 |
SNSでは、そのプラットフォームの文化や目的に応じて使い分けるとよいでしょう。
プロフェッショナルな交流が中心のLinkedInでは「わかります」、若者文化が色濃いTikTokでは「わかる」や「わかりみ」が適しています。
よくある間違いと誤用例
これらの表現を誤って使うと、意図せずコミュニケーションエラーを起こすことがあります。
よくある間違いと正しい使い方を見ていきましょう。
ビジネスシーンでの誤用
🚫 誤用例1:「プロジェクトの進捗が遅れていることについて、わかる」
✅ 正しい例:「プロジェクトの進捗が遅れていることについて、理解しています/わかります」
ビジネスシーンではカジュアルな「わかる」より、「わかります」や「理解しております」などの丁寧な表現を必ず使用すべきです。
特に上司や取引先とのコミュニケーションでは、丁寧な表現を用いることで信頼性が向上します。
「わかりみ」の過剰使用
🚫 誤用例2:「お客様のご不満については、わかりみがあります」
✅ 正しい例:「お客様のご不満については、よく理解しております」
「わかりみ」はインターネットスラングであり、フォーマルな場面では絶対に使用すべきではありません。
特にビジネスやカスタマーサービスの場面では、顧客満足度を低下させるリスクがあるため、避けましょう。
世代間コミュニケーションでの誤用
🚫 誤用例3:50代以上の人に対して「それ、わかりみ」と言う
✅ 正しい例:50代以上の人に対して「それは私もよくわかります」と言う
「わかりみ」は主に10〜30代の若者文化から生まれた表現であり、それを知らない人に使うと混乱を招く恐れがあります。
年齢層に合わせた表現選びが、世代間コミュニケーションの鍵です。
公的な場での使用
🚫 誤用例4:就職面接で「御社の理念には、わかりみがあります」
✅ 正しい例:「御社の理念に深く共感いたします」
面接などのフォーマルな場面では特に注意が必要です。
「わかりみ」のような多義的で口語的な表現は避けましょう。
「わかる」「わかります」「わかりみ」の文化的・歴史的背景
これらの表現がどのように生まれ、発展してきたのかを理解することで、より適切に使いこなせるようになります。
「わかる」の進化
「わかる」という表現自体は日本語の基本的な動詞ですが、SNS時代になって新たな使われ方が生まれました。
特に単独で「わかる」と書くことで、「その気持ち、よくわかる」という共感を簡潔に示す表現として定着しました。
2010年代からTwitterなどのSNSで広く使われるようになり、共感を示す定型表現として進化しました。
「わかりみ」の誕生
「わかりみ」は2010年代後半から2020年代初頭にかけてインターネット上で広まった表現です。
元々は「わかる」の語尾を変化させた「わかりみ」が、オンラインゲームやVTuber(バーチャルYouTuber)コミュニティなどで使われ始め、そこから若者の間で広まりました。
この表現は日本語の文法からすると不自然ですが、あえて文法を崩すことで親しみやすさやユーモアを生み出すインターネットミーム文化の一部として捉えられています。
「わかりみが深い」「わかりみの深海」など派生表現も生まれ、共感の度合いをより強調する表現として使われるようになりました。
共感文化の高まり
SNSの普及により、他者の投稿に共感を示す文化が強まったことも、これらの表現が広まった背景にあります。
特に「いいね」ボタンだけでは表現しきれない深い共感を言葉で示す手段として、「わかる」や「わかりみ」が活用されるようになりました。
テキストだけでのコミュニケーションが増える中で、感情や共感の強さを効果的に伝えるための言語表現が進化してきたのです。
これは日本のコミュニケーション文化がデジタル時代に適応する過程を反映しています。
実践的な例文集
様々な場面での使用例を見ていきましょう。
適切な状況とともに、実践的な例文を紹介します。
日常会話での使用例
「わかる」の使用例
- 友人:「最近、睡眠時間が短くて疲れがたまってる」 あなた:「わかる。私も最近忙しくて睡眠不足だよ」
- 友人:「この映画、ラストシーンで泣いちゃった」 あなた:「わかる!私も涙が止まらなかった」
- 友人:「カフェでパソコン作業すると、つい長居しちゃうんだよね」 あなた:「わかる。ついつい時間を忘れちゃうよね」
- 友人:「夏は暑すぎて外に出たくない」 あなた:「わかる。家でエアコンの効いた部屋にいたいよね」
- 友人:「新しいアプリ、使いにくくない?」 あなた:「わかる!操作が複雑すぎて慣れるまで時間かかりそう」
「わかります」の使用例
- 上司:「このプロジェクト、納期が厳しくて大変ですね」 あなた:「わかります。チームで協力して乗り切りましょう」
- 客:「商品が届くまで時間がかかりすぎるんですよ」 店員:「わかります。ご不便をおかけして申し訳ございません」
- 初対面の人:「初めてのプレゼン、緊張します」 あなた:「わかります。最初は誰でも緊張するものですよ」
- 年配の方:「最近の技術の進歩についていけないことがあります」 あなた:「わかります。私も新しいシステムの適応には時間がかかります」
- セミナー講師:「新しい知識を身につけるのは大変ですよね」 参加者:「わかります。特に実践での応用が難しいと感じています」
「わかりみ」の使用例
- 友人:「好きな曲が突然配信停止になって悲しい」 あなた:「それ、わかりみが深い。先月私も経験したばかり…」
- SNS投稿:「推しが武道館ライブ決まって泣いてる」 コメント:「わかりみしかない!おめでとう!」
- 友人:「レポート締め切り前日に全然進んでなくて絶望してる」 あなた:「それ、わかりみの深海。私も徹夜確定だよ…」
- SNS投稿:「好きな漫画が完結して喪失感やばい」 コメント:「わかりみ…私も終わってほしくなかった」
- 友人:「スマホの電池がすぐ切れて困る」 あなた:「わかりみ。充電器持ち歩くの必須だよね」
SNSでのコメント例
「わかる」のSNS使用例
- 投稿:「リモートワーク中に冷蔵庫を開けすぎて体重が増えた…」 コメント:「わかる〜!ついつい食べちゃうよね😂」
- 投稿:「月曜の朝の電車、つらすぎ問題」 コメント:「わかる。毎週の戦いだよね」
- 投稿:「新作ゲーム、難しすぎて全然進まない」 コメント:「わかる!3回同じところでやられた…」
- 投稿:「家で映画見てるとついつい寝ちゃう現象」 コメント:「わかる…もう3回も最後まで見れてない」
- 投稿:「推しの誕生日に起きれなかった罪悪感…」 コメント:「わかる。アラーム5個セットしたのに…」
「わかります」のSNS使用例
- 投稿:「40代になって初めて英語学習を始めました。難しいですね」 コメント:「わかります。私も大人になってから始めましたが、継続が鍵ですよ」
- 投稿:「子育てしながらの仕事、両立が難しいときがあります」 コメント:「わかります。特に子どもが小さいうちは大変ですよね」
- ビジネスアカウント投稿:「新サービスについてお客様からご意見をいただいております」 コメント:「ご対応お疲れ様です。顧客の声を聞くことの大切さ、わかります」
- 投稿:「転職して3ヶ月、まだ環境に慣れない日々です」 コメント:「わかります。新しい環境への適応には時間がかかるものです」
- 投稿:「初めての海外旅行、不安と期待が入り混じっています」 コメント:「わかります。私も初めての時はドキドキしました。素晴らしい経験になりますよ」
「わかりみ」のSNS使用例
- 投稿:「推しのライブチケットが取れなくて泣いてる」 コメント:「わかりみ…先月の公演も全然取れなかった😭」
- 投稿:「締め切り前日になって急に集中力が出てくる現象」 コメント:「わかりみが深い。いつも前日に徹夜決定する」
- 投稿:「新しいiPhone買った!カメラの性能やばいです😍」 コメント:「わかりみ!私も先週買ったけど写真のクオリティやばすぎ!」
- 投稿:「富士山からの日の出、やばすぎて言葉にならない…✨」 コメント:「わかりみしかない!先月行ったときも感動した!」
- 投稿:「今日のライブやばすぎた…まじ神だった!」 コメント:「わかりみの深海。配信で見てたけど泣いた」
ビジネスシーンでの使用例
適切な例
- 顧客:「納期がもう少し遅くならないでしょうか」 担当者:「ご事情はよくわかります。検討させていただきます」
- 同僚:「締め切りが近くて、プレッシャーを感じています」 あなた:「わかります。チームでサポートできることがあれば言ってください」
- 上司:「この企画書、もう少し具体的に書いてほしい」 部下:「わかりました。修正して再提出いたします」
- 顧客:「サービスの使い方がわかりにくいです」 担当者:「ご指摘ありがとうございます。わかります。改善に向けて検討いたします」
- 同僚:「毎月の報告書作成が負担になっています」 あなた:「わかります。フォーマットを簡略化できないか検討しましょう」
避けるべき例
- 顧客:「この製品の品質に満足していません」 ❌ 担当者:「わかる。次回は改善します」 ✅ 担当者:「ご不満をおかけし申し訳ございません。ご意見はしっかりと受け止め、改善に努めます」
- 上司:「この資料、締め切りに間に合いますか?」 ❌ 部下:「わかりみ。頑張ります」 ✅ 部下:「わかりました。期日までに必ず完成させます」
- 顧客:「説明書が分かりにくいです」 ❌ 担当者:「わかる。みんな言ってます」 ✅ 担当者:「ご指摘ありがとうございます。説明書の改善を検討いたします」
- メール:「プロジェクトの進捗状況を教えてください」 ❌ 返信:「わかる。今調べて連絡します」 ✅ 返信:「ご連絡ありがとうございます。現在の進捗状況を確認し、本日中にご報告いたします」
- 会議中:「この問題についてどう思いますか?」 ❌ 回答:「それ、わかりみしかない」 ✅ 回答:「おっしゃる通りだと思います。特に〇〇の点が重要だと考えています」
言い換え表現
場面や相手に応じて、他の表現に言い換えるのも効果的です。
「わかる」の言い換え
- 「同感」「共感できる」「そうだよね」
- 「確かに」「そうなんだよね」「まさにそれ」
- 「私もそう思う」「納得」「そのとおり」
「わかります」の言い換え
- 「理解しています」「お気持ちはよくわかります」「ごもっともです」
- 「ご指摘の通りです」「おっしゃる通りです」
- 「共感いたします」「認識しております」
「わかりみ」の言い換え
- 「めちゃくちゃわかる」「骨身に染みる」「痛いほどわかる」
- 「激しく共感」「それな!」「完全に理解した」
- 「まさにそれ!」「強く共感」「100%わかる」
まとめ
「わかる」「わかります」「わかりみ」は、いずれも相手への共感を示す表現ですが、使われる状況や持つニュアンスが異なります。
適切な使い分けを心がけることで、より効果的なコミュニケーションが可能になります。
覚えておきたいポイント
- 「わかる」:カジュアルな場面での基本的な共感表現で、親しい間柄で使用するのが最適
- 「わかります」:フォーマルな場面や目上の人との会話で使う丁寧な表現で、ビジネスシーンでは必須
- 「わかりみ」:若者文化(主に10〜30代)に根ざした、強い共感を示すカジュアルな表現
- 場面や相手の年齢・背景に合わせた適切な表現選びが、誤解を防ぐ最大のポイント
- ビジネスシーンでは「わかります」を基本とし、「わかる」「わかりみ」は必ず避ける
これらの表現を状況に合わせて使い分けることで、あなたのコミュニケーション効率は大きく向上するでしょう。
特にSNS時代においては、適切な共感表現を使うことでより良い人間関係を構築できます。
よくある質問(FAQ)
Q1: 「わかりみ」はビジネスの場で使っても良いですか?
A: 基本的には避けるべきです。
「わかりみ」は若者言葉・インターネットスラングであり、ビジネスシーンではフォーマルさに欠けると判断されることがあります。
ビジネスの場では「わかります」「理解しています」などの表現が適切です。
Q2: 「わかる」と「理解する」の違いは何ですか?
A: 「わかる」はより日常的でカジュアルな表現であり、特に共感のニュアンスが強いです。
一方「理解する」はやや客観的・論理的な理解を示す傾向があります。
例えば「あなたの気持ちがわかる」は感情的な共感を、「あなたの状況を理解する」はより客観的な把握を意味します。
Q3: 「わかりみ」の類似表現はありますか?
A: 「共感性」「それな」「わかるすぎる」「それ私」などが類似の強い共感を表すインターネットスラングとして使われています。
これらも「わかりみ」同様、主にカジュアルなオンラインコミュニケーションで使用されます。
Q4: 「わかります」「わかりました」の違いは?
A: 「わかります」は現在形で「理解している・共感している」状態を表すのに対し、「わかりました」は過去形で「今理解した・了解した」という意味合いが強くなります。
共感を示す場合は「わかります」、指示を受けて了解する場合は「わかりました」が自然です。
Q5: 50代以上の人と話すとき、「わかりみ」を使うのは失礼になりますか?
A: 必ずしも失礼とは言えませんが、誤解を招く可能性が高いです。
調査によると、50代以上の約85%が「わかりみ」という表現を知らない、または意味を誤解しているという結果があります。
特に初対面の方や公式な場では避け、「わかります」や「共感します」など、より一般的な表現を選ぶことをお勧めします。
Q6: 「わかりみ」はいつ頃から使われるようになった表現ですか?
A: 「わかりみ」は2010年代後半から2020年代初頭にかけてオンラインゲームやVTuberコミュニティなどで使われ始め、そこから若者の間で広まりました。
インターネットミームとしての特性を持ち、特にSNS上で普及した比較的新しい表現です。
Q7: 仕事のメールで「わかる」と書いてしまいました。問題があるでしょうか?
A: ビジネスメールでは「わかる」よりも「わかります」や「理解しております」などの丁寧な表現を使うのが適切です。
一度だけのミスであれば大きな問題にはならないかもしれませんが、今後は状況に合わせた表現を心がけましょう。
特に目上の人や取引先へのメールでは丁寧な表現を使用することをおすすめします。
Q8: 「わかりみが深い」とはどういう意味ですか?
A: 「わかりみが深い」とは「非常に共感できる」「強く理解できる」という意味の表現です。
「わかりみ」に「深い」を付け加えることで、共感の度合いがさらに強いことを示しています。
主に若者のSNS上で使われる表現で、特に同じ経験や感情を共有していることを強調したい時に使われます。
Q9: 英語に「わかりみ」に相当する表現はありますか?
A: 英語には直接対応する表現はありませんが、”I feel you deeply” や “I totally get that” などが近いニュアンスを持ちます。
また、インターネットスラングとしての特性を考えると、”big mood” や “same energy” などの若者言葉が「わかりみ」の持つ強い共感のニュアンスに近いと言えるでしょう。
Q10: 「わかる」「わかります」「わかりみ」以外に共感を示す日本語表現はありますか?
A: はい、以下のような表現があります。
- 「共感します」:フォーマルな場面で使える丁寧な表現
- 「同感です」:相手の意見に賛同する際に使う表現
- 「それな」:「わかりみ」と同様の若者言葉で強い共感を示す
- 「ごもっとも」:相手の意見が正しいと認める際の丁寧な表現
- 「そうだよね」:カジュアルな場面での軽い共感
- 「まさに」「確かに」:相手の言葉に対する同意を示す表現
これらの表現も、TPOに応じて適切に使い分けることで、より豊かなコミュニケーションが可能になります。