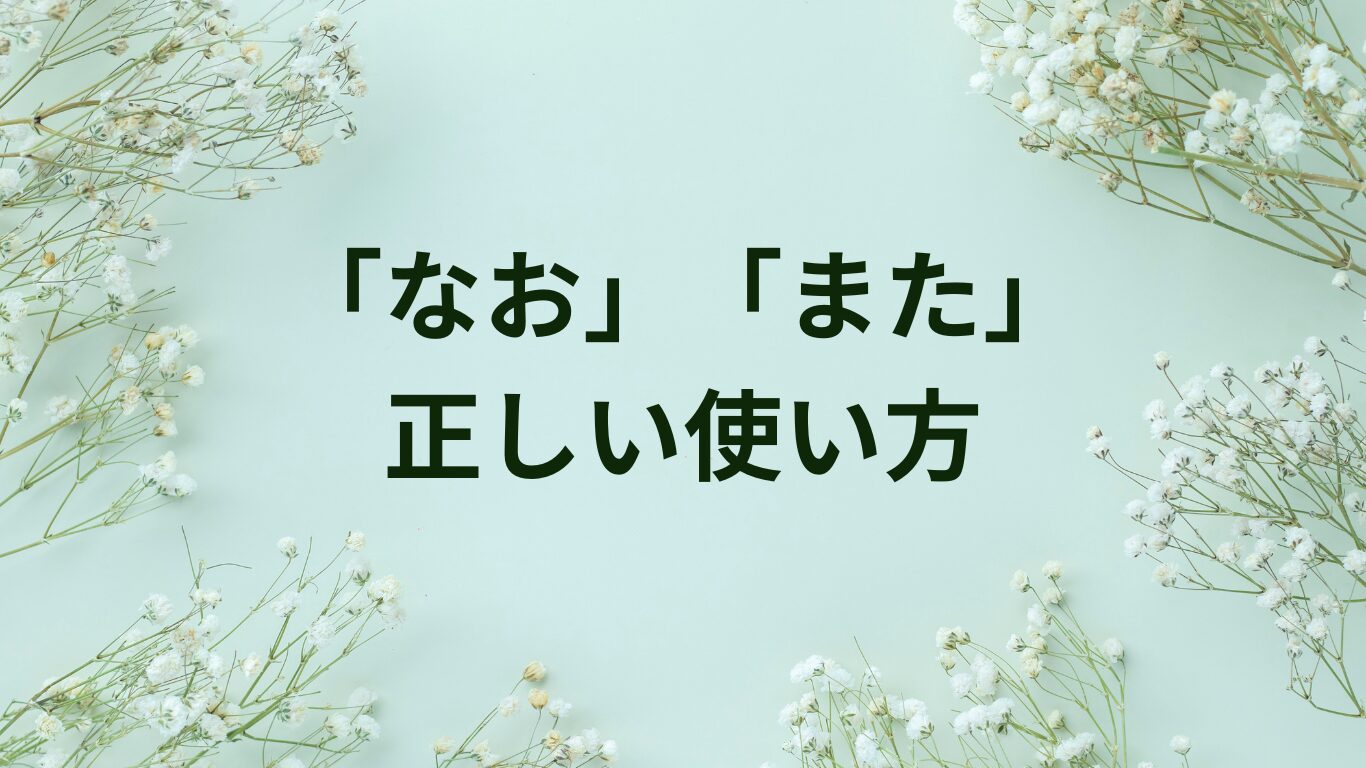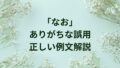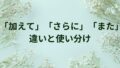試験で差がつく接続語の使い分けマスターガイド
日本語の文章を書く際、「なお」と「また」はどちらも情報を追加するときによく使われる接続語ですが、その微妙な使い分けに悩む方は多いのではないでしょうか。
特に日本語能力試験(JLPT)のN1・N2レベルや日本語検定では、これらの接続語の正しい使い方を問う問題が頻出します。
「なお」と「また」の基本的な違いは、「なお」は主に補足や注意を示すのに対し、「また」は並列的に情報を追加する際に使われます。
しかし、実際の試験問題では、より複雑な文脈判断が求められることが多いです。
この記事でわかること
- 「なお」と「また」の基本的な意味と違い
- 日本語能力試験・日本語検定での出題パターン
- よく間違える例と正しい使い方
- 実践的な例題と詳しい解説
- 試験対策に役立つ使い分けチェックポイント
「なお」「また」の基本的な意味と違い
基本的な意味の違い
「なお」の基本的な意味
「なお」は主に「補足情報の追加」「注意事項の提示」「前述内容に対する付加的な説明」を表します。
前の内容を踏まえたうえで、さらに別の情報や条件を付け加える場合に使用します。
「また」の基本的な意味
「また」は主に「並列的・追加的な情報の提示」「別の視点からの情報追加」を表します。
前述の内容と並列的に新たな情報を加える場合や、話題を少し変えて別の事柄を述べる場合に使用します。
使い分けの比較表
| 項目 | 「なお」 | 「また」 |
|---|---|---|
| 基本的な機能 | 補足・注意を示す | 情報を追加・並列する |
| ニュアンス | 前の内容に関連する付加情報 | 独立した新情報の追加 |
| 文中での位置 | 主に文頭、または文中 | 文頭、または文と文の間 |
| フォーマル度 | やや硬い・書き言葉的 | 汎用性が高い |
| 代表的な表現 | なお~に関しては、なお~の場合 | また~もあります、また~と言えます |
例文比較
「なお」の例文
- 会議は明日10時から開始します。なお、資料は事前に配布済みです。
- 申込期限は今週金曜日です。なお、一度提出した書類は返却できません。
- 商品の発送は来週の予定です。なお、天候により遅延する場合があります。
「また」の例文
- 会議は明日10時から開始します。また、次回の会議は来週水曜日の予定です。
- このアプリは写真編集ができます。また、動画の編集も可能です。
- 彼女は英語が堪能です。また、フランス語も話せます。
「なお」は前述の内容に関連する補足情報を提供するのに対し、「また」はより独立した新しい情報を追加する傾向があります。
日本語検定・JLPTでの頻出パターン
出題形式と頻出パターン
日本語能力試験(JLPT)や日本語検定では、「なお」と「また」の使い分けについて、主に以下のような形式で出題されます。
- 空欄補充問題:文章中の空欄に適切な接続語を選ぶ
- 誤用訂正問題:不適切な接続語の使用を指摘し、正しいものを選ぶ
- 文脈判断問題:複数の文脈から適切な接続語を判断する
試験で出やすい判断ポイント
- 補足か並列か:情報が前文の補足なのか、並列的な追加なのかを判断する
- 文脈の連続性:前後の文脈のつながりの強さで判断する
- 注意喚起の有無:特に注意を促す内容かどうかで判断する
過去問題に出た例
例1:空欄補充問題
「試験の申込期限は5月31日までです。( )、一度申し込むとキャンセルはできませんのでご注意ください。」
A. また B. なお C. ところで D. そして
正解は「B. なお」です。これは申込みに関する注意事項・補足情報を追加しているためです。
例2:誤用訂正問題
「この商品は耐久性に優れています。なお、デザイン性も高く、多くのお客様に好評です。」
この文の「なお」は適切でしょうか?
この文の「なお」は不適切です。
「デザイン性も高く」という部分は、「耐久性に優れている」ことと並列的な特徴を述べているため、「また」の方が適切です。
例題と解説
ここでは、実際の試験で出題されそうな問題を5問用意しました。
まずは自分で考えてから解説を読んでみましょう。
問題1
「新製品の発売日は6月15日です。( )、予約は来週から開始します。」
A. なお B. また C. ところで D. しかし
解説
正解:A. なお
これは発売日に関連する補足情報(予約開始日)を述べているため、「なお」が適切です。
「また」だと、発売日と予約開始日が並列的な独立情報のように感じられます。
問題2
「彼女は英語が堪能です。( )、中国語も話すことができます。」
A. なお B. また C. ただし D. そのため
解説
正解:B. また
英語が堪能なことと中国語も話せることは並列的な情報であり、特に補足や注意ではないため、「また」が適切です。
「なお」を使うと、中国語を話せることが英語に関する補足情報のように感じられてしまいます。
問題3
「会議は10時から始まります。( )、議事録は後日メールで共有します。」
A. なお B. また C. しかし D. そのうえ
解説
正解:A. なお
会議に関する補足情報(議事録の共有方法)を述べているため、「なお」が適切です。
これは会議の進行に直接関わる情報ではなく、後日の対応に関する補足であることがポイントです。
問題4
次の文の「なお」は適切でしょうか、不適切でしょうか。
不適切な場合は、どの接続語が適切かも答えてください。
「このホテルは駅から徒歩5分です。なお、周辺には多くのレストランがあります。」
解説
不適切です。「また」が適切です。
ホテルの立地(駅からの距離)と周辺環境(レストランの多さ)は並列的な情報であり、特に前者に対する補足や注意ではないため、「また」が適切です。
「なお」を使うと、レストランの存在がホテルの立地に関する補足情報のように感じられてしまいます。
問題5
次の対話文の空欄に入る最も適切な表現を選んでください。
田中:「新しいプロジェクトの締め切りはいつですか?」
鈴木:「来月の15日です。( )、中間報告は今月末までに提出してください。」
A. なお B. また C. ところで D. だから
解説
正解:A. なお
プロジェクトの締め切り(来月15日)に関連する注意事項(中間報告の提出期限)を述べているため、「なお」が適切です。
これはプロジェクト全体のスケジュールに関する補足情報です。
学習者のための使い分けチェックポイント
「なお」と「また」を適切に使い分けるために、以下のチェックポイントを活用してください。
使い分け判断フローチャート
- 情報の性質を確認
- 前述の内容に対する補足や注意事項 → 「なお」
- 独立した新しい情報や並列的な内容 → 「また」
- 文脈の関連性を確認
- 前の情報と密接に関連(同一事項の詳細・条件など) → 「なお」
- 前の情報と並列的な関係(別の特徴・別の事例など) → 「また」
- 注意喚起の有無を確認
- 特に注意を促したい情報 → 「なお」
- 単に情報を追加するだけ → 「また」
文脈判断のコツ
- 前後の文脈を読み直す
- 情報同士の関係性を確認する
- 主題との関連性を考える
- 言い換えてみる
- 「なお」なら「付け加えると・補足すると」に置き換えてみる
- 「また」なら「そして・加えて」に置き換えてみる
- 自然に聞こえる方を選ぶ
- 情報の重要度を考える
- 補足的でマイナーな情報 → 「なお」
- メインの情報と同等の重要度 → 「また」
教師・指導者向けの補足アドバイス
指導のポイント
- 文脈重視の指導
- 単語の意味だけでなく、文脈全体を見る習慣をつけさせる
- 前後の文との関係性を意識させる
- 例文の比較
- 同じ文脈で「なお」と「また」を入れ替えた例文を比較させる
- ニュアンスの違いを感じ取らせる
- 実践的な演習
- 実際の文章やメールから例を挙げる
- 学習者自身に文を作らせる
日本語学習者の典型的な間違い
- 「また」の過剰使用
- 補足情報にも「また」を使ってしまう
- 改善法:「なお」の用法を具体例で示す
- 「なお」の不適切な使用
- 並列情報に「なお」を使ってしまう
- 改善法:「なお」は補足・注意用であることを強調
- 文頭での使い方の混同
- メール等で段落の冒頭に「なお」を不適切に使用
- 改善法:文頭の「なお」は前の内容を受けていることを説明
「なお」と「また」の歴史と語源
「なお」と「また」は日本語の長い歴史の中で発展してきた接続語です。
「なお」は元々「猶(なお)」という漢字で表記され、「まだ」「依然として」という意味がありました。
時代と共に用法が広がり、現代では補足情報や注意を追加する接続語として定着しています。
「また」は「又(また)」という漢字で表され、「再び」「更に」という意味がありました。
現代では情報を並列的に追加する接続語として広く使われています。
興味深いことに、書き言葉と話し言葉での使用頻度にも違いがあります。
「なお」は主に書き言葉(特に公式文書やビジネス文書)で使われることが多く、日常会話では比較的使用頻度が低いのに対し、「また」は書き言葉・話し言葉の両方で頻繁に使用されます。
まとめ
「なお」と「また」は似た役割を持つ接続語ですが、使い分けのポイントは明確です。
- 「なお」:前述の内容に対する補足情報や注意事項を追加するときに使用
- 「また」:並列的な情報を追加するときに使用
日本語検定や日本語能力試験では、これらの違いを正確に理解し、文脈に応じて適切に使い分けることが求められます。
本記事で紹介したチェックポイントや例題を参考に、繰り返し練習することで、試験での得点アップだけでなく、より自然な日本語表現を身につけることができるでしょう。
関連記事
- 「なお」「また」「さらに」の違いとは?正しい使い分けと誤用例を徹底解説【例文50選付き】
- 「加えて」「さらに」「また」の違いと使い分け【フォーマル文書の表現技法】
- 外国人のための「なお」「また」完全ガイド|日本語学習者向け使い分け解説【例文30選】
- ビジネスで使える「なお」「また」の使い分け|メール・文書・会話での実践テクニック【例文40選】
- 「なお」は使いすぎ?言い換え表現15選と文例付きで解説
- 「なお」を間違って使っていませんか?ありがちな誤用と正しい例文解説
よくある質問
Q1: 「なお」と「また」はどのような場面で間違えやすいですか?
A: 特に「並列的な情報の追加」と「補足情報の追加」の境界が曖昧な場合に間違えやすいです。
例えば商品の複数の特徴を述べる場合、それが並列的な情報(「また」を使用)なのか、主な特徴に対する補足(「なお」を使用)なのかの判断が難しいことがあります。
Q2: 「なお」と「また」以外に、似た役割を持つ接続語はありますか?
A: 「さらに」「加えて」「その上」「ちなみに」「それから」などが情報の追加に使われる接続語です。
それぞれニュアンスが異なるので、文脈に応じた使い分けが重要です。
Q3: ビジネス文書では「なお」と「また」のどちらがより適切ですか?
A: 状況によって異なります。
補足情報や注意事項を伝える場合は「なお」が適切です。
一方、並列的に複数の情報を伝える場合は「また」が適切です。
ビジネス文書では特に「なお」が多用される傾向があります。