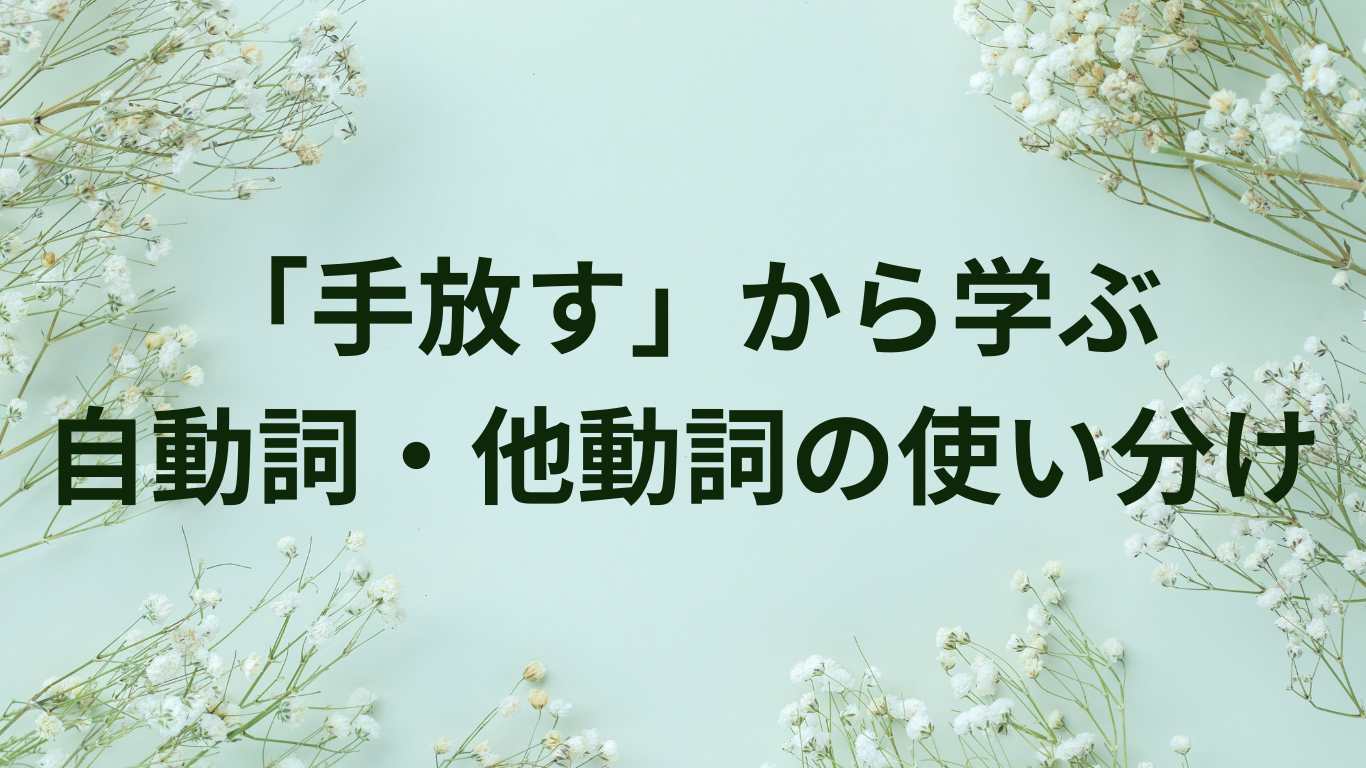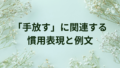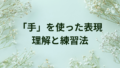日本語学習者にとって、自動詞と他動詞の区別は常に頭を悩ませる問題です。
特に「手放す」のような言葉は、文脈によって使い方が変わるため混乱しやすいものです。
「彼は会社を手放した」「彼の手から品物が手放された」など、同じ「手放す」でも使い方が異なります。
本記事では、「手放す」を例に自動詞と他動詞の違いを徹底解説し、正しい使い分けのコツをお伝えします。
これを読めば、自動詞・他動詞の概念がクリアになり、日本語表現の幅も広がるでしょう。
関連記事
自動詞と他動詞の基本的な意味の違い

自動詞と他動詞は、日本語文法の基本でありながら、最も混乱しやすい概念の一つです。
両者の違いを正確に理解することで、日本語の表現力が格段に向上します。
自動詞とは
自動詞は「〜が」という主語を取り、目的語(〜を)を必要としない動詞です。
主語自身の状態変化や動作を表します。
例えば
- 花が咲く
- 風が吹く
- 彼が歩く
これらの動作は、主語自身が行うもので、動作の対象(目的語)を必要としません。
他動詞とは
他動詞は「〜が〜を」という形式で、主語が目的語に対して働きかける動作を表します。
例えば
- 私が本を読む
- 彼が窓を開ける
- 先生が宿題を出す
他動詞の場合、誰かが「何か」に対して行う動作であるため、目的語が必要になります。
「手放す」の場合
「手放す」は基本的に他動詞として使われますが、文脈によっては自動詞的な使い方もされることがあります。
他動詞としての「手放す」
- 彼は大切な宝石を手放した(彼が=主語、宝石を=目的語)
- 会社は不採算部門を手放すことにした
これは、主体が意図的に「何かを離す・手元から放つ」という意味です。
自動詞的な使い方
- 手から品物が手放された(受身形で自動詞的に)
- つるつるした棒は手放しやすい
この場合、「自然に離れる・放れる」というニュアンスになります。
使い分けのポイント

自動詞と他動詞の使い分けは、場面や意図によって変わります。
「手放す」を例に、具体的な使い分けのポイントを解説します。
意図的な行為か自然な現象か
| 種類 | 意図 | 例文 |
|---|---|---|
| 他動詞 | 意図的に手元から離す | 彼は家業を弟に手放した |
| 自動詞的用法 | 自然に離れる現象 | 強い衝撃で手から品物が手放された |
フォーマル度による使い分け
| 場面 | 表現 | 例文 |
|---|---|---|
| ビジネス・公式文書 | 他動詞+丁寧語 | 当社はこの度、子会社を手放すことといたしました |
| 日常会話 | 自然な表現 | もったいないけど、そろそろ古い服を手放そうかな |
| 文学的表現 | 比喩的表現 | 彼は長年の夢を手放すことができなかった |
感情や抽象概念の場合
物理的なものだけでなく、感情や概念についても「手放す」は使われます
- 思い出を手放す(思い出=目的語)
- 執着を手放す
- 権力を手放す
これらは全て他動詞として使われ、「意図的に離れる・諦める」というニュアンスを持ちます。
よくある間違い & 誤用例

自動詞と他動詞の混同は、日本語学習者だけでなく、日本語母語話者でもよく見られる間違いです。
「手放す」に関連するよくある誤用を見ていきましょう。
助詞の誤用
🚫 彼は大切な宝石が手放した
✅ 彼は大切な宝石を手放した
他動詞「手放す」の場合、目的語には「を」を使います。「が」は主語に使う助詞です。
自他の混同
🚫 品物は手放した(自然に)
✅ 品物が手から放れた/品物は手放された
自然に物が離れた場合は、「放れる」(自動詞)や受身形を使います。
意味の誤解
🚫 新しい商品を手放す(新商品を発売する意味で)
✅ 新しい商品を発売する/市場に出す
「手放す」は「手元から離す・所有を手放す」意味であり、「新たに提供する」意味ではありません。
敬語表現での誤り
🚫 お客様がお品物を手放されました
✅ お客様が品物を手放されました
「お〜を」という組み合わせは避けるべきです。
敬語を使う場合は目的語に「お」をつけないのが原則です。
文化的背景・歴史的背景

「手放す」という表現には、日本文化特有の「所有」と「分離」に関する考え方が反映されています。
「手」の象徴性
日本文化において「手」は所有や支配の象徴とされてきました。
「手に入れる」は獲得を、「手を離れる」は制御不能になることを意味します。
「手放す」はそうした文化的背景から生まれた言葉です。
仏教的な「執着を手放す」概念
日本に深く根付いている仏教では、「執着を捨てる」ことが精神的成長の一部とされています。
現代では「手放す」が物理的な動作だけでなく、精神的な「捨て去る・諦める」意味で使われるのは、こうした文化的背景があるためです。
歴史的用法の変遷
古典文学では「手放す」よりも「手を放す」という表現が多く見られました。
時代とともに漢字一字と動詞の複合形「手放す」が定着していきました。
この言葉が他動詞として確立したのは比較的新しい現象です。
実践的な例文集
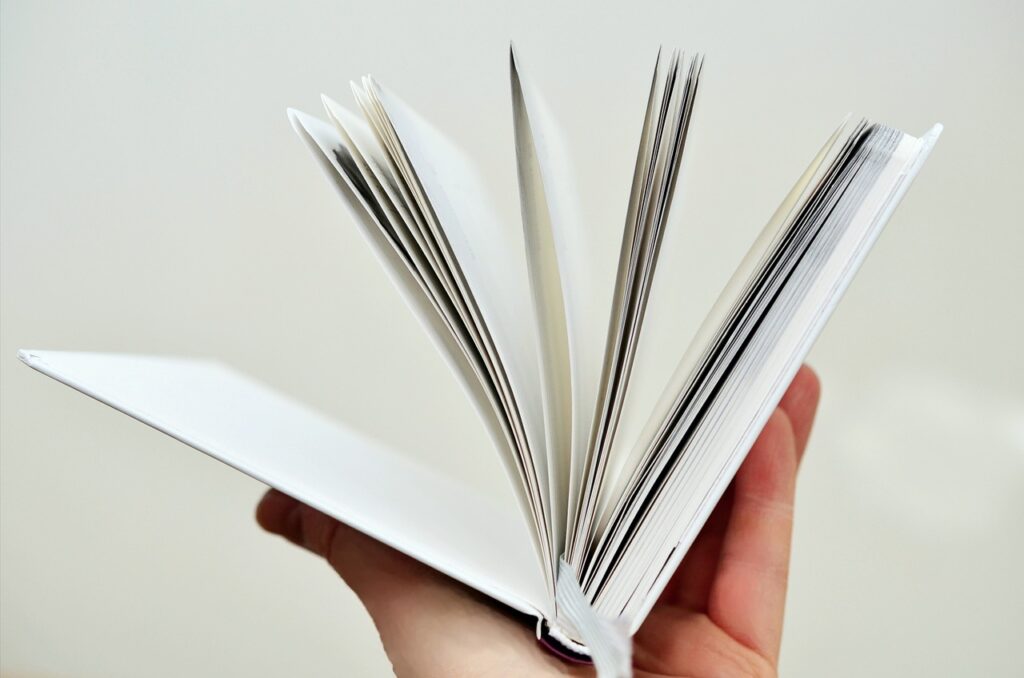
様々な状況での「手放す」の使い方を、例文を通して学びましょう。
日常会話での使用例
- 「引っ越しを機に、使わない物を手放すことにした」
- 「このギターは思い入れがあって、なかなか手放せないんだ」
- 「彼女は過去の失恋の思い出を手放せずにいる」
ビジネスシーンでの使用例
- 「当社は不採算事業を手放し、コア事業に集中する戦略を取っています」
- 「彼は社長の座を手放し、会長に就任した」
- 「優秀な人材を手放さないための施策を検討中です」
文学的・哲学的表現
- 「時には愛する者を手放すことが、最大の愛情表現となる」
- 「過去の栄光を手放せない者には、新たな成功は訪れない」
- 「執着を手放した時、本当の自由が訪れる」
他の動詞との言い換え
- 手放す→手離す、手元から離す、譲る、売却する
- 物を手放す→処分する、捨てる
- 権利を手放す→譲渡する、放棄する
- 感情を手放す→諦める、克服する
まとめ
「手放す」を例に自動詞と他動詞の違いを見てきました。
自動詞と他動詞の理解は、日本語表現の正確さと豊かさに直結します。
覚えておきたいポイント
- 他動詞は「〜が〜を」の形で使い、自動詞は「〜が」のみで使う
- 「手放す」は基本的に他動詞だが、受身形などで自動詞的に使われることもある
- 意図的な行為か自然な現象かで使い分ける
- 物理的な物だけでなく、感情や概念も「手放す」対象になる
- 文脈によって、「諦める」「売却する」「譲る」など、さまざまな意味合いを持つ
自動詞・他動詞の区別は一見難しいですが、実例を通じて学ぶことで徐々に感覚が身についていきます。
日本語の表現力を高めるためにも、この区別を意識して練習してみてください。
関連記事
よくある質問(FAQ)
Q1:「手放す」以外にも自他の区別が紛らわしい動詞はありますか?
A: はい、多くあります。
例えば「開く/開ける」「つく/つける」「割る/割れる」「閉まる/閉める」などが代表的です。
多くの場合、自動詞は「〜る」「〜まる」で終わり、他動詞は「〜す」「〜める」で終わる傾向があります。
Q2:「手放す」を英語に訳すとどうなりますか?
A: 文脈によって異なりますが、物理的に「手放す」場合は “let go of”、所有物を「手放す」なら “give up” や “part with”、権利などを「手放す」なら “relinquish” や “surrender” などが対応します。
Q3:「手放す」を使った慣用表現はありますか?
A: 「二度と手放さない」(大切にし続ける)、「惜しげもなく手放す」(気前よく譲る)、「チャンスを手放す」(機会を逃す)などの表現があります。
Q4:自動詞と他動詞の見分け方のコツはありますか?
A: 「〜を」を伴うかどうかが基本的な見分け方です。
また、動詞の語尾に注目すると、「〜える」「〜す」は他動詞、「〜れる」「〜る」は自動詞であることが多いです(例:見せる/見える、壊す/壊れる)。