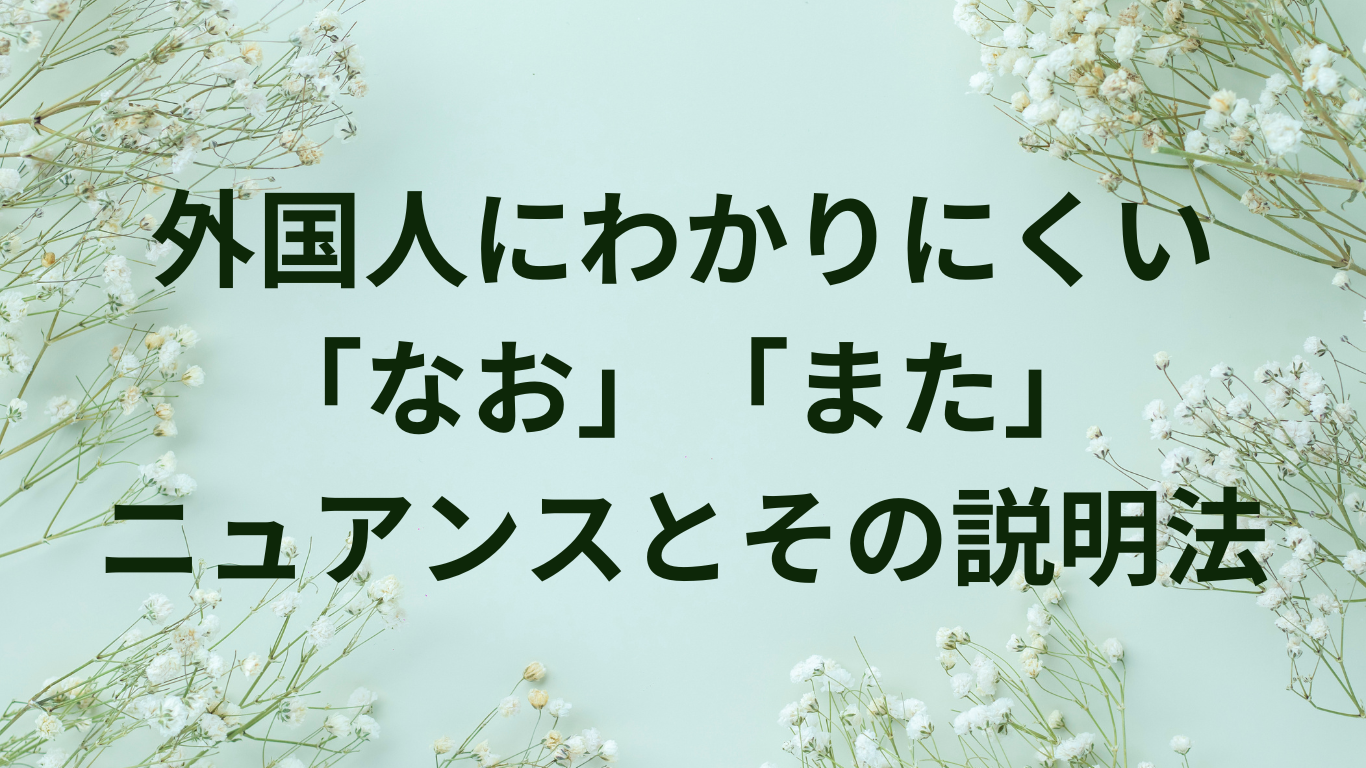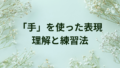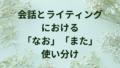日本語学習において、接続語「なお」と「また」の使い分けは多くの学習者が戸惑う点の一つです。
特にビジネス文書や公式な場面では、これらの表現を適切に使用することが求められます。
本記事では、日本語学習者の皆さんに向けて、よくある間違いとその修正方法、基本的な意味の違い、そして実践的な使用方法までを詳しく解説していきます。
この記事でわかること
- 「なお」と「また」の基本的な意味の違い
- 英語の類似表現との比較
- 正しい使い分けのポイント(初級〜上級レベル別)
- 外国人が間違いやすいパターンと修正例
- 実践で使える30の例文
- 練習問題で理解度を確認できる
「なお」「また」の基本的な意味の違い
「なお」と「また」は、どちらも文と文をつなぐ接続語として使われますが、その役割には明確な違いがあります。
「なお」の基本的意味
「なお」は「その上さらに」という意味で、すでに述べたことに対する補足情報や追加的な説明を導入するときに使用します。元の話題に関連する重要な情報や注意点を付け加える場合に適しています。辞書的には「それでもなお」「依然として」という意味もありますが、接続語としては「補足」の意味で使われることが一般的です。
「また」の基本的意味
一方、「また」は「そして」「加えて」という意味で、新たな別の情報や事柄を追加するときに使います。前の内容と並列的に新しい要素を加える場合に適しています。「再び」という時間的な意味でも使われますが、接続語としては「追加」のニュアンスが強くなります。
直感的な例えで理解する
「なお」と「また」の違いを料理に例えると、理解しやすくなります。
「なお」は、メインディッシュを説明した後に「なお、このソースには少量の唐辛子が含まれています」というように、補足情報や注意点を加える調味料のような役割をします。
一方、「また」はコース料理の次の一皿のように、前の料理(情報)と同等に重要な新しい料理(情報)を提供するイメージです。
「なお」と「また」の違いの比較表
| 特徴 | なお | また |
|---|---|---|
| 情報の性質 | 補足説明・付加情報 | 同等の重要性を持つ別情報 |
| イメージ | 脚注・調味料 | 新しい料理の一皿 |
| フォーマル度 | 高め(特に文書で多用) | 中〜高(会話でも文書でも使用) |
| 英語の近い表現 | additionally, furthermore, moreover | also, as well, moreover |
| 代用可能な日本語表現 | ちなみに、付け加えると | そして、それから |
英語と日本語の接続詞の比較
外国人学習者にとって、母国語との比較は理解の助けになります。ここでは、英語圏の学習者向けに、英語の類似表現と「なお」「また」の対応関係を説明します。
「なお」に近い英語表現
- “Furthermore” – 補足情報を加える点で類似していますが、「なお」の方が副次的・補足的なニュアンスが強いです
- “Moreover” – 追加情報を示す点で類似していますが、「なお」は主題から少し離れた補足にも使えます
- “Additionally” – 補足的な情報を加える点で「なお」に近いですが、「なお」には注意喚起のニュアンスもあります
- “By the way” – カジュアルな会話での「なお」に近いですが、「なお」の方がフォーマルです
「また」に近い英語表現
- “Also” – 同等の情報を追加する点で「また」に最も近い表現です
- “In addition” – 情報を加える点で類似していますが、「また」の方が並列性が強いです
- “Moreover” – 前述の内容に追加する点で似ていますが、「また」はより独立した情報の追加にも使えます
- “Furthermore” – 論点を発展させる点では似ていますが、「また」は独立した情報の追加にも適しています
注意点
英語の接続詞と日本語の「なお」「また」は完全に対応するわけではありません。
文脈や使用状況によって適切な訳し分けが必要です。
例えば、”Furthermore” は文脈によって「さらに」「また」「なお」のいずれにも訳し分けられます。
使い分けのポイント(レベル別)
日本語のレベルに応じた「なお」「また」の使い分けのポイントを解説します。
初級レベル(JLPT N4-N5相当)
基本的な使い分け
- 「また」は “also” や “and” のように、新しい情報を加える時に使います
- 「なお」は注意点や例外を伝える時に使います
簡単な例文
- 私は日本語を勉強しています。また、英語も話せます。
- 明日、パーティーがあります。なお、開始時間は7時です。
初級者へのアドバイス
- まずは「また」から使えるようになりましょう。日常会話でより頻繁に使われます
- 「なお」は主にビジネスメールや書き言葉で覚えていきましょう
中級レベル(JLPT N3-N2相当)
より精密な使い分け
- 「また」は同等の重要性を持つ情報を追加するときに使います
- 「なお」は主題に関連する補足情報や条件を述べる時に使います
- 文章構造の中での適切な位置を意識しましょう
中級向け例文
- この本は内容が充実しています。また、イラストも豊富で分かりやすいです。
- 研修は来週の月曜日に行われます。なお、参加できない場合は事前に連絡してください。
中級者へのアドバイス
- 両方の接続詞を意識的に使い分ける練習をしましょう
- ニュースや新聞で実際の使用例を観察すると効果的です
上級レベル(JLPT N1相当・ビジネスレベル)
高度な使い分け
- 「なお」と「また」の微妙なニュアンスの違いを理解し、文脈に応じて使い分けます
- フォーマル度や文章のジャンルに応じた適切な選択ができるようになります
- 「なお」「また」だけでなく、類似の接続詞(さらに、加えて、ちなみに、など)との使い分けも習得します
上級向け例文
- 当社の第3四半期決算は前年同期比10%増となりました。また、営業利益率も2ポイント改善しております。なお、地域別の詳細な数値につきましては、添付資料をご参照ください。
- 彼の論文は独創的な視点から問題を考察しています。また、実証的なデータに基づいた議論展開も説得力があります。なお、この研究手法は従来の枠組みを超えたものであるため、批判的な見解も一部あることをご承知おきください。
上級者へのアドバイス
- ビジネス文書や学術論文などの専門的な文章で、接続詞の選択が論理構造にどう影響するかを意識しましょう
- 自分の書いた文章を日本語母語話者にチェックしてもらうことで、微妙なニュアンスの違いを掴むことができます
よくある間違い & 誤用例
外国人学習者がよく間違える「なお」と「また」の使用例を見てみましょう。
「なお」の誤用例
🚫 誤用例1:「なお」を並列的な情報に使う
誤: この商品は500円です。なお、あの商品は300円です。
✅ 正: この商品は500円です。また、あの商品は300円です。
(解説: ここでは二つの商品の価格を並列的に紹介しているため、「また」が適切です)
🚫 誤用例2:「なお」を新しい話題の導入に使う
誤: 彼は英語が上手です。なお、彼はフランス語も話せます。
✅ 正: 彼は英語が上手です。また、彼はフランス語も話せます。
(解説: 話せる言語を並列的に紹介する場合は「また」が自然です)
「また」の誤用例
🚫 誤用例1:「また」を補足説明に使う
誤: 開店時間は9時です。また、駐車場は裏にあります。
✅ 正: 開店時間は9時です。なお、駐車場は裏にあります。
(解説: 開店時間という主情報に対し、駐車場の位置は補足情報なので「なお」が適切です)
🚫 誤用例2:「また」を注意事項の説明に使う
誤: 申込期限は明日までです。また、申込用紙の記入は黒ペンでお願いします。
✅ 正: 申込期限は明日までです。なお、申込用紙の記入は黒ペンでお願いします。
(解説: 期限という主要情報に対して、記入具の指定は細かい補足なので「なお」が適切です)
「なお」と「また」の文化的・歴史的背景
これらの接続詞の使い分けの難しさは、日本語の文脈依存性と「察する文化」に根ざしています。
「なお」の語源と発展
「なお」(尚)は元々「なほ」という発音で、「まだ・さらに」という意味の副詞でした。
平安時代の文学作品にも登場し、時間的な継続や程度の強調を表していました。
現代では書き言葉としての性格が強まり、特に公文書やビジネス文書で補足情報を丁寧に提示する役割を担っています。
「また」の語源と発展
「また」(亦・又)は古くから「再び」や「加えて」の意味で使われてきました。
日本の伝統的な縦書き文化において、横に並ぶ項目を示す役割も担ってきました。
「また」は話し言葉としても書き言葉としても広く使われる汎用性の高い接続詞として発展してきました。
日本文化との関連
日本語のコミュニケーションでは、情報の重要度や関係性を明示的に示す接続詞が発達しています。
これは「言わなくても分かるはず」という文化的背景がある一方で、誤解を避けるために情報の位置づけを繊細に表現する必要性から生まれたものです。
「なお」と「また」の使い分けは、この日本語特有の情報の階層化と関連しています。
文書の論理性と明確さを重視する日本のビジネス文化では、特に「なお」が重用されます。
一方、日本語の会話では「また」がより自然に使われる傾向があり、文化的な文脈によって使い分けられています。
実践的な例文集(場面別30選)
様々な場面での「なお」と「また」の使用例を見てみましょう。
日常会話での使用例
「なお」の日常会話例文
- 明日の集合時間は10時だよ。なお、雨が降ったら中止になるからね。
- このレシピで作ると美味しいよ。なお、材料の牛乳は必ず常温に戻してから使ってね。
- 映画は7時からだから、6時半には集合しよう。なお、チケットは私が予約済みだから安心して。
- この電車は新宿に行きます。なお、途中で乗り換えが必要です。
- 彼の誕生日は来週です。なお、サプライズパーティーを計画していることは秘密にしておいてください。
「また」の日常会話例文
- 彼は英語がペラペラで、海外でも困らないよ。また、フランス語も少し話せるから、ヨーロッパ旅行にはぴったりの同行者だね。
- このカフェはコーヒーが美味しいんだ。また、ケーキもハンドメイドで評判がいいよ。
- 週末は友達と買い物に行く予定。また、その後で新しくオープンした映画館にも行ってみようと思っているんだ。
- 私は音楽が好きです。また、映画を見ることも好きです。
- この本はストーリーが面白いです。また、イラストも素晴らしいです。
ビジネスシーンでの使用例
「なお」のビジネス例文
- 会議の主な議題についてはすでにお知らせしましたが、なお、会場が変更になりましたのでご注意ください。
- ご注文いただいた商品は来週発送予定です。なお、北海道・沖縄への配送は2日ほど余分にお時間をいただきます。
- お見積書を添付いたします。なお、納期につきましては別途ご相談させていただければ幸いです。
- セミナーへのお申し込みありがとうございます。なお、当日は会場が混雑することが予想されますので、お時間に余裕をもってお越しください。
- 契約期間は1年間となります。なお、期間満了の1ヶ月前までに申し出がない場合は自動更新されます。
「また」のビジネス例文
- 新商品のパンフレットを同封いたします。また、期間限定のキャンペーンも実施しておりますので、ぜひご利用ください。
- 会議では予算案について議論します。また、新プロジェクトのスケジュールについても確認する予定です。
- お見積書を添付いたします。また、類似商品のカタログも同封いたしましたので、ご検討の参考にしていただければ幸いです。
- セミナーへのお申し込みありがとうございます。また、事前アンケートにもご協力いただければ幸いです。
- 当社は東京と大阪に支社があります。また、来年には福岡にも新支社を開設する予定です。
学術・論文での使用例
「なお」の学術例文
- 本研究では質的分析手法を採用した。なお、インタビューデータの収集方法の詳細については第3章で説明する。
- 実験結果は表1に示した通りである。なお、統計的有意差が認められなかったデータは省略している。
- この実験結果からXという結論が導かれる。なお、温度条件によっては結果が異なる可能性がある。
- 本論文では日本語の助詞について議論する。なお、方言による違いについては扱わない。
- サンプルサイズは100名である。なお、年齢分布は20代から50代まで均等になるよう調整した。
「また」の学術例文
- 第一の実験では視覚刺激に対する反応時間を測定した。また、第二の実験では聴覚刺激についても同様の測定を行った。
- 従来の理論では説明できない現象が観察された。また、先行研究との比較からも新たな理論構築の必要性が示唆された。
- 植物の成長には光の強度が影響する。また、波長の違いによっても成長パターンが変化することが明らかになった。
- この手法は計算コストを50%削減できる。また、精度も従来手法を上回る。
- 日本語の助詞は文法的機能を持つ。また、話者の意図や感情を表現する役割も担っている。
練習問題
以下の文章の空欄に適切な接続詞(「なお」または「また」)を入れてみましょう。
- 来週の会議は水曜日に変更になりました。( )、開始時間は予定通り10時からです。
- この製品は防水機能があります。( )、耐久性も高く、長期間ご使用いただけます。
- 入場料は大人1000円、子供500円です。( )、3歳以下のお子様は無料となります。
- 日本語能力試験は年に2回実施されています。( )、受験会場は全国の主要都市にあります。
- ホテルのチェックインは15時からです。( )、早めに到着された場合は、荷物をお預かりすることができます。
- このレストランは和食が評判です。( )、イタリア料理も提供しています。
- 申込書は郵送でお送りください。( )、必ず締切日までに到着するようにお願いします。
- この薬は1日3回服用してください。( )、食後に飲むのが効果的です。
- 彼女は英語が堪能です。( )、中国語も話すことができます。
- 明日の天気は晴れの予報です。( )、風が強くなる可能性もありますので、ご注意ください。
答え
- なお(補足説明)
- また(並列的な特徴の追加)
- なお(補足・例外の説明)
- また(並列的な情報の追加)
- なお(補足情報)
- また(新しい情報の追加)
- なお(注意点の補足)
- なお(補足的なアドバイス)
- また(並列的な能力の追加)
- なお(注意点の補足)
まとめ
「なお」と「また」の違いを理解し、適切に使い分けることは、洗練された日本語表現への第一歩です。
覚えておきたいポイント
- 「なお」は補足情報・例外事項・但し書きを示す(脚注のようなイメージ)
- 「また」は同等の重要性を持つ情報の追加・並列を示す(新しい箇条書き項目のイメージ)
- フォーマルな文書では両方とも頻繁に使われるが、カジュアルな会話では「また」の方が一般的
- 情報の関係性(主従関係か並列関係か)で使い分けを判断する
- 日本語レベルに応じて使い分けを段階的に習得するのが効果的
「なお」と「また」の適切な使い分けを身につけることで、あなたの日本語はより自然で洗練されたものになります。
日々の学習と実践を通じて、これらの表現を使いこなせるようになりましょう。
「なお」の代わりに使える表現集はこちら ▶︎“なお”は使いすぎ?言い換え表現15選と文例付きで解説
関連記事
- 「なお」「また」「さらに」の違いとは?正しい使い分けと誤用例を徹底解説【例文50選付き】
- ビジネスで使える「なお」「また」の使い分け|メール・文書・会話での実践テクニック【例文40選】
- 「なお」を間違って使っていませんか?ありがちな誤用と正しい例文解説
- 「なお」「また」の正しい使い方と頻出ポイント|日本語検定対策
よくある質問(FAQ)
Q1:「なお」と「また」を同じ文章で使うことはありますか?
A:はい、あります。
複数の情報を追加する際に、重要度や関係性に応じて使い分けることができます。
例えば「会議は10時からです。また、資料は事前に配布します。なお、会場は変更になる可能性があります。」
Q2:「なお」は文章の最初に使えますか?
A:通常、「なお」は何らかの先行情報に対する補足として使われるため、文章の最初には使いにくいです。
ただし、前の文脈を受けた段落の冒頭などでは使用可能です。
Q3:「また」と「そして」の違いは何ですか?
A:「また」は並列的な追加を表すのに対し、「そして」は時間的順序や論理的展開を示すことが多いです。
「また」は新しい項目の追加、「そして」は流れの中での次のステップを示す傾向があります。
Q4:英語では「なお」と「また」をどのように訳し分けますか?
A:文脈によって異なりますが、「なお」は “furthermore”、”moreover”、”additionally”、”by the way” などに、「また」は “also”、”moreover”、”in addition”、”furthermore” などに相当します。
ただし、完全に対応する表現はなく、状況に応じた訳し分けが必要です。
Q5:話し言葉では「なお」と「また」はどう使い分けられていますか?
A:話し言葉では「また」の方が一般的に使われています。
「なお」は少しフォーマルな印象があり、講演やプレゼンテーションなどで使われることが多いです。
日常会話では「なお」の代わりに「ちなみに」や「それから」などが使われることもあります。