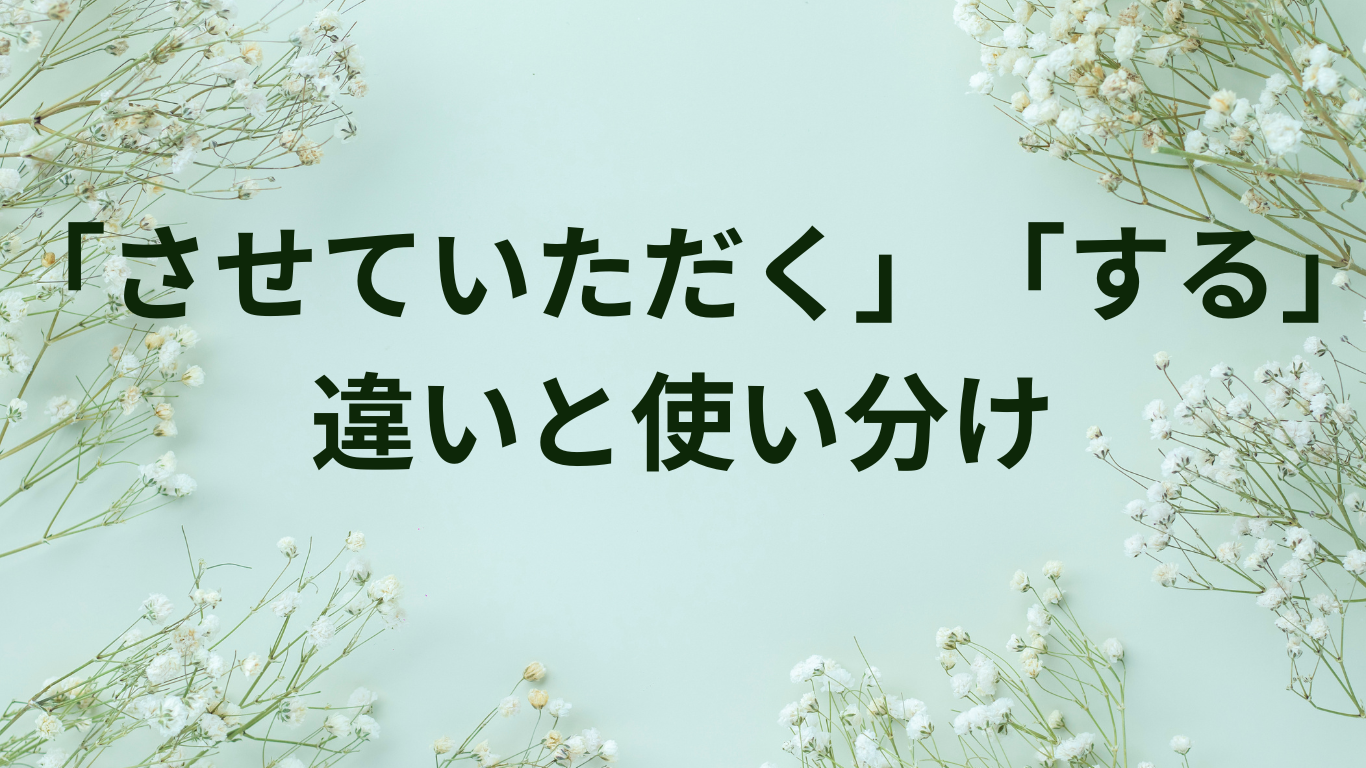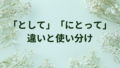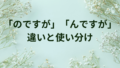ビジネスシーンでは「させていただく」をよく耳にしますが、使い過ぎると違和感を与えることもあります。
一方、「する」は基本的な表現ですが、場面によっては失礼に感じられることも。
この記事では、「させていただく」と「する」の違いと適切な使い分けについて、具体例を交えながら詳しく解説します。
この記事でわかること
- 「させていただく」と「する」の本質的な意味の違い
- それぞれの表現が適切な場面と具体的な使用例
- 「させていただく」の過剰使用を避けるためのポイント
- ビジネスシーンでの適切な使い分け方
- 日常会話での自然な表現方法
「させていただく」と「する」の基本的な意味
日本語の敬語表現において、「させていただく」と「する」は、同じ行動を表現する際によく使用される表現です。
しかし、その丁寧さのレベルや適切な使用場面には大きな違いがあります。
ここでは、それぞれの表現の基本的な意味と特徴を詳しく解説していきます。
まずは、両者の本質的な意味の違いを理解することから始めましょう。
「させていただく」の基本的な意味
「させていただく」は、日本語の敬語表現の中でも特に丁寧な謙譲表現として知られています。
相手や周囲の人々への深い配慮を示すとともに、行動の許可を得たことへの感謝の意も込められた表現形式です。
この表現は、ビジネスシーンや公式な場面で頻繁に使用される重要な敬語表現の一つとなっています。
主な構成要素は以下の通りです
- 動詞の使役形「させる」による行動の間接化
- 謙譲語「いただく」による敬意の表現
- 二つの要素の組み合わせによる丁寧さの強調
- 相手からの許可や承認の含意
- 話者の謙虚な態度の表明
この表現の本質的な意味は、「相手の許可や恩恵のもとで行動をさせてもらう」という、話者の謙虚な立場と相手への敬意を同時に表現することにあります。
正しく使用することで、円滑なコミュニケーションと良好な人間関係の構築に役立ちます。
ただし、過剰な使用は逆効果となる可能性もあるため、状況に応じた適切な判断が求められます。
「する」の基本的な意味
「する」は日本語の基本動詞として最も頻繁に使用される表現の一つです。
シンプルながら非常に汎用性が高く、様々な場面で活用できる重要な動詞です。
特に日常会話やカジュアルなコミュニケーションにおいて、自然な表現として広く受け入れられています。
相手への特別な配慮を示す必要がない場面での標準的な選択肢となっています。
基本的な特徴は以下の通りです
- 行動や状態の変化を直接的に表現する
- 特別な配慮や謙譲の意味を含まない
- 状況に応じて「します」という丁寧語に変化可能
- 多様な名詞と組み合わせて使用できる
- 文脈に応じて様々な意味を表現できる
「する」は基本形であるがゆえに、その使用範囲は非常に広く、日本語学習において最初に習得すべき重要動詞の一つとされています。
丁寧語「します」の形にすることで、基本的な敬意を示すことも可能であり、場面や状況に応じて柔軟に使い分けることができます。
ただし、フォーマルな場面や特別な配慮が必要な状況では、より丁寧な表現を選択する必要があります。
「させていただく」と「する」の主な違い
「させていただく」と「する」には、丁寧さのレベルや使用される場面において、いくつかの重要な違いがあります。
これらの違いを正しく理解することで、状況に応じた適切な表現の選択が可能になります。
ここでは、両者の主な違いについて、具体的な例を交えながら詳しく見ていきましょう。
丁寧さのレベル
日本語の敬語表現において、「させていただく」と「する」は丁寧さのレベルが大きく異なります。
この違いは、場面や相手との関係性に応じて適切な表現を選択する際の重要な判断基準となります。
特にビジネスシーンでは、この丁寧さのレベルの違いが、コミュニケーションの成否に大きく影響することがあります。
両者の丁寧さの特徴は以下の通りです
「させていただく」の特徴
- 最も丁寧な表現の一つ
- 相手への深い敬意を明確に示す
- フォーマルで慎重な印象を与える
- 謙譲の意を含む
- ビジネス文書に適している
「する」の特徴
- 基本的な丁寧さのレベル
- 中立的で自然な印象
- カジュアルな雰囲気
- 直接的な表現
- 日常会話に適している
丁寧さのレベルは、コミュニケーションの質を左右する重要な要素です。
過度に丁寧すぎる表現を使用すると、かえって違和感を与えたり、コミュニケーションの障害となったりする可能性があります。
また、状況に応じた適切な丁寧さのレベルを選択することで、より自然で効果的なコミュニケーションが可能となります。
使用される場面の違い
「させていただく」と「する」は、使用される場面によって、その適切さと効果が大きく異なります。
それぞれの表現には、最も効果的に機能する特定の状況や文脈があり、これらを正しく理解することが、適切なコミュニケーションの鍵となります。
特に、フォーマル度の高い場面とカジュアルな場面での使い分けは、重要なポイントとなっています。
それぞれの表現に適した場面は以下の通りです
「させていただく」が適している場面
- ビジネスの正式な会議や商談
- 公式文書や企画書の作成
- プレゼンテーションや発表
- 目上の人との重要な会話
- お客様対応の場面
「する」が適している場面
- 日常的な会話や雑談
- 友人や家族との対話
- カジュアルな文書やメール
- 社内の打ち合わせ
- SNSでの投稿
場面に応じた適切な表現の選択は、円滑なコミュニケーションの基本となります。
特に、ビジネスシーンでは、状況を正しく判断し、適切な表現を選択する能力が重要です。
また、同じ相手でも、状況によって使い分けることで、より効果的なコミュニケーションが可能となります。
「させていただく」が適切な場面・例文
「させていただく」は、特に相手への配慮や敬意を示す必要がある場面で重要な役割を果たします。
ビジネスシーンやフォーマルな場面では、この表現を適切に使用することで、円滑なコミュニケーションを図ることができます。
以下で、具体的な使用場面と例文を詳しく見ていきましょう。
ビジネスシーンでの使用例
ビジネスシーンでは「させていただく」の使用が一般的です。
特に、取引先や上司とのコミュニケーション、公式な文書作成、プレゼンテーションなどの場面で重要となります。
この表現を適切に使用することで、ビジネスマナーを守りつつ、相手への敬意と配慮を示すことができます。
具体的な使用例は以下の通りです
- 申し出や提案の場面:「新しい企画を提案させていただきます」
- 依頼や確認の際:「書類を確認させていただきたいのですが」
- 報告や説明の時:「進捗状況についてご報告させていただきます」
- 商談や会議の場面:「弊社の製品をご紹介させていただきます」
- お詫びの際:「大変申し訳ございません。再度確認させていただきます」
ただし、ビジネスシーンでも場面や状況によっては「する」の使用が自然な場合もあります。
特に、社内の日常的なコミュニケーションや、すでに合意済みの事項について話す際は、「させていただく」の使用が過剰になる可能性があるため、状況に応じた適切な判断が必要です。
フォーマルな場面での使用例
フォーマルな場面での適切な表現の選択は、円滑なコミュニケーションの鍵となります。
特に、式典やセレモニー、公式なスピーチ、重要な文書作成など、高い格式が求められる場面では、「させていただく」の使用が効果的です。
このような場面での適切な敬語使用は、場の雰囲気を整え、参加者への敬意を示す重要な要素となります。
フォーマルな場面での具体的な使用例
- 式典での挨拶:「本日の司会を務めさせていただきます」
- 講演や発表:「本日のテーマについてお話しさせていただきます」
- 感謝の表明:「長年のご愛顧に感謝させていただきます」
- お詫びの場面:「この度はご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げさせていただきます」
- 申し出の際:「ご提案をさせていただきたく存じます」
フォーマルな場面での「させていただく」の使用は、単なる形式的な丁寧さを超えて、場の格式と参加者への配慮を示す重要な役割を果たします。
ただし、同じフォーマルな場面でも、文脈や状況によっては適切な表現が異なる場合があるため、場の雰囲気や参加者の関係性を考慮した判断が必要です。
「する」が適切な場面・例文
「する」は日本語の基本的な動詞として、多様な場面で使用される表現です。
特に日常的なコミュニケーションや、過度な敬意表現が不要な場面では、この表現を使用することで自然な会話が可能となります。
ここでは、「する」が適切な具体的な場面と例文を紹介していきます。
日常会話での使用例
日常会話では、基本的に「する」を使用することで、自然で円滑なコミュニケーションが可能となります。
友人や家族との会話、日常的な社内のやり取り、カジュアルな場面など、特別な配慮が必要ない状況では、「する」の使用が適切です。
過度に丁寧な表現を避けることで、より親しみやすく自然な会話の流れを作ることができます。
日常的な会話での使用例
- 予定の説明:「今日は早めに帰ります」
- 行動の表明:「映画を見に行きます」
- 状況の説明:「週末は買い物に行きます」
- 意思の伝達:「この本を読むことにします」
- 日常的な報告:「明日から新しい趣味を始めます」
日常会話における「する」の使用は、コミュニケーションの自然さと親しみやすさを維持する重要な要素です。
ただし、相手や状況によっては、より丁寧な表現が必要となる場合もあるため、会話の文脈や相手との関係性を考慮しながら、適切な表現レベルを選択することが大切です。
カジュアルな文書での使用例
カジュアルな文書コミュニケーションでは、「する」を基本とした表現を使用することで、読みやすく親しみやすい文章を作成することができます。
SNSでの投稿、個人的なメール、インフォーマルな社内連絡など、形式張らない文書では、自然な表現として「する」を選択することが効果的です。
過度な敬語表現を避けることで、読み手に負担をかけない文章となります。
カジュアルな文書での具体的な使用例
- 一般的なメール:「明日の予定を確認します」
- SNSでの投稿:「新しい趣味を始めます」
- 社内チャット:「資料を添付します」
- 個人的な連絡:「週末の予定を連絡します」
- インフォーマルな報告:「進捗状況を報告します」
カジュアルな文書における「する」の使用は、文章の読みやすさと親しみやすさを保つ重要な要素となります。
ただし、同じカジュアルな文書でも、状況や受信者によっては適切な丁寧さのレベルが異なる場合があるため、文書の目的や読み手との関係性を考慮した表現の選択が必要です。
よくある間違いと注意点
「させていただく」と「する」の使い分けにおいて、しばしば見られる間違いや注意すべきポイントがあります。
特に「させていただく」の過剰使用は、かえってコミュニケーションの障害となる可能性があります。
以下で、代表的な間違いとその改善方法について解説していきます。
過剰使用を避けるべき場面
「させていただく」の過剰使用は、かえってコミュニケーションの自然さを損なう原因となります。
特に、相手の許可や恩恵が関係しない場面や、日常的な行動を説明する際に使用すると、不自然さや違和感を生じさせる可能性があります。
このような過剰使用は、ビジネスの場面でもしばしば問題となっています。
以下のような場面では、「する」を使用する方が自然です
- 日常的な行動の説明(「今日は早く帰ります」)
- 単純な事実の陳述(「会議は3時から始まります」)
- 相手の許可や恩恵が関係ない場面(「資料を確認します」)
- 定型的な業務連絡(「明日の予定をお知らせします」)
- すでに合意済みの事項の実行(「契約書を送付します」)
過剰な「させていただく」の使用は、しばしば「マニュアル敬語」や「過剰敬語」として批判の対象となることがあります。
本来の謙譲表現としての意味を理解し、適切な場面で使用することが重要です。
また、組織の文化や業界の慣習によっても適切な使用頻度は異なってくるため、周囲の状況をよく観察し、バランスの取れた表現を心がけることが推奨されます。
適切な表現の選び方
状況に応じた適切な表現の選択は、円滑なコミュニケーションの基本となります。
「させていただく」と「する」の選択は、場面のフォーマル度、相手との関係性、組織の文化など、複数の要素を総合的に判断する必要があります。
特に、ビジネスシーンでは、これらの要素を慎重に検討することが重要です。
表現を選ぶ際の主なポイントは以下の通りです
- 場面のフォーマル度(公式会議、日常会話、社内打ち合わせなど)
- 相手との関係性(取引先、上司、同僚、部下など)
- 文書の種類(企画書、報告書、社内メール、チャットなど)
- 組織や業界の慣習(業界標準的な表現、社内での一般的な使用例)
- コミュニケーションの目的(依頼、報告、提案、相談など)
適切な表現の選択には、状況に応じた柔軟な判断が求められます。
過度に形式的になりすぎず、かといって軽すぎる印象を与えないよう、バランスの取れた表現を心がけることが大切です。
また、同じ相手でも、場面や文脈によって適切な表現が変わることもあるため、状況に応じて柔軟に使い分けることをお勧めします。
まとめ
「させていただく」と「する」の使い分けは、コミュニケーションの質に大きく影響します。
それぞれの特徴をまとめると
- 「させていただく」は謙譲の意を含む丁寧な表現で、フォーマルな場面やビジネスシーンで適切
- 「する」は基本的な表現で、日常会話や一般的なコミュニケーションで自然に使用可能
使い分けのポイント
- 場面のフォーマル度に応じて選択
- 相手との関係性を考慮
- 過剰な丁寧表現は避ける
- 文脈に合わせて適切に使用
実践的なアドバイスとして、まずは基本の「する」を中心に使い、フォーマルな場面や特別な配慮が必要な状況で「させていただく」を使用することをお勧めします。
よくある質問(FAQ)
敬語表現の使い分けについて、よく寄せられる質問にお答えします。
ここでは、「させていただく」と「する」に関する具体的な疑問点を解消し、より自然な日本語の使用をサポートします。
「させていただく」は過剰な敬語表現?
相手や状況に応じて適切に使用すれば、過剰な表現とはなりません。
ただし、以下の点に注意が必要です
- 本来必要のない場面での使用は避ける
- 文章全体のトーンとの調和を考慮する
- 相手への実質的な配慮が伴っているか確認する
ビジネスメールではどちらを使うべき?
状況と相手によって使い分けます
- 社外の取引先:「させていただく」を基本とする
- 社内の同僚:「する」の丁寧形「します」で十分
- 上司への報告:状況に応じて使い分ける
「させていただく」は必ず謙譲の意味を持つ?
基本的には謙譲の意味を持ちますが、近年では慣用句として使われることも増えています。
ただし、本来の意味を理解した上で使用することが望ましいでしょう。